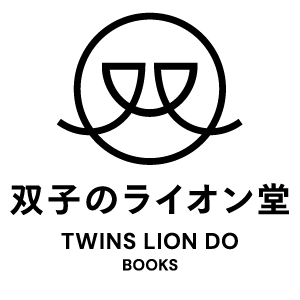【新刊】『本の町は、アマゾンより強い』仲俣暁生
¥1,320 税込
残り1点
なら 手数料無料で 月々¥440から
別途送料がかかります。送料を確認する
B6判・並製/64ページ
日本全国で書店が減少し続けた2010年代から2020年代にかけて、独立ウェブメディアの『マガジン航』やリトルマガジンに発表した「出版」「書店」「メディア」をめぐるエッセイを精選収録。先行発売した『もなかと羊羹』の前史にあたる時期のエピソードが掲載されています。本と人との関係を根底から考え直すヒントに満ちた、「行動する人」のための小冊子。
【本書に収録したエッセイ】
・本の町は、アマゾンより強い
・アイヒマンであってはならない
・「真の名」をめぐる闘争
・ZINEの生態系とローカリティ
・論じるよりも、その一部になりたかった
── 一九九〇年代ウェブ私史
・インディ文芸誌は文芸復興の担い手になるか
"新しい古書店がいくつもできたことで、下北沢は「本の町」として、静かに動き始めた。その流れの先に「本屋B&B」が登場したことで、この町の目に見えない〝本をめぐるネットワーク〟が完成した感がある。アマゾンがどんなに便利でも、それに負けない力をこのネットワークはもっている。"(「本の町は、アマゾンより強い」より)
あとがき
本書は二〇一三年から二〇二〇年までの間に、私自身が編集発行人であるウェブメディア「マガジン航」やその他の媒体に発表した、出版や書店を主題とする文章をあつめたものだ。書かれた時点の状況をそのまま残すため、掲載にあたっての改稿は最低限度にとどめ、その後の変化については【追記】というかたちで補足した。
二〇一〇年代は日本の出版産業が水面下で大きな変化を迎えた時期だった。本書に収めた文章のなかでいちばん新しいのは二〇二〇年二月の〈「真の名」をめぐる闘争〉だが、この後に日本は本格的に新型コロナウイルスのパンデミックに襲われ、社会的なロックダウンの日々が続いた。本書は「それ以前」の記録だが、「以後」に起きる激変の前触れが「地下水」(鶴見俊輔)のように、本の世界のさまざまな場所で同時多発的に起きた時代でもあった。
「誰にも頼まれていないけど自分が作りたいから作る自主的な出版物」(野中モモ)、あるいは津野海太郎のいう「小さなメディア」。それらの系譜の先に、私がいまごろになってようやく実践しはじめた「軽出版」の営みがある。そのことを明らかにしたいというのが本書をまとめた最大の動機である。この本はその意味で、二〇二四年に刊行した拙著『もなかと羊羹──あるいはいかにして私は出版の未来を心配するのをやめて軽出版者になったか。」で書かなかった「前史」の部分にあたる。
それぞれの文章の主題は書店(本屋)だったり、ウェブやインターネットだったり、文芸だったりするが、通して読んでいただいた方はお気づきのとおり、どの文章にも「ネットワーク」「つながり」「生態系」「コミュニティ」「共同体」といったモチーフが繰りかえし立ち現れている。
二〇一〇年代は私にとって、多くの仲間を得た時代でもあった。
「独立(系)書店」や「一人出版社」といった出版業界のなかでのあらたな動きだけでなく、電子書籍による自己出版(セルプパブリッシング)、「文学フリマ」や「東京アートブックフェア(TABF)」のようなリトルプレスやジンを扱う即売イベント、「ノベルジャム」や「ブンゲイファイトクラブ」といった公開型の文芸創作イベントなど、「紙かデジタルか」といったありがちな対立構図を超えた、さまざまな試みが始まり、広まった。その一部には私自身も参加し、自分よりはるかに若い世代と協働する機会があった。それがどれほど貴重な体験であったか、自分自身でもささやかな出版活動を始めて、ようやく身に沁みてわかるようになった。
本書の中で具体的に名を挙げた方々(一部敬称略で失礼しました)だけでなく、日本中で〝本をめぐるネットワーク〟をかたちづくる人たちに、この本を捧げたい。
二〇二四年 大晦日
阿佐ヶ谷にて 著者記す
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について