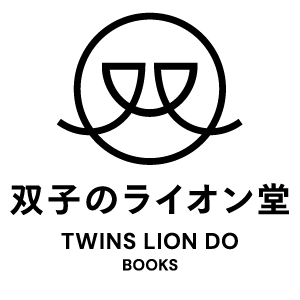-

【新刊】『旧ソビエト連邦を歩く』星野藍
¥2,420
SOLD OUT
A5判/192ページ 気鋭の女性写真家による、前世紀の夢の跡をめぐる旅 それはまるで近未来のような、あるいはディストピアのような風景 【内容紹介】 共産主義を掲げ理想の国家建設を目指すも、1991年に崩壊を迎えたソビエト連邦。直後の混乱も30年以上経過した現在ではほぼ収束し、立ち入りが難しかった旧ソ連の構成国に興味を持つ人や、失われた国家の痕跡を見るために実際に足を踏み入れる人も増えています。 本書は、旧ソビエト連邦に何度も足を運んできた経験を持つ女性写真家・星野藍による旅行記です。彼女は、旧ソ連の構成国15カ国をすべて旅して写真に収めてきました。さらに、国として認めておらず、入国が極めて困難な“未承認国家”4カ国(ナゴルノ・カラバフ、アブハジア、南オセチア、沿ドニエストル)にも入っています。 フォトグラファー・星野藍がこれまで撮影してきた“巨大建造物”をはじめ、旅を進める中で目にしてきた景色や街中の生活風景、人々との出会いなど、多数の写真と紀行文で構成する一冊です。 【構成】 ■第1章 ロシアほか4カ国 ウクライナ、ロシア、モルドバ、沿ドニエストル、ベラルーシ ■第2章 中央アジア5カ国 ウズベキスタン、キルギス、トルクメニスタン、カザフスタン、タジキスタン ■第3章 バルト三国 リトアニア、ラトビア、エストニア ■第4章 コーカサス3国ほか ジョージア、南オセチア、アブハジア、 アルメニア、アゼルバイジャン、ナゴルノ・カラバフ ■コラム ……etc. 【著者】 星野藍 福島県出身。写真家・グラフィックデザイナー。軍艦島をきっかけに、廃墟を被写体として撮影を始める。旧共産圏や未承認国家に強く惹かれ、近年縦横無尽に巡っている。「APAアワード2024」金丸重嶺賞、「名取洋之助写真賞」奨励賞を受賞。著書に『幽玄廃墟』『旧共産遺産』『未承認国家アブハジア 魂の土地、生きとし生けるものと廃墟』などがある。
-

【新刊】『到来する女たち 石牟礼道子・中村きい子・森崎和江の思想文学』渡邊英理
¥2,640
SOLD OUT
四六判/400ページ じんぶん大賞2026 18位 不揃いなままで「わたし」が「わたしたち」になる──。 1958年に創刊された雑誌『サークル村』に集った石牟礼道子、中村きい子、森崎和江が聞書きなどの手法で切り拓いた新たな地平を、『中上健次論』が話題を呼んだ著者が「思想文学」の視点で読み解く。 「『サークル村』を通して、彼女たちが手に入れたのは、儚い「わたし」(たち)の小さな「声」を顕すための言葉であったにちがいない。この新しい集団の言葉は、異質なものと接触し遭遇することで自らを鍛え、異質な他者とともに葛藤を抱えながらも不透明な現実を生きようとする言葉でなければならなかった。支配や権力、垂直的な位階制や序列的な差別から自由で、不揃いなままで水平的に「わたし」は「わたしたち」になる。 三人の女たちは、そのような「わたし」と「わたしたち」を創造/想像し、「わたし」と「わたしたち」とを表現しうる言葉を発明しようとしたのではなかったか」(渡邊英理) ・石牟礼道子(1927-2018)【熊本】……熊本県天草生まれ。詩人、作家。生後すぐに水俣へ。著書に『苦海浄土』『椿の海の記』『西南役伝説』ほか。 ・中村きい子(1928-1996)【鹿児島】……鹿児島生まれ。小説家、作家。母をモデルにした小説『女と刀』は大きな話題を呼び、木下恵介監督によりドラマ化もされた。 ・森崎和江(1927-2022)【福岡】……朝鮮大邱生まれ。詩人、作家。17歳で単身九州へ渡り、58年筑豊炭鉱近郊の中間に転居、谷川雁らと『サークル村』創刊。著書に『まっくら』『慶州は母の呼び声』『非所有の所有』など。
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日』惣田大海水
¥1,430
A6判/232ページ 【内容】 わたしはきっと父親と同じように、いつか首を吊って死ぬだろうを思いこんで、でも残った家族に、もう一度自殺した人間の骨を見せるわけにいかないと必死だった生活を抜け、いつの間にか死ななくてもよい日々がそこにあった。しかし、だからといって、その後は楽しく幸せに生きていきました、めでたしめでたし、とはならなかった。ある日、父親が首を吊る原因となった土地を、売ってほしいという手紙が届く。ヤングケアラーがヤングでなくなった後、どう生きれば穏やかな日々を手に入れられるか、死にたかった人が死にたくなくなった後、どう生きれば人生を楽しめるのか、を模索した日日の日記。(2023年7月から2024年4月までの日記を収録)
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日2』惣田大海水
¥1,320
A6判/163ページ 【内容】 私が求めているのは、死にたい気持ちのその先にもきっとあるであろう、穏やかな生活である。穏やかな生活を手に入れるためには、きっと今のままでは駄目で、私は自分の土台を固める必要がある。しかし、仕事の環境が変化し、どうにもこうにも慌ただしく、自分と向き合うどころではない。カウンセリングに行くべきか、行かざるべきか三万光年ほど検討し、ついに心理士の元へ行く、そんな日々の記録。(2024月5月から2024年10月までの日記を収録)
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日3』惣田大海水
¥1,650
A6判/299ページ 【内容】 死ななくてよくなったからこそ、やっと通うことが出来るようになったカウンセリング。父親とは、母親とは、自分とは、いったいどういう人間なのか。体内に残存する子供のころの家庭環境というブラックボックスを、心理士との対話の中で再度考え直していく「カウンセリング日記」を含む日日の記録。(2024年11月から2025年7月までの日記を収録)
-

【新刊】『本屋の人生』伊野尾宏之
¥1,870
四六/224ページ 昭和三十二年開店、 令和八年閉店。 材木屋をたたみとりあえず本屋を開いた父。 フリーターからとりあえず本屋を継いだ息子。 新宿・中井の親子二代にわたる本屋の記録と営み。 伊野尾書店は、ただそこにあるだけの店だった。 [目次] 閉店の挨拶 “とりあえず“の本屋の69年 本屋の息子として生まれて 店の風景 店売のFくん あとがき
-

【新刊】『高円寺グルメガイド 青』海猫沢めろん
¥750
A6横とじ/32P 海猫沢めろんさんによる高円寺グルメガイドの最新版、青です。 最初の「高円寺グルメガイド」はこちら! https://shop.liondo.jp/items/103640701
-

【新刊】『踊る幽霊』オルタナ旧市街
¥1,650
四六判/168ページ “いつまででも読んでいられるしどこまででも歩いていけると思った。ずれて輝く記憶と世界、軽妙さと誠実さ、私はオルタナ旧市街を信頼する。” ――芥川賞作家・小山田浩子さん、推薦。 【内容】 巣鴨で踊る老婆、銀座の魔法のステッキ男、流通センターのゆで太郎から始まる妄想、横浜中華街での怪異、不穏な水戸出張……街をめぐる断片的な21篇。 わたしたちは瑣末なことから日々忘れて暮らしている。忘れないと暮らしていけないとも思う。わたしとあなたの断片をみっともなく増やしていこう。何度でも覚え直せばいいし、何度でも忘れていい。 インディーズシーンで注目を集める謎多き匿名作家・オルタナ旧市街が、空想と現実を行き来しながら編み出した待望のデビュー・エッセイ集。 “誰の記憶にも残らなければ、書き残されることもない。それはそれで自然なのかもしれないけれど、身の回りに起こったことの、より瑣末なほうを選び取って記録しておく行為は、未来に対するちょっとしたプレゼントのようなものだと思う。”(表題作「踊る幽霊」より) 誰にでも思いあたる(いや、もしかしたらそれはあなたのものだったのかもしれない)この記憶のスクラップ帳は、書かれるべき特異な出来事も起きなければ、特殊な事情を抱えた個人でもない「凡庸」な人々にこそ開かれている。 【目次】 踊る幽霊[巣鴨] されども廻る[品川] 反芻とダイアローグ[水戸] スクラップ・スプリング[御茶ノ水] 午前8時のまぼろし[駒込] 老犬とケーキ[東陽町] タチヒの女[立川] 麺がゆでられる永遠[流通センター] アフターサービス[横浜] 大観覧車の夜に[お台場] ウィンドウショッピングにはうってつけの[五反田] おひとりさま探偵クラブ[銀座] 白昼夢のぱらいそ[箱根] 聖餐[吉祥寺] 愛はどこへもいかない[小岩] 猫の額でサーカス[浅草] がらんどう[南千住] さよなら地下迷宮[馬喰町] (not) lost in translation[渋谷] 見えざる眼[秋葉原] テールランプの複製[八重洲]
-

【新刊】『私は私に私が日記をつけていることを秘密にしている』古賀及子
¥1,870
四六判/p280ページ/ 人気の日記エッセイ作家が明かす、 みんなに読まれる日記の秘密。 「文学フリマ」が毎回入場者数を更新し、日記本がブームになり、自分でも日記を書きたい・noteで公開したい・ZINEにまとめたい……という人が増えているなか、日記エッセイストの第一人者が、日記を書く際の独自の経験知と秘密を大公開。その実践例としての日記もあわせて収録。日記を読みたい人にも、書きたい人にも、いますぐ役立つアイデアと実例が満載の、これからの日記作家に捧ぐメタ日記エッセイ。
-

【新刊】『つくって食べる日々の話』
¥2,420
四六判・ソフトカバー/160ページ これ絶対、おいしい本! 食の文芸、最前線の一冊がついに発売 人気小説家や食エッセイの第一人者、ノンフィクションライターなど様々な分野で活躍する16名の表現者による「料理と生活」をテーマにした書き下ろしエッセイ集。 執筆 平松洋子/円城塔/スズキナオ/春日武彦/大平一枝/白央篤司/牧野伊三夫/阿古真理/絶対に終電を逃さない女/辻本力/オカヤイヅミ/島崎森哉/宮崎智之/松永良平/ツレヅレハナコ/滝口悠生
-

【新刊】『「若者の読書離れ」というウソ: 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』飯田一史
¥1,078
新書判・ソフトカバー/264ページ この20年間で、小中学生の平均読書冊数はV字回復した。そんな中、なぜ「若者は本を読まない」という事実と異なる説が当たり前のように語られるのだろうか。各種データと10代が実際に読んでいる人気の本から、中高生が本に求める「三大ニーズ」とそれに応える「四つの型」を提示する。「TikTok売れ」の実情や、変わりゆくラノベの読者層、広がる短篇集の需要など、読書を通じZ世代のカルチャーにも迫る。
-

【新刊】『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』飯田一史
¥1,540
新書判・ソフトカバー/288ページ 日本人の本の「読む量」は減っていない。「買う量」が減っている。 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の著者による、本の「売上を伸ばす」ための提言。 「本が売れない」と1990年代後半から言われ始め、四半世紀以上経った。書店の閉店が相次ぐなか、2024年以降、国策による書店振興への取り組みが話題を集めた。だが、それらで語られている現状分析には誤りが含まれている。出版産業の問題は読書(読む)量ではなく購買(買う)量である。本書ではまず、出版業界をめぐる神話、クリシェ(決まり文句)を排して正しい現状を認識する。その上でデジタルコミック、ウェブ小説、欧米の新聞や出版社、書店の先進事例やマーケティングの学術研究から判明した示唆をもとに、出版社と書店に共通する課題ーー「売上を伸ばす」ために何ができるかを提案していく。
-

【新刊】『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか: 知られざる戦後書店抗争史』飯田一史
¥1,320
新書判・ソフトカバー/366頁 かつて本屋は「帰り道にふらっと寄る」場所だった。だが、いつのまにか町から本屋の姿はなくなり、「わざわざ行く」場所になってしまっている。いったいいつから、どのようにして、本屋は消えていったのか? 本書では、出版社・取次・書店をめぐる取引関係、定価販売といった出版流通の基本構造を整理した上で、戦後の書店が歩んだ闘争の歴史をテーマごとにたどる。 公正取引委員会との攻防、郊外型複合書店からモール内大型書店への移り変わり、鉄道会社系書店の登場、図書館での新刊書籍の貸出、ネット書店の台頭――。 膨大なデータの分析からは、書店が直面してきた苦境と、それに抗い続けた闘争の歴史が見えてくる。「書店がつぶれていく」という問題の根幹を明らかにする一冊。
-

【新刊】『よりぬきのん記2024』スズキロク
¥1,100
新書判・並製/244p 「『のん記』を読み始めてからというもの、仕事や生活で疲れたときに浮かぶのは、もうすっかり「ツカツカレンコン」だ。」 石山蓮華(電線愛好家・TBSラジオ「こねくと」パーソナリティ) 「ドンキ前でドンギマってのん記もって集合!」 矢野利裕(批評家) イラストレーター、漫画家、歌人のスズキロクによるエッセイ4コマ本新刊です。 ぬいぐるみと布団が好きでくいしんぼうな「妻」と、 本とレコードが好きで、ぬいぐるみに厳しい「夫」の、 いろいろあっても結局、なんだかのんきな毎日。 2024年1月から12月まで毎日X(旧Twitter)の鍵アカウントでひっそりと発表された4コマから、多めによりぬいています。 巻末解説はTBSラジオ「こねくと」メインパーソナリティで電線愛好家、石山蓮華さん!
-

【新刊】『をとめよ素晴らしき人生を得よ―女人短歌のレジスタンス』瀬戸夏子
¥2,090
四六判/256ページ 注目を集めたウェブ連載に、 書き下ろしを加えた待望の書籍化。 語られてこなかった女性歌人たちのレジスタンスを、 現代によみがえらせる。 『はつなつみずうみ分光器』の著者が挑む、 女たちの群像伝記エッセイ。 * * * 「きちんと目を向けさえすれば、ちゃんとわかることなのだった。 彼女たちの存在も、彼女たちの歌の価値も。」 ――本書「はじめに」より 1949年、女性だけの短歌結社「女人短歌会」と歌誌「女人短歌」が誕生した。 戦後短歌において独自の場を築き、数多くの才能を送り出してきたにもかかわらず、 彼女たちの活動は十分に顧みられてこなかった。 短歌をはじめ、さまざまな表現領域に光を当ててきた著者が、 男性優位の世界に抗いながら独創的な歌を詠みつづけた女性たちの姿と作品、 知られざるシスターフッドの軌跡を、 時を越えて鮮やかに描き出す。 「この本を読むあなたたちへ。 彼女たちの声も歌も、 おそらく未来のあなたたちに捧げられている。 絡みあった複雑な旋律を、 どうか、耳を澄まして聴いてほしい。」 巻末には、登場する女性歌人たちの作品から著者が選出し、 一首評を加えた精選120首のアンソロジーを収録。 装丁:アルビレオ 装画:三岸節子 本文カット:朝倉摂 【目次】 はじめに 第1章 大西民子と北沢郁子 第2章 片山廣子と「物語の女」 第3章 斎藤史とコンスタンス・マルキエヴィッチ 補章01 アガサ・クリスティーと中島梓 第4章 北見志保子と川上小夜子 第5章 五島美代子と五島ひとみ 第6章 長沢美津と「女人短歌」 補章02 もうひとつの大西民子と北沢郁子、あるいはデーリン・ニグリオファ、ミア・カンキマキ、ケイト・ザンブレノ 第7章 中城ふみ子と中井英夫 第8章 穂積生萩と釈迢空 第9章 河野愛子と「アララギ」 第10章 葛原妙子と森岡貞香 おわりに 付録「をとめよ素晴らしき人生を得よ」アンソロジー 主要参考文献
-

【新刊】『「手に負えない」を編みなおす』友田とん(サイン本)
¥1,980
四六判/248ページ 「言葉も、記憶も、インフラだったのか!」 地下鉄の漏水対策の観察から始まる、暮らしと探究のクロニクル。予測不能な脱線の果てに目にした景色とは――。 『『百年の孤独』を代わりに読む』著者、待望の新作! 「ユーモアも文章力も本当にすごい。でも何より、なんでもなさそうなものにまなざし、愛でる感性に胸打たれ、嫉妬しました」――星野概念さん(精神科医)も推薦! 【あらすじ】 十年近く前に「地下鉄の漏水対策」に心を奪われ、極私的なフィールドワークを続けてきた著者。その過程で気づいたのは、人が手当てをすることで維持されている「手に負えない」ものに、なぜか心惹かれてしまう自身の性質だった。 「手に負えない」ものたちとのちょうどいい向き合い方を見つけたい。だが、解決の糸口をつかむたびに新たな「手に負えない」が発生し、圧倒されてしまう。果たしてこの本を、無事に閉じることはできるのか! 予測不能な脱線の果てにある、謎の感動をあなたに。 【目次】 まえがき 第一部 地下鉄にも雨は降る 第一回 探しものはなんですか? 第二回 上を向いて歩こう 第三回 この恍惚を味わいたかったのかもしれない 第四回 管理台帳の姿を想像しながら 第五回 地方の地下鉄も見に行く 第六回 手に負えない 第二部 手に負えないものたちと暮らしてみる 第一章 さかのぼる 第二章 見る 第三章 作る 第四章 編みなおす あとがき
-

【新刊】鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』
¥1,870
四六判/264ページ 言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった「常識」を覆し、「シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っている」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ。 【編集担当からのおすすめ情報】 本書の草稿を拝読したとき、何より感動したのは、鈴木先生が「シジュウカラのことが好きだ、もっと知りたい」というまっすぐな気持ちで、自然の中に身を置いて根気強く鳥たちをよく観察する姿勢でした。文系、理系、アウトドア派、インドア派問わず、何かを「好き」と思う気持ちを大事にすることで、日常生活の中でも新鮮な驚きや気づきが得られ、ひいては世界的な発見にまで繋がる--これは読者の皆さまにとっても、ポジティブなメッセージとなることと思います。 本文内のイラストもすべて鈴木先生自身によるもの! 細部までかわいらしく描かれているのは、愛と興味をもって丁寧に相手を観察する鈴木先生ならではのタッチです。
-

【新刊】『AI先生のSF小説教室 ─ クリエイティブVibe ライティング入門』樋口恭介
¥1,980
四六/280ページ 読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している!AIによる小説執筆入門の決定版。 書き始めない言い訳として、「時間がない」も「才能がない」もLLM(Large Language Model/大規模言語モデル)の前では)通用しない。 ── 九段理江 ChatGTP、Claude、Geminiなど生成AIによって、SF、ミステリ、ホラー、ライトノベルなどジャンル小説の書き方は劇的に変わった。 AI推進のコンサルタントであり、作家・批評家でもある著者が、作家を志す人に向けてAIを活用した小説執筆のプロセスを詳細に解説。 SF短編小説『量子図書館の調律師』を執筆する全過程(アイデア、主題、キャラクター設定、プロットづくり、シーン設計からブラッシュアップまで)をさまざまなプロンプトとともに公開。 ソフトウェア開発のトレンドである「Vibe Coding」の手法を小説執筆に応用したメソッドで、読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している。AIによる小説執筆入門の決定版! ──────────────────────── “創作の世界において、まさに革命的な時代が始まっています。100年前の作家たちがタイプライターの登場に目を見張り、その可能性に胸を躍らせたように、私たちは今、LLMという新たな創作メディアの黎明期に立ち会っているのです。未来の作家たちは、この時代をどのように回顧するでしょうか。おそらく、「テクノロジーと人間の創造性が、かつてない形で融合し始めた、刺激的な転換点」として記憶されるのではないでしょうか。”(「はじめに」より) ──────────────────────── 【目次】 はじめに LLM(Large Language Model/大規模言語モデル)初心者のための基礎知識 序章 Creative Vibe Writing とは Chapter 1 5分でAI小説を書いてみよう(超速ハンズオン) Chapter 2 Vibe設計ワークショップ Chapter 3 キャラクターを生成する Chapter 4 世界観を構築する Chapter 5 プロットとシーン設計 Chapter 6 スタイル & 声のコントロール Chapter 7 反復改良と編集術 Chapter 8 小説のブラッシュアップと完成 Chapter 8.5 AI時代の創作倫理と著作権:共創の未来を考える(特別コラム) 付録1:他ジャンルへの応用──CVWの可能性を広げる 付録2:AI共創コミュニティと未来のコラボレーション 付録3:実践トラブルシューティングガイド──AIとの対話で困ったときに 付録4:用語集と推薦リソース──CVWの旅をさらに深めるために あとがき
-

【新刊】『緑をみる人』村田あやこ
¥2,640
四六変形/384ページ 名もなき緑を日々見守る、世界の“隙間植物愛好家”たち アスファルトのひび割れやマンホール蓋のふち、側溝の奥底、室外機の下……。 整備された都市空間の隙間で、人知れず芽吹き繁茂する植物たち。 「路上園芸鑑賞家」として発信を続ける著者は、街の隙間に生きる緑に自身の秘めた「野性」を重ね、その制御不能さに心惹かれ続けている。 本書では、著者が世界13カ国18人の“隙間植物愛好家”にコンタクトを取り、約2年にわたって取材を重ねた。 水抜き穴協会・モリタケンイチは、水抜き穴という小さな穴に広がる生態系に「小宇宙」をみる。 イタリア在住のパオロ・カスパーニは、路上の植物に「勇敢さ」と「しぶとさ」をみる。 スウェーデンの元テレビマン、スタファン・フィッシャーは植物が生きる隙間に「ミニチュアの世界」をみる。 オランダの芸術家・アン・ゲーネは植物の「不完全さ」に「完璧」をみる。 メキシコのデザイナー・アストリッド・ストゥーペンと文化人類学者のステファニー・スアレスは、都市の植物から「パラレルな時間の流れ」を垣間みる。 日本、フランス、トルコ、メキシコ、韓国、台湾、イタリア、スウェーデン、ブラジル、シンガポール、アメリカ、オランダ、ニュージーランド。ぜんぶで19人の緑をみる人たち。それぞれのストーリーと総数800枚もの写真をとおしてみえてくるのは、日常にひそむ地球の「野生」だ。 (巻末に英訳掲載) <目次> PART1:著者が15年ほど前から撮りためてきた、日本の路上でみつけた隙間植物の写真395枚を掲載。 ●はみ出す緑に自身の「野性」を重ねる/村田あやこ(botaworks) PART2:著者がSNSで知り合った「中の人」など、世界の隙間植物愛好家18人にコンタクトをとりインタビュー。それぞれが撮りためた写真も紹介する。 ●植物はどんな場所でも生きるすべを見つける/フランソワ・デコベック(Plants of Babylon) ●小さな穴の中に広がる小宇宙/モリタ ケンイチ(水抜き穴協会) ●定形の空間に、不定形のものが生まれる楽しさ/まつ(東京自由植物) ●人間も、足元の植物たちも、自然の一部/エレクトリックアイ(parts.of.nature) ●都市の植物は、自然と人工物とを融合させる存在/ケレム・オザン・バイラクター(Sokak Otları) ●都市の植物から垣間見える、パラレルな時間の流れ/アストリッド・ストゥーペン&ステファニー・スアレス(Planta De Asfalto) ●都市の小さな亀裂から、命が始まる/イ・ユンジュ(botanicity) ●植物は、都市にぬくもりと活気をもたらす/トム・ルーク(Treehouses of Taiwan) ●路上の植物たちは勇敢でしぶとい/パオロ・カスパーニ(being_weeds) ●植物が生きる小さな隙間は、まるでミニチュアの世界/スタファン・フィッシャー(Trottoaser) ●どんな場所でも、植物はただそこに存在する/エリサ・ヌネス(arvorexiste) ●人間と同じように、都市には多様な植物が生きている/サラ・セオ(Urban Lithophytes) ●人間界のルールの隙間に、植物のエネルギーが噴出する/山田泰之(路上盆栽) ●都市に自生する植物は、生態系にとって重要な存在/デビッド・サイター(Spontaneous Urban Plants) ●不完全さこそ植物の完璧な姿/アン・ゲーネ(Book of Plants) ●道端の草たちが、街への愛着を取り戻してくれる/重本晋平(まちくさ) ●困難な状況でも生きる植物たちの美しさ/ダニエラ・フエンザリダ(Aesthetics Of The Resistance) PART3:PART2に登場する18人+著者が撮影した写真215枚を、シチュエーションごとに整理して掲載。 あとがき
-

【新刊】『継続するコツ』坂口恭平
¥1,760
四六判・並製/240ページ みなさん、継続することは得意ですか? 得意な人はこの本は手に取っていないと思いますから、おそらくちょっと苦手ですよね。 一方、僕は継続することがむちゃくちゃ得意です。なんか自慢みたいで申し訳ありません。 でもその代わりといってはなんですが、別に質が良いわけではないと思います。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 執筆、絵描き、作詞・作曲、「いのっちの電話」…… どれも20年以上つづけてきた、スランプ知らずの継続マニア・坂口恭平さんが見つけた、 「やりたいこと」をつづけるコツが1冊に! 僕も挑戦している最中です。 最中であればいいんです。継続中ってことですから _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 多くの人は、何かをやろうとして、手をつけはじめて、 無事に完成することができたとしても、 それが売れないだとか、人から評価されないだとか、そういった不遇を味わい、 自信を失い、徒労感ばかりを感じるようになり、いずれはやめてしまうようです。 僕はいつも、もったいない!と思ってしまいます。 だって、作っているときのほうが楽しいですもん。 つまり、何かを継続しているときのほうが、楽しいんです。 この馬鹿みたいに単純なことに、僕は気づいたんです。
-

【新刊】『文学カウンセリング入門』チン・ウニョン 、キム・ギョンヒ
¥2,420
A5判 /228ページ 「読むこと」と「書くこと」が、こんなにも静かに人を癒やす。 ―文学が“カウンセリング”になるという、新しい読書のかたち― 韓国で出版された本書『文学カウンセリング入門』は、詩や文学作品を通じて、自分自身の心の模様を読み解き、癒し、育むための方法を丁寧に示した1冊です。 韓国相談大学院大学での詩人チン・ウニョンとギム・ギョンヒの講義や論文などをもとに構成された本書は、理論編(第1部、第2部)では、文学の癒しの力とその背景にある哲学・教育思想を豊富に紹介。実践編(第3部)では、シンボルスカ、メアリー・オリヴァーらの詩を用いた実践的な12のレッスンを通して、読む・書くことで自己理解と癒しを深める手法を紹介しています。 書き写しやリライトを通じて、自らの気持ちに寄り添い、誰かと分かち合う力を育てるカリキュラム。医療・教育・福祉関係者はもちろん、自分を見つめたいすべての人へ。
-

【新刊】杉森仁香『死期か、これが』(サイン本)
¥880
SOLD OUT
A5判・並製 『夏影は残る』で第30回(2021年度)やまなし文学賞を受賞した杉森仁香さんによるリトルプレス。
-

【新刊】『利尻島から流れ流れて本屋になった』工藤志昇(サイン本)
¥1,870
SOLD OUT
四六判/168ページ 書店は、故郷だ――。ゴールの見えない多忙で多様な仕事と、ふとした拍子に思い起こされる大切な記憶――。絶景絶品の島・利尻島で生まれ育った三省堂書店札幌店係長が綴った最北の風味豊かなエッセイ集。〈解説〉北大路公子
-

【新刊】『アカデミック・ハラスメントの解決ー大学の常識を問い直す』北仲千里&横山美栄子
¥2,200
四六判/458ページ ●第1章 アカデミック・ハラスメントとは何か ▼第1節 言葉の整理─キャンパス・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント ・対策の法令はセクハラのみ ・「相手が不快ならパワハラ?」ではない ・強い叱責ばかりがパワハラ/アカハラではない ・「加害」がなくても「被害」は起きうる ▼第2節 アカデミック・ハラスメントの世界 ・アカハラ問題をとくに掘り下げる意義 ・処分事由の変化 ・処分報道の例 ▼第3節 教員の学生に対するアカデミック・ハラスメント ・特徴1 尊敬や期待が裏切られるとき ・特徴2 専門教育における教員の立場の強さ ・特徴3 キャンパスの外にまで及ぶ教員の社会的影響力 ▼第4節 研究者同士のアカデミック・ハラスメント ・特徴1 相互評価による学会/学界運営 ・特徴2 キャリアに長く影響を及ぼす ▼第5節 アカデミック・ハラスメントと向き合う ・問題があることを直視しよう ・良識ある大学人による「基準」づくりをしよう ・アカハラが起こる背景を見直そう ▼第6節 アカデミック・ハラスメントの具体例 ・学生の不幸─尊敬できない教員 ・研究室でのハラスメントやいじめ ・研究者同士のハラスメントやいじめ ◎コラム 研究者世界のピラミッド ●第2章 相談員は見た! 知られざる学問研究の世界 ▼第1節 学問分野のサブカルチャーとアカデミック・ハラスメント ・研究中心の大学と教育中心の大学 ・研究文化の違い ▼第2節 理系のアカデミック・ハラスメント ・チームで行われる研究と教育 ・「発表せよ、さもなくば滅びよ」 ・典型例1 ブラック研究室の「ピペド」 ・典型例2 長時間労働が当たり前 ・典型例3 強い叱責、追い詰め ▼第3節 オーサーシップと研究倫理問題 ・誰が著者? ・オーサーシップ問題は「微妙な問題」の象徴 ・国際基準のルールはあるけれど ・研究不正とアカハラの深い関係 ▼第4節 教授がとても「偉い」ところ ・小講座制が生んだピラミッド組織 ・「教授独裁型」という悪夢 ・小講座制は絶対悪? ▼第5節 医歯学部の医局講座制 ・医学部教授がとくに「偉い」理由 ・「医局」という不思議なシステム ・万年助教の存在はハラスメント!? ▼第6節 文系でのアカデミック・ハラスメント ・文系の研究スタイル ・ディープな関係、マインド・コントロール ◎コラム 教育中心の大学でのハラスメント ●第3章 アカデミック・ハラスメントへの対応 ▼第1節 ハラスメント相談員の役割 ・被害の意味づけをする ・そこから抜け出す方法を考える ・責任者に関係調整・環境調整の依頼をする ・解決するまで面談を継続する ▼第2節 解決までのステップ1「助言・情報提供」 ・相談者自身で解決を図る ・二次被害への怖れ ▼第3節 解決までのステップ2「通知」─行為者への注意・警告 ・通知パターン1 行為者に対する聴き取りを行った上で通知する ・通知パターン2 簡単な事実確認だけをして通知する ・だれが「通知」をするか ・通知を行う上で注意するべきこと ▼第4節 解決までのステップ3「調整」─人間関係や環境の改善 ・調整パターン1 相談者と行為者の引き離し ・調整パターン2 上司や同僚、相談員による監視(モニタリング) ・調整パターン3 行為者による謝罪 ・調整パターン4 当事者間での話し合いの援助(調停) ▼第5節 解決までのステップ4「苦情申し立て」 ・事実調査の進め方 ・調査に入る前に準備しておくこと ・行為者に通知するとき ・調査期間中の配慮 ・事情聴取の際の配慮 ・事実調査後の対応 ・結論が出るまでの期間 ・処分が決まったら─当事者への通知と処分の公表 ▼第6節 再発防止のための取り組み─経験から学ぶ ・ほかにも被害が隠れていないかどうか調べる ・実際に起きた事例をもとに啓発・教育・研修をする ◎コラム 弁護士を活用する ●第4章 ハラスメントをなくすために大学が取り組むべきこと ▼第1節 大学という組織固有の難しさ ・自治の原則が閉鎖性を生む ・ハラスメントは大学のガバナンス問題 ▼第2節 ハラスメントが起きにくい「体質」をつくる ・ハラスメントが起こりやすい組織 ・アクセスしやすい相談窓口 ・スキルのある専任の相談員をおく ・大学間の環境の格差 ▼第3節 研究不正にかかわるハラスメントにどう取り組むか ・研究不正とハラスメントの関係 ・研究不正の起こりにくい土壌をつくる ・ローカルルールを超えて ◎コラム 外部相談のメリットとデメリット ●アカデミック・ハラスメントに関する資料 ・大学院生の教育・研究環境に関するアンケート調査票の例 ・広島大学ハラスメント相談室規則 ・広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則 ・広島大学におけるハラスメントの防止等に関するガイドライン