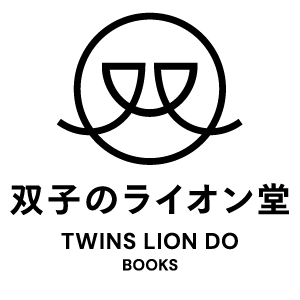-

【新刊】『AV監督が映画を観て考えた考えたフェミニズムとセックスと差別と』二村ヒトシ
¥1,320
B6変形版/113頁/ ZINE概要 これからのフェミニズムって? 「普通のセックス」とは? 差別するってどういうこと? 「いい変態」って? セックスしないのが純愛? 痴女や女装子など旧来のジェンダー観を揺るがすAVでその地位を獲得した二村ヒトシが、国内外の名作映画から愛と性を考えるエッセイです。二村ヒトシ、還暦記念にして初のZINE、どうぞご注目ください! もくじ 『男女残酷物語サソリ決戦』を観て、フェミニズムのことを考えた 『毛皮のヴィーナス』を観て、変態って何だ、そもそもセックスって何だ、って考えた 『オアシス』を観て、差別って何だ、純愛って何だ、って考えた 『パトリシア・ハイスミスに恋して』とパトリシアが原作を書いた何本かの映画を観て、まともじゃなく生きることについて考えた 『紙の月』を観て、(大きなお世話かもしれないけれど)女の人にとって“私”という意 識って何だろう、と考えた 『海街diary』を観て、女を幸せにする「男らしくなさ」について考えた 『卍』を観たら、「すべての人間は変態である」と言われた気がして、勇気づけられた 『大いなる自由』を観て、セクシャルマイノリティ にとってだけじゃなくノンケ男女にとっても「セックスにおける自由 」って何だろう、と考えた 『ニンフォマニアック』を観て、人のセックスを解釈してはいけませんと思った 『オキナワより愛を込めて』を観て、50年前のギャルの生きざまについて考えた あとがきのようなおしゃべり 二村ヒトシ×碇雪恵(本書編集担当)※『ナミビアの砂漠』『花束みたいな恋をした』の感想付き。 著者:二村ヒトシ 装丁:宮﨑希沙(KISSA LLC) 装画:加藤崇亮 Special Thanks:松村果奈(映画 .com)、広瀬美玲 編集・発行人:碇雪恵 発行所:温度 ページ数:103ページ 判型:B6 二村ヒトシさんプロフィール AV監督・文筆家。1964年六本木生まれ。慶應義塾大学文学部中退。97年にAV監督としてデビュー。著書に『すべてはモテるためである』『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』『あなたの恋がでてくる映画』『オトコのカラダはキモチいい』(金田淳子・岡田育との共著) 、『欲望会議―性とポリコレの哲学』(千葉雅也・柴田英里との共著)、『深夜、生命線をそっと足す』(燃え殻との共著)などがある。
-

【新刊】『ひとり出版入門』宮後優子
¥2,420
SOLD OUT
四六判/ どうやって本をつくる? どうやって運営していく? ひとり出版ノウハウのすべて。 本の制作と販売、出版社登録、書誌情報登録、書店流通、在庫管理、翻訳出版、電子書籍、さまざまなひとり出版の運営についてまとめられています。 著者 宮後優子 装幀 守屋史世(ea) 編集 小林えみ、宮後優子 校正 牟田都子 印刷 藤原印刷 <目次> はじめに 1章 本のつくり方 本をつくるプロセス 1 企画を立てる 2 著者と打ち合わせする 3 企画書をつくる 4 原価計算をする 5 企画内容を確定する 6 台割とスケジュールをつくる 7 著者に原稿を依頼する 8 原稿整理をする 9 写真撮影や図版の手配をする 10 デザイナーに中ページのデザインを依頼する コラム:デザイナーの探し方 11 ISBNを割り振る 12 デザイナーに表紙のデザインを依頼する 13 束見本を発注する 14 用紙を確定して印刷代を計算する コラム:コストをおさえ美しい本をつくるコツ コラム:書店流通で避けたほうがいい造本 15 著者編集者が校正する 16 校正者が校正する コラム:校正者、翻訳者の探し方 17 文字や画像をDTP で修正する 18 定価を決めて注文書を作成する 19 受注して刷り部数を決める コラム:書店への訪問営業 20 書誌データを登録する 21 印刷所へ入稿する コラム:紙見本の入手方法 コラム:印刷所の選び方(おすすめ印刷所リスト) 22 色校をチェックする 23 色校を印刷所へ戻す(校了) 24 電子書籍を作成する(必要があれば) 25 刷り出しや見本をチェックする 26 制作関係者やプレスに見本を送付する 27 販促をする(イベント企画やプレスリリースの作成) 28 請求書をもらい支払い処理をする 29 書店で確認する 30 発売後の売れ行きを見ながら追加受注する コラム:売上の入金時期 コラム:直販サイトのつくり方 コラム:本の発送料をおさえるコツ コラム:倉庫のこと 番外編 翻訳出版 1 翻訳したい本の原書、PDFを入手する 2 原書出版社に版権の問い合わせをし、オファーする 3 版権取得可能なら、契約と支払いをする 4 翻訳書を制作し、原書出版社のチェックを受ける 5 翻訳書を出版する 2章 本の売り方 書店流通のために必要なこと 書店への配本の流れ 出版物の流通方法を決める 1 版元直販(直販サイト、イベントでの販売) 2 別の出版社のコードを借りる(コード貸し) 3 Amazonと直取引で売る(e 託) 4 書店と直取引で売る 5 トランスビューの取引代行で流通 6 中小取次経由で流通 7 大手取次経由で流通 電子書籍の流通 コラム:Book&Design の場合 コラム:図書館からの注文 3章 ひとり出版社の運営 ビーナイス 烏有書林 西日本出版社 よはく舎 ひだまり舎 コトニ社 みずき書林 Book&Design URLリスト、索引 参考文献 おわりに 宮後 優子 (ミヤゴ ユウコ) (著/文) 編集者。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業後、出版社勤務。1997年よりデザイン書の編集に従事。デザイン専門誌『デザインの現場』『Typography』の編集長を経て、2018年に個人出版社・ギャラリーBook&Design を設立。日本デザイン学会会員。共著『要点で学ぶ、ロゴの法則150』(BNN)。 https://book-design.jp/
-

【新刊】『北欧フェミニズム入門』枇谷玲子
¥1,200
A5/84ページ 翻訳者・枇谷玲子編著の北欧で刊行されたフェミニズムに関連した本をを介するブックガイド。 詳しくはこちら。https://note.com/reikohidani/
-

【新刊】『第二開国』藤井太洋
¥2,035
四六判/400ページ 現代の黒船がもたらすのは再生か、終焉か? 父親の介護のため地元・奄美大島にUターンした昇雄太。 長年過疎と人口減少に悩まされていた町は、巨大クルーズ船寄港地を中心としたIR誘致計画により、活気を取り戻しつつあった。 この事業は、圧倒的巨大資本の力で雇用創出とインフラ整備を実現し、町の、そして日本の救世主となる――多くの島民がそう思っていた。 ところが計画が着々と進むある時、昇はクルーズ船〈エデン号〉の前代未聞の事業内容を突きつけられる。 門戸開放か排斥か。様々な思惑が渦巻く計画を前に、島民たちの決断は?(版元サイトより)
-

【新刊】『太陽系SF冒険大全 スペオペ!』全巻セット(1巻のみサイン本)
¥6,556
少年画報版の「太陽系SF冒険大全 スペオペ! 1〜8」全巻セット 1巻にのみサインが入っています。 時はいつか見た未来。 所は懐かしき宇宙。 この宇宙には星間物質たるエーテルが満ち満ちていた… 「サイレントメビウス」など数々のヒット作を持つサイバーコミックの旗手・麻宮騎亜による9年ぶりの完全新作SF巨編!
-

【新刊】『R´eunion―麻宮騎亜画集』麻宮騎亜(サイン本)
¥4,400
SOLD OUT
A4判/288頁 画業35周年記念!! 漫画家・麻宮騎亜が35年間で描いた渾身の画稿281点を収録した完全保存版! 『サイレントメビウス』『彼女のカレラ』『快傑蒸気探偵団』『遊撃宇宙戦艦ナデシコ』『Compiler(コンパイラ)』『太陽系SF冒険大全 スペオペ!』などで知られる、漫画家、イラストレーター、アニメーターである麻宮騎亜の画業35年を記念したファン待望の画集。代表作である作品の装画や扉絵を中心に281点の多彩な絵を全288ページに詰め込んだ一冊。 内容説明 漫画家・麻宮騎亜が35年間で描いた渾身の画稿281点を収録した完全保存版!!キャラクターやメカ、戦艦、背景まで!麻宮騎亜が描く多彩な絵の魅力を全288ページに詰め込んだ一冊!! 目次 サイレントメビウス メビウスクライン 快傑蒸気探偵団 神星記ヴァグランツ Compiler アセンブラ0X 遊撃宇宙戦艦ナデシコ 聖獣伝承ダークエンジェル コレクター・ユイ 彼女のカレラ―My Favorite Carrera〔ほか〕
-

【新刊】『増補新版 韓国文学の中心にあるもの』斎藤真理子
¥1,980
SOLD OUT
四六判/368ページ なぜハン・ガンは、アジア人女性として初めて、ノーベル文学賞を受賞したのか? 大きな話題を呼んだ原著に、この2年、激動する韓国文学の重要作の解説を加筆、40頁増の新版登場! 韓国文学は、なぜこんなにも面白く、パワフルで魅力的なのか。その謎を解くキーは「戦争」にある。 ・著者メッセージ 本書の初版は二〇二二年七月に刊行された。その後二年と少しの間に、新たに多くの韓国文学が翻訳出版された。増補新版ではその中から注目すべきものを追加すると同時に、初版時に紙幅の関係などで見送った作品にも触れることにした。特に「第7章 朝鮮戦争は韓国文学の背骨である」の章に多くを追補している。 その作業を進めていた二〇二四年十月に、ハン・ガンがアジア人女性として初のノーベル文学賞を受賞した。本書を読めば、ハン・ガンが決して孤立した天才ではなく、韓国文学の豊かな鉱床から生まれた結晶の一つであることがわかっていただけると思う。 海外文学には、それが書かれた地域の人々の思いの蓄積が表れている。隣国でもあり、かつて日本が植民地にした土地でもある韓国の文学は、日本に生きる私たちを最も近くから励まし、また省みさせてくれる存在だ。それを受け止めるための読書案内として、本書を使っていただけたらと思う。(「まえがき」より) ・目次 まえがき 第1章 キム・ジヨンが私たちにくれたもの 『82年生まれ、キム・ジヨン』の降臨 キム・ジヨンは何を描いていたか みんなの思いが引き出されていく 「顔のない」主人公 キム・ジヨン以前のフェミニズム文学のベストセラー 大韓民国を支える男女の契約、徴兵制 冷戦構造の置き土産 キム・ジヨンのもたらしたもの 第2章 セウォル号以後文学とキャンドル革命 社会の矛盾が一隻の船に集中した 止まった時間を描く―キム・エラン「立冬」 キャンドル革命に立ち会う―ファン・ジョンウン『ディディの傘』 当事者の前で、寡黙で 傾いた船を降りて 無念の死に捧げる鎮魂の執念 第3章 IMF危機という未曾有の体験 IMF危機とは何か 危機の予兆―チョン・イヒョン「三豊百貨店」 IMF危機が家族を変えた―キム・エラン「走れ、オヤジ殿」 「何でもない人」たちの風景―ファン・ジョンウン「誰が」 生き延びるための野球術 セウォル号はIMF危機の答え合わせ 第4章 光州事件は生きている 五・一八を振り返る 光州事件はなぜ生きているか 詩に描かれた光州事件 体験者による小説 決定版の小説、ハン・ガン『少年が来る』 遺体安置所の少年 死者の声と悪夢体験 死を殺してきた韓国現代史 『少年が来る』は世界に開かれている アディーチェの作品との類似性 さらに先を考えつづけるパク・ソルメ 歴史の中で立ち返る場所 第5章 維新の時代と『こびとが打ち上げた小さなボール』 「維新の時代」が書かせたベストセラー タルトンネの人々 都市開発と撤去民の歴史 『こびと』は一つのゲリラ部隊 物語を伝達するための驚くべき構成 若者たちの心の声が響いてくる 生き延びた『こびと』 石牟礼道子とチョ・セヒ 興南から水俣へ、また仁川へ 『こびと』が今日の日本に伝えること 再開発は韓国文学の重要なテーマ 第6章 「分断文学」の代表『広場』 「分断文学」というジャンル 朝鮮戦争と「釈放捕虜」 南にも北にも居場所がない 批評性と抒情性溢れる『広場』 四・一九革命がそれを可能にした 韓国文学に表れた「選択」というテーマ 堀田善衛の『広場の孤独』 絶対支持か、決死反対か 終わらない広場 そして、日本で終わっていないものとは 第7章 朝鮮戦争は韓国文学の背骨である 文学の背骨に溶け込んだ戦争 苛烈な地上戦と「避難・占領・虐殺」 イデオロギー戦争の傷跡 朝鮮戦争を六・二五と呼ぶ理由 金聖七が見た占領下のソウル 廉想渉『驟雨』の衝撃 したたかに生き延びる人々 自粛なき戦争小説 望郷の念を描く自由がない―失郷民作家たち 韓国社会を見すえる失郷民のまなざし 子供の目がとらえた戦争―尹興吉『長雨』 戦争の中で大人になる―朴婉緒の自伝的小説 私にはこれを書く責任がある 避難生活はどう描かれたか―金源一 避難生活はどう描かれたか―呉貞姫、黄順元 それぞれの休戦後―兵士たちの体験 それぞれの休戦後―虚無と生きる 南北双方から見た「興南撤収」 文学史上の三十八度線 越北・拉北作家の悲劇 日本がもし分割されていたら パク・ミンギュも失郷民の子孫 ファン・ジョンウンの描くおばあさんたち なぜ朝鮮戦争に無関心だったのか 世界最後の休戦国 第8章 「解放空間」を生きた文学者たち 一九四五年に出現した「解放空間」 李泰俊の「解放前後」 「親日行為」の重さ―蔡萬植「民族の罪人」 中野重治の「村の家」と「民族の罪人」 済州島四・三事件 終わりなきトラウマ―玄基栄「順伊おばさん」 解放空間と在日コリアン作家 趙廷來の大河小説『太白山脈』 パルチザンという人々 光州から済州島へ―ハン・ガン『別れを告げない』 死の堆積の上で生き延びてきた韓国文学 終章 ある日本の小説を読み直しながら あまりにも有名な青春小説『されど われらが日々―』 朝鮮戦争をめぐって激しく論争する高校生たち ロクタル管に映った朝鮮戦争 朝鮮戦争の記憶はどこへ 「特需」という恥 十代、二十代の目に残った朝鮮戦争 なぜ韓国の小説に惹かれるのか 傷だらけの歴史と自分を修復しながら生きる 韓国の文芸評論家が読む『されど われらが日々―』 時代の限界に全身でぶつかろうとする人々の物語 良い小説は価値ある失敗の記録 あとがき 増補新版 あとがき 本書関連年表 本書で取り上げた文学作品 主要参考文献
-

【新刊】『韓国文学の中心にあるもの』斎藤真理子
¥1,650
四六判/328ページ なぜ、韓国文学はこんなに面白いのか。なぜ『82年生まれ、キム・ジヨン』は、フェミニズムの教科書となったのか。世界の歴史が大きく変わっていく中で、新しい韓国文学がパワフルに描いているものはいったい何なのか。その根底にあるのはまだ終わっていない朝鮮戦争であり、またその戦争と日本は深くつながっている。ブームの牽引者でもある著者が、日本との関わりとともに、詳細に読み解き、その面白さ、魅力を凝縮する。 (「まえがき」より) 『最近日本で、韓国文学の翻訳・出版が飛躍的に増えている。この現象は、読者の広範でエネルギッシュな支持に支えられたものだ。読者層は多様で、一言ではくくれないが、寄せられる感想を聞くうちに、読書の喜びと同時に、またはそれ以上に、不条理で凶暴で困惑に満ちた世の中を生きていくための具体的な支えとして、大切に読んでくれる人が多いことに気づいた。(中略)韓国で書かれた小説や詩を集中的に読む人々の出現は、ここに、今の日本が求めている何かが塊としてあるようだと思わせた。それが何なのか、小説を読み、また翻訳しながら考えたことをまとめたのが本書である。』
-

【新刊】『女に聞け』宮尾節子
¥1,980
SOLD OUT
四六判/142P/サイン本 2014年初頭。突然、ネット上で一篇の詩「明日戦争がはじまる」が爆発的に拡散し、詩の検索ヒット数は1200万件を弾き出した。この詩で一世を風靡した宮尾節子は、その後も普段着のままで、「明日の詩集」を模索。このほど、クラウドファンディングの応援を得て、新刊詩集、『女に聞け』をここに出版。女、戦争、暮らし、宮尾節子の明日の詩53篇! 宮尾節子(みやお せつこ) 高知県出身。飯能市在住。2014年SNSで公開した詩『明日戦争がはじまる』の爆発的な拡散で各種メディアで話題になる。既刊詩集『くじらの日』『かぐや姫の開封』『妖精戦争』『ドストエフスキーの青空』『恋文病』『明日戦争がはじまる』『宮尾節子アンソロジー明日戦争がはじまる』。第10回ラ・メール賞を受賞。*キャンプファイヤー・クラウドファンディング(宮尾節子 明日の詩集出版プロジェクト)の成功により本詩集を上梓。
-

【新刊】『猫にご用心 知られざる猫文学の世界』
¥2,420
四六判・上製本/232ページ 英語で初めて書かれた小説といわれる、 16世紀イギリスの怪奇譚「猫にご用心」。 「猫には九つの命がある」という伝承の出典ともされている知る人ぞ知る物語が、 翻訳家・大久保ゆうさんによる完訳版としてよみがえりました。 歴史に埋もれた怪奇小説が、本邦初の書籍化です! 猫たちの会話を理解しようと、 主人公・ストリーマ氏は動物の言葉が分かるようになる秘薬を作り出すのですが……。 現実と噂話が錯綜しながら、魔術や宗教の話題が入り乱れ、 人間たちの滑稽な姿が猫の目を通して描かれる世にも不思議な怪奇小説「猫にご用心」。さらに、そこから派生した知られざる猫文学も同時収録。 すべての作品に共通するのは、グリマルキンという猫のキャラクターです。 シェイクスピアからゲゲゲの鬼太郎やファイナルファンタジーまで、 時代と場所を超えてさまざまな作品に登場する「猫の王様・グリマルキン」とは? 「猫にご用心」で初登場したといわれるグリマルキンは、なぜ現代にも生き続けるのか? 奇書と伝承の謎を追う大久保さんのスリリングな解説も巻末に収録しています。 読んでまさに愉快痛快な“猫文学”アンソロジー、ここに誕生!!
-

【新刊】『タイヤル・バライ 本当の人』 トマス・ハヤン(著)、下村作次郎(翻訳)
¥3,080
四六判・上製本/268ページ 幽霊の対話は異なる時空を行き来しながら、この物語は進んでいく。死者たちの語らいに私たちは何を見るのか――民族の核心にある文化を直視し植民統治下に命を落としていった霊魂を救済する、台湾原住民文学の秀作。 『タイヤル・バライ 本当の人』では、多くの歴史事件によって、この世界で起こった様々な変化を暗喩しています。作品は、オットフ(幽霊)の眼を通して、タイヤル族が現実世界で味わった怪異現象や荒唐無稽な出来事について語っています。植民統治下で起こったタイヤル族の世代間の認識の変化をたどり、タイヤル族がどのようにして自分たちの心の核心である文化を直視したかを振りかえることで、不公平な扱いの中で命を落としていった霊魂が安らぎを得られ、タイヤル族は真摯に自分に向き合えるのです。台湾原住民族を理解するための一冊として、日本の皆さまにこの『タイヤル・バライ 本当の人』を読んでいただきたいと思います。(トマス・ハヤン「日本の読者の皆さまへ」より)
-

【新刊】『 韓国・朝鮮の心を読む』クオン
¥4,180
A5判/516ページ 「韓国・朝鮮の心」とは何かーー。 『韓国・朝鮮の知を読む』(2014年)、『韓国・朝鮮の美を読む』(2021年)に続き、三部作構想で始まったシリーズがついに完結! 今回のテーマは〈心〉。122人に及ぶ日・韓の執筆者らが、それぞれの分野や読書体験を紐解きながら綴るブックガイド。 読む⼈の⼼、新たな本との出会いを開く渾⾝の1冊。 中沢けいさん、中島京⼦さん、平野啓⼀郎さん、斎藤真理⼦さん、吉川凪さん、菱⽥雄介さん、⼋⽥靖史さん、前⽥エマさんといった著名⼈ほか⽇本や韓国各地にある独⽴系書店店主、⽇韓の知識⼈、作家、詩⼈など、122⼈に及ぶ多彩な執筆者が、それぞれの分野や読書体験を紐解きながら綴るブックガイドです。
-

【新刊】『35歳からの反抗期入門』碇雪恵(サイン本)
¥1,210
B6版/128頁/サイン本 目次 はじめに べつに自由じゃない リクナビペアーズマイナビティンダー しあわせな村人だったときのこと やさしさもSEXも両方あっていい ーー映画『この星は、私の星じゃない』をみて STOP神格化(そして健康に目を向ける) この世のすべての人のためには泣けない 東京の価値観 善き行動の一部始終 俺の値段は俺が決める トイレその後に(男性ver.) 産まれたらもう無力ではないーー映画『ハッピーアワー』をみて 花束には根がない 遅れてきたレイジアゲインスト花束 いまさらですけど花束雑感ーー映画『花束みたいな恋をした』をみて 夢のよう、っていうか実際夢だった 愛に気がつくためのケアをーー映画『すばらしき世界』をみて 派遣とフリーランス兼業の現状と悩み 打算のない関係だけが美しいのかーー映画『愛について語るときにイケダの語ること』をみて 雑な言葉に抵抗したい STOP神格化2022(というかBreak the ファンタジー)
-

【新刊】『反省しない日々』碇雪恵(サイン本)
¥660
A5版/26頁/サイン本 嫌なことばかりに目を向けず、明るい気持ちで暮らしたい。 大切な人との関係を自分の手で壊さないようにしたい。 そう願った碇は、これまでの人生の失敗を「反省」して「もうしない」と誓うZINEを作ろうと思い立つが、一転して「反省」って本当に必要? と問い始めてしまう……。 考えが行ったり来たりする日々を書くうち、「今ここにあるこの暮らしこそが宇宙だよ」的な考えに至る日記エッセイ。 著者:碇雪恵 デザイン:飯村大樹 ページ数:26ページ 装画:Franz Kafka 判型:A5
-

【新刊】『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力』谷川嘉浩・朱喜哲・杉谷和哉
¥1,980
四六判/288ページ 「わからなさ」を抱えて生きる方法を熱論! 情報や刺激の濁流にさらされる加速社会は、即断即決をよしとする世界だ。私たちは物事を性急に理解し、早々に結論を出し、何でも迅速に解決しようとする。しかし、それでいいのだろうか。「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは不可解な物事、問題に直面したとき、簡単に解決したり安易に納得したりしない能力のこと。わからなさを受け入れ、揺れながら考え続ける力だ。注目の若手論客3人が対話でネガティヴ・ケイパビリティの魅力と実践可能性に迫る知の饗宴! * * * リスクや不確実性に満ちた社会を渡り歩くために、大半の人は余計な時間やコストをかけることを避け、身軽で即断即決のスッキリした生き方、悩みや疑いなどないスピード感ある生き方を追い求めています。そういう流れに抗して、私たちはこの本で「ネガティヴ・ケイパビリティ」の価値を訴えようとしています。本書の試みは、濁流の中に「よどみ」を作るような仕事だと言えるかもしれません。激しすぎる流れの中で、魚やその他の水生生物は暮らしを営むことができません。魚などが暮らしやすい環境には、「よどみ」があります。同じことが、人間の生態系にも言えるはずです。何事も変化し続ける社会において「よどみ」は、時代遅れで、回りくどく、無駄なものに見えますが、そういうものがなければ、私たちは自分の生活を紡ぐことに難しさを感じるものです。逆に言えば、この社会に「よどみ」が増えれば、前よりも少し過ごしやすくなります。(「はじめに」より) 第1章 「一問一答」的世界観から逃れる方法 ――陰謀論、対人論証、ファシリテーション 第2章 自分に都合のいいナラティヴを離れる方法 ――フィクション、言葉遣い、疲労の意味 第3章 「アイヒマンにならないように自分の頭で考えよう」という言葉に乗れない理由 ――コンサンプション(消費)、アテンション(注目)、インテンション(意図) 第4章 信頼のためには関係が壊れるリスクを負わねばならない ――マーケティング、トラスト、脱常識 第5章 「言葉に乗っ取られない」ために必要なこと ――SNS、プライバシー、言葉の複数性 第6章 自分のナラティヴ/言葉を持つこと ――倫理、相対化、ナッジ 第7章 公と私を再接続するコーポラティヴ・ヴェンチャー ――関心、実験、中間集団 第8章 イベントとしての日常から、エピソードとしての日常へ ――観察、対話、ナラティヴ
-

【新刊】『哲学者カフカ入門講義』仲正昌樹
¥2,200
四六上製/270ページ 没後100年。 ドゥルーズ+ガタリ、ベンヤミン、アドルノなど、哲学/現代思想の諸理論の視座から、カフカの主要作品を精読し、解釈を加えることを通して、世界を見る時の「自分」の視線の動きを変調させるやり方を学ぶ。 今までなかった哲学の視点からスリリングにその奇怪な小説の世界を読解する。 漫才でありそうな、ちょっとしたボケの効果が――読者がこの程度のことはそれほど珍しくもないなと思っているうちに――徐々に大きくなっていき、いつの間にかとんでもない不条理に発展していることに、しばらくしてから気付く。そういう、気付かないうちに読者の時間感覚、秩序感覚を狂わせてしまうような文体にこそカフカの魅力があると思う。(本文より)
-

【新刊】『海と夕余白』小林えみ、柳沼雄太
¥1,100
四六変形判/80頁 小林えみ・柳沼雄太がそれぞれの書評に短評をつけあう連弾書評集。ひとつの本について書評と短評という多角的な視点から考える新しい形式は、本の紹介だけではなく、批評する/批評文そのものも楽しめる。 目次 はじめに 小林えみ 柳沼雄太 「場」のペルソナ 町屋良平『生きる演技』 歴史はゆるくつながる星座のように 田中さとみ『ノトーリアス グリン ピース』 匿名性というレッテル 安堂ホセ『迷彩色の男』 ふたつの喪失と無意識的試み 安岡章太郎『海辺の光景』 手癖に導かれた身体性 小川洋子・佐伯一麦『川端康成の話をしようじゃないか』 独りで立つ、片手に羅針盤を 辻山良雄『しぶとい十人の本屋』 小林えみ 藪の中で語ることへの希望 小松原織香『当事者は嘘をつく』 コツコツとつくりあげる公共 猪谷千香『小さなまちの奇跡の図書館』 幸せなパン、悲しみのパン 『こんがり、パン おいしい文藝』 加害を歴史に記録する 『戦争のかけらを集めて』 本で学ぶということ、実践するということ 『ガスライティングという支配』 私の愛した悪役令嬢 おわりに 柳沼雄太
-

【新刊】『矢野利裕のLOST TAPES2』矢野利裕
¥1,650
A 5判/182ページ 矢野利裕さんの批評集第2弾。 《書評》 場所と時代を越えて届けられる音楽の感触―萩原健太『70年代シティ・ポップ・クロニクル』 社会は変態の夢を見るか―九龍ジョー『メモリースティック』 ロラン・バルト流記号分析のすぐれた実践―ナンシー関『超傑作選ナンシー関リターンズ』 いま家で聴くことのできない人たち―『別冊ele-king いま家で聴くこと』 フィメールラップ史観の試み―つやちゃん『わたしはラップをやることに決めた』 ドブネズミの声は風に消されても―陣野俊史『ザ・ブルーハーツドブネズミの伝説』 芸能と音楽をつなぐ一級の資料―近田春夫『調子悪くてあたりまえ近田春夫自伝』 2000年代以降にブラジルとアシッドフォークの影響を見る— 柴崎祐二『ミュージック・ゴーズ・オン』 社会的条件に左右されない音楽の姿―辻田真佐憲『日本の軍歌』 SPレコードに刻まれたゆたかな歴史— 毛利眞人『SPレコード入門』 これは純文学か―又吉直樹『夜を乗り越える』 歌うような思考、内省するようなダンス―加藤シゲアキ『できることならスティードで』 複雑すぎる世界でもがきながら— 加藤シゲアキ『オルタネート』 フェミニズム的な観点からの自己批判―村上春樹『一人称単数』 愛の逆説を物語ること— 上田岳弘『最愛の』 逆説的な言葉の世界―宮崎智之『平熱のまま、この世界に熱狂したい』 いっそ徹底的に資本主義とともに生きよ— 野々村文宏・中森明夫・田口賢司『卒業KYON2に向って』 安心な僕らは旅に出ようぜ―橋爪志保『地上絵』 この社会を生きざるをえない、と同時に、乗り越える言葉— 山川藍『いらっしゃいませ』、小佐野彈『メタリック』 音楽の混淆的な編成―湯浅学『大音海』 音楽における歴史性と現代性―永冨真莉・忠総太・日高良祐・編『[クリティカル・ワード]ポピュラー音楽』 日本語ラップ技術史としてのTWIGY自伝―TWIGY『十六小節』 言うこと聞かない奴から言うこと聞かせるわたしたちへ―ECD『他人の始まり因果の終わり』 ラッパーが示す「救済」という主題―山下壮起・二木信・編『ヒップホップ・アナムネーシス』 あらゆる音楽への批評的介入―柳樂光隆・監修『Jazz The New Chapter 』 《音楽評》 器用以上に夢中— コーネリアス『The First Question Award 』 MELODYKOGAと音楽と言葉 ニューウェイヴ経由のヒップホップとして— 佐野元春『VISITORS 』 繊細でポリフォニックな音楽—Prefuse73 『Rivinton Não Rio + Forsyth Gardens and Every Color of Darkness 』 メロディとリズムと言葉の分かちがたさ— 滝沢朋恵『AMBIGRAM 』 ECDの自主制作 歴史性も時代性も大衆性も天才性もあるさ— 小沢健二『LIFE』 戦前歌謡曲でありながらオルタナ— 泊『霽月小曲集』 越境/移動する伝統のかたち—Quantic presents The Western Transient 『A NEW CONSTELLATION 』 不穏とユーモア、あるいはシンガーソングライター的な温かみ—SUBMARINE 『島唄』 DJ、レコードバッグに追加すべし— 王舟「Ward /虹」 1990年代の夜空— スガシカオ『FREE SOUL a classic of スガシカオ』 ダッセーものからカッケーものへ―KOHHの革命的日常語 フリッパーズ・ギターの鋭さとゆたかさ 平成という時代を鳴らすように―マキタスポーツ「平成最後のオトネタ」@草月ホール サニーデイ・サービス「東京再訪」ライブレポート ニッポンのR&B受容史(1)— ニッポンR&B前夜 ニッポンのR&B受容史(2)— R&Bとヒップホップの交流 ニッポンのR&B受容史(3)— 本格派としての〝ディーヴァ〟 ニッポンのR&B受容史(4)— 拡散していくR&B 《映画評》 桐島とはオレである―映画『桐島、部活やめるってよ』 『LA LA LAND 』の愛のなさ— 映画『LA LA LAND 』 「上/下」の物語―映画『シン・ゴジラ』について瞬発的に考えた 観察者の痛みはどこにあるのか―映画『FAKE』 大衆と前衛— 映画『人生フルーツ』 最後のバンド、フィッシュマンズ— 映画『映画:フィッシュマンズ』 殺伐とした日本で言葉を獲得する— 映画『WALKING MAN 』 まぶたの裏に大林映画を— 大林宣彦監督を追悼する
-

【新刊】『「知らない」から始まる 10代の娘に聞く韓国文学のこと』(ま)& アサノタカオ
¥1,980
未知の世界を発見する喜びは、いつも知らないものたちの冒険心からはじまる。 サウダージ・ブックスの編集人で韓国文学ファンである父親が、K - POPが好きな10代の娘に話を聞いてみた。憧れのソウルを旅行したこと、韓国の小説を読んだこと。隣の国のカルチャーを追いかける親子の、少しミーハーで少しきまじめな証言を一冊に。インタビュー&エッセイによる韓国文学ガイド。 《作者のチョン・セランには、いまの韓国はそう簡単に幸せになることが許されない暗い時代だっていう考え方があって、暗ければ暗いほど、小さな希望に光を感じられるっていうことなんじゃないの? だから……ホ先生が通りすがりの子どもに運を分けてあげたいと思うちょっとしたエピソードにもあたたかい価値が生まれるんだと思う。》 ——(ま)「ホ先生が人生の最後に抱く幸福には、でも陰がある」本書より もくじ はじめに ——「知らない」からはじまる旅と読書 アサノタカオ Ⅰ インタビュー ま&アサノタカオ 「バンタン食堂」で会ったお姉さんは、とてもフレンドリーだった ——BTS聖地巡礼その他 1 距離みたいなものがなくなってメンバーが身近な存在に ——BTS聖地巡礼その他 2 この「むなしさ」は自分と同じ「世界線」にある ——チェ・ウニョン『ショウコの微笑』 ホ先生が人生の最後に抱く幸福には、でも陰がある ——チョン・セラン『フィフティ・ピープル』 思いを話したいと願うようになったから「ことば」が出てきた ——ファン・インスク『野良猫姫』 背負いきれないものを背負っている人たちが何かを封印して生きている ——キム・エラン『外は夏』 問題の原因は目に見えない感情や気持ち、人と人の関係にある ——チョン・セラン『保健室のアン・ウニョン先生』 非日常のあとの日常を普通に生きていく人を描くこと ——チョン・セラン『屋上で会いましょう』 Ⅱ エッセイ 心の矢印が、ぐっと朝鮮半島のほうに傾いた アサノタカオ 忘れられたものたち、忘れてはならないものたち ——ファン・ジョンウン『ディディの傘』 アサノタカオ わからない世界で自分を生きる ——チョン・セラン『声をあげます』 (ま) おわりに ——親子という境域(ボーダーランズ)で話を聞く アサノタカオ 著者紹介 (ま) 2004生まれ。高校生(執筆当時)。K - POPファン、韓国語を勉強中。 アサノタカオ 1975年生まれ。大学卒業後、2000年からブラジルに滞在し、日系移民の人類学的調査に従事。2009年よりサウダージ・ブックスの編集人をつとめながら、現在はフリーランスで編集と執筆の仕事をしている。著書に『読むことの風』(サウダージ・ブックス)、共著に『韓国文学ガイドブック』(黒あんず監修、Pヴァイン)。
-

【新刊】『すべての、白いものたちの』ハン・ガン
¥935
文庫判/192ページ チョゴリ、白菜、産着、骨……砕かれた残骸が、白く輝いていた――現代韓国最大の女性作家による最高傑作。崩壊の世紀を進む私たちの、残酷で偉大ないのちの物語。 ノーベル文学賞受賞! ハン・ガン作品、どれから読んだらいいかわからない……という方には、個人的には『すべての、白いものたちの』をお勧めしたいです。 詩のように淡く美しく、それでいて強く心をゆさぶる名作です ーー岸本佐知子 『すべての、白いものたちの』は、アジア初のブッカー国際賞を受賞した『菜食主義者』(cuonから2011年に邦訳刊行)に続き、2度目のブッカー国際賞候補となったハン・ガンさんの代表作です。 詩的に凝縮された言葉で書かれた本書は、個人の痛みのむこう側に横たわる歴史的・普遍的な痛みという、著者のテーマがストレートに表れている作品です。 単行本では、造本に特別な仕様をほどこしました。『すべての、白いものたちの』物語全編に通底する「白にもさまざまな白がある」ことをコンセプトに、書籍の本文用紙にすべて異なる5種類の紙材を使用。小口側から本をながめると、色味、彩度、手ざわり、さまざまな白が存在することが見てとれます。
-

【新刊】『カフカ入門』室井光広
¥3,080
A5判/210ページ カフカの秘められたエロスとは…。芥川賞作家によるカフカ文学へのイニシエーション。 目次 第1部 カフカ入門(千声と一声;くるみ割り式;見者カフカ;カフカの書き出し―『変身』の場合;カフカの書き結び―『審判』の場合;ちっぽけな問題作―『父の気がかり』考) 第2部 世界文学依存症―カフカ入門のための十三参り(旧訳K書と新訳K書;服用と着服;ベンヤミンの着服;極めつきの邪道;花の道行き;依存症患者K;人魚の男;友愛的かつ裏切り的;「あのギリシャの神」と「苦い薬草」;サトゥルヌス人;遺言という錬金術;聖セバスチャンの変種;十三参りの終りに)
-

【新刊】『カント『判断力批判』入門』高木駿
¥2,090
四六判/152ページ 今までになかった『判断力批判』入門! 近年の再検討事項でもあるジェンダーの視点を取り入れつつ、「難解」と評判のカント美学を理解しやすいように解説。 目次 はじめに 第一章 無関心性:快の感情の分析(その一) 第二章 主観的な普遍性:快の感情の分析(その二) 第三章 目的のない合目的性:快の感情の分析(その三) 第四章 範例的な必然性:快の感情の分析(その四) 第五章 三つの原理と正当化:快の感情の正当化 おわりに
-

【新刊】『スマホ片手に文学入門』小池陽慈
¥1,870
SOLD OUT
四六判/280ページ 本を読み慣れていない学生さんへ、または「忙しくて本が読めなくなってしまった……」という社会人にも。細かいポイントで立ち止まっては検索し、わかりやすく解説しながらじっくり読み進めていくマイペースな読書論。
-

【新刊】『鳥は飛ぶのが楽しいか』チャン・ガンミョン/訳:吉良佳奈江
¥1,980
四六判/368ページ ソウルのセヨン高校で給食費の横領事件が発覚。 動揺する学生たち、加熱するマスコミ、事態を抑え込もうとする教師たち、迫る大学入試……。 追及の先頭に立つ級友とともにビラまきをおこなった3年生のジェムンは、学校に対する怒りと、大学入試に影響が出ることを心配する母親との間で揺れていた。 不正義に直面したとき、私たちは立ち向かうことができるのだろうか? 大人の不正義をめぐって若者たちのさまざまな思いが交錯する表題作をはじめ、職場、就職活動、フランチャイズ店舗、ストライキ現場などで“希望"を求めて闘う人々が交差する10編の連作小説。 元新聞記者として現代韓国社会のリアルを鋭く見つめてきた気鋭の作家が贈る、闘いと希望の書。