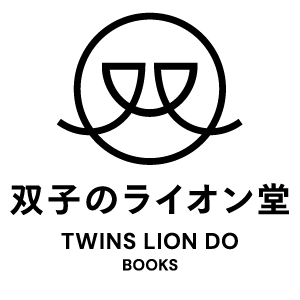-

【新刊】『踊る幽霊』オルタナ旧市街
¥1,650
四六判/168ページ “いつまででも読んでいられるしどこまででも歩いていけると思った。ずれて輝く記憶と世界、軽妙さと誠実さ、私はオルタナ旧市街を信頼する。” ――芥川賞作家・小山田浩子さん、推薦。 【内容】 巣鴨で踊る老婆、銀座の魔法のステッキ男、流通センターのゆで太郎から始まる妄想、横浜中華街での怪異、不穏な水戸出張……街をめぐる断片的な21篇。 わたしたちは瑣末なことから日々忘れて暮らしている。忘れないと暮らしていけないとも思う。わたしとあなたの断片をみっともなく増やしていこう。何度でも覚え直せばいいし、何度でも忘れていい。 インディーズシーンで注目を集める謎多き匿名作家・オルタナ旧市街が、空想と現実を行き来しながら編み出した待望のデビュー・エッセイ集。 “誰の記憶にも残らなければ、書き残されることもない。それはそれで自然なのかもしれないけれど、身の回りに起こったことの、より瑣末なほうを選び取って記録しておく行為は、未来に対するちょっとしたプレゼントのようなものだと思う。”(表題作「踊る幽霊」より) 誰にでも思いあたる(いや、もしかしたらそれはあなたのものだったのかもしれない)この記憶のスクラップ帳は、書かれるべき特異な出来事も起きなければ、特殊な事情を抱えた個人でもない「凡庸」な人々にこそ開かれている。 【目次】 踊る幽霊[巣鴨] されども廻る[品川] 反芻とダイアローグ[水戸] スクラップ・スプリング[御茶ノ水] 午前8時のまぼろし[駒込] 老犬とケーキ[東陽町] タチヒの女[立川] 麺がゆでられる永遠[流通センター] アフターサービス[横浜] 大観覧車の夜に[お台場] ウィンドウショッピングにはうってつけの[五反田] おひとりさま探偵クラブ[銀座] 白昼夢のぱらいそ[箱根] 聖餐[吉祥寺] 愛はどこへもいかない[小岩] 猫の額でサーカス[浅草] がらんどう[南千住] さよなら地下迷宮[馬喰町] (not) lost in translation[渋谷] 見えざる眼[秋葉原] テールランプの複製[八重洲]
-

【新刊】『トークの教室』藤井青銅(サイン本)
¥990
新書/240頁/版元事情で帯がないです <概要> トークに悩める全人類&ラジオファン必読! 数多の才能を見出した放送作家がそのトーク術をついに皆伝。 オードリー 若林正恭さん推薦!! 「この教室の授業のせいで、痛い目にあった時に 「儲けた〜」と思ってしまう身体になりました。」 本書は、数多の新人アイドル、芸人に寄り添い、巧みなアドバイスで彼らのトーク力に磨きをかけてきたメンター、放送作家・藤井青銅氏がそのトーク術についてまとめた一冊です。 「トークの途中がおもしろければ、オチは無くてもいい」 「誰かに聞いてもらうことで、話し方のコツを見つけた人は伸びる」 「〈心の動き〉を切り口にすれば、トークの題材には困らない」 「キャラを作ったり、背伸びしたり、パブリックイメージになんて、合わせなくていい」…etc. 若林正恭さん、山里亮太さんを描いたドラマ『だが、情熱はある』(日本テレビ系)へ本人役での出演も記憶に新しいところですが、YouTubeチャンネル「オードリー若林の東京ドームへの道」では、第一回ゲストとして若林さんと“二人っきりサシ対談”。 番組を観た視聴者からの「⻘銅さんのトーク本があったら、絶対に読みたい!」という多くのリクエストに応え、本書の執筆がスタートしました。 「あの人は、どうしていつも面白いネタを持っているのか?」 「つい聞き入ってしまうトークには、どんな秘密があるのか?」 “面白いトーク”とは何か?を突き詰め、話し手のボールを真摯に受け取り、返す、その運動を40年以上も続けるなかで導き出したトーク術を整理し、アップデートさせながら執筆された本書で、自分に合ったトークの正解が、きっと見つかるはずです。 ●目次 はじめに 第1章 「面白いトーク」という呪縛 第2章 トークの構造 第3章 「つまらない」にはワケがある 第4章 トークの「切り口」 特別企画 紙上トークレッスン 第5章トークの「語り口」 第6章 「ニン」に合うトークとは? 第7章 トークの居場所 おわりに
-

【新刊】『お口に合いませんでした』オルタナ旧市街(サイン本)
¥1,980
四六変型判/200ページ フードデリバリーの冷めたシチュー、北欧家具店のミートボール、激安居酒屋の肉寿司…… タワマンを遥か頭上に見上げ、気鋭の文筆家が都市生活の不満を嘆く憂鬱グルメ小説。 食事はいつもおいしくて満たされて幸せ、なんてやっぱり嘘だった。 ——高瀬隼子(『おいしいごはんが食べられますように』)推薦! 体調を崩した私は初めてデリバリーを注文するが、届いたシチューからは独特の冷えて固まった油のような匂いがして……(ゴースト・レストラン)。10年ぶりの同窓会、クラスのLINEグループに「完全個室創作和食バル★肉寿司食べ放題! 3時間飲み放題付き2980円」の食べログURLが送られてくる(Girl meats Boy)。おいしくない食事の記憶から都市生活のままならなさと孤独を描く、憂鬱なグルメ小説13篇を収録。 目次 ゴースト・レストラン ユートピアの肉 町でいちばんのうどん屋 愚者のためのクレープ メランコリック中華麺 終末にはうってつけの食事 ラー油が目にしみる フライド(ポテト)と偏見 Girl meats Boy たったひとつの冷めたからあげ 「いつもの味」 完璧な調理法
-

【新刊】『AV監督が映画を観て考えた考えたフェミニズムとセックスと差別と』二村ヒトシ
¥1,320
B6変形版/113頁/ ZINE概要 これからのフェミニズムって? 「普通のセックス」とは? 差別するってどういうこと? 「いい変態」って? セックスしないのが純愛? 痴女や女装子など旧来のジェンダー観を揺るがすAVでその地位を獲得した二村ヒトシが、国内外の名作映画から愛と性を考えるエッセイです。二村ヒトシ、還暦記念にして初のZINE、どうぞご注目ください! もくじ 『男女残酷物語サソリ決戦』を観て、フェミニズムのことを考えた 『毛皮のヴィーナス』を観て、変態って何だ、そもそもセックスって何だ、って考えた 『オアシス』を観て、差別って何だ、純愛って何だ、って考えた 『パトリシア・ハイスミスに恋して』とパトリシアが原作を書いた何本かの映画を観て、まともじゃなく生きることについて考えた 『紙の月』を観て、(大きなお世話かもしれないけれど)女の人にとって“私”という意 識って何だろう、と考えた 『海街diary』を観て、女を幸せにする「男らしくなさ」について考えた 『卍』を観たら、「すべての人間は変態である」と言われた気がして、勇気づけられた 『大いなる自由』を観て、セクシャルマイノリティ にとってだけじゃなくノンケ男女にとっても「セックスにおける自由 」って何だろう、と考えた 『ニンフォマニアック』を観て、人のセックスを解釈してはいけませんと思った 『オキナワより愛を込めて』を観て、50年前のギャルの生きざまについて考えた あとがきのようなおしゃべり 二村ヒトシ×碇雪恵(本書編集担当)※『ナミビアの砂漠』『花束みたいな恋をした』の感想付き。 著者:二村ヒトシ 装丁:宮﨑希沙(KISSA LLC) 装画:加藤崇亮 Special Thanks:松村果奈(映画 .com)、広瀬美玲 編集・発行人:碇雪恵 発行所:温度 ページ数:103ページ 判型:B6 二村ヒトシさんプロフィール AV監督・文筆家。1964年六本木生まれ。慶應義塾大学文学部中退。97年にAV監督としてデビュー。著書に『すべてはモテるためである』『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』『あなたの恋がでてくる映画』『オトコのカラダはキモチいい』(金田淳子・岡田育との共著) 、『欲望会議―性とポリコレの哲学』(千葉雅也・柴田英里との共著)、『深夜、生命線をそっと足す』(燃え殻との共著)などがある。
-

【新刊】『魂の声をあげる現代史としてのラップ・フランセ』陣野俊史(サイン本)
¥2,420
サイズ:四六判 ページ:365 ※サイン本です。 世界中で関心が高まっている、「声をあげる」ことの重要さ。 ラップをとおして世界を知ろう。 郊外の貧困、移民、宗教、暴動、テロ、#MeToo… 世界を取り巻く社会問題に対して放たれるラップのリリック(歌詞)は、国境を越えてわたしたちを鼓舞し、今につながる世界の歴史を知ることの大切さを気づかせてくれます。 移民社会フランスに生きるルーツもスタイルも多様なラッパーたち。 彼らのあげる声をとおして、広い世界に目を向けてみてはいかがでしょうか? わたしたちの「いま」と「ここ」がラップにはある――。
-
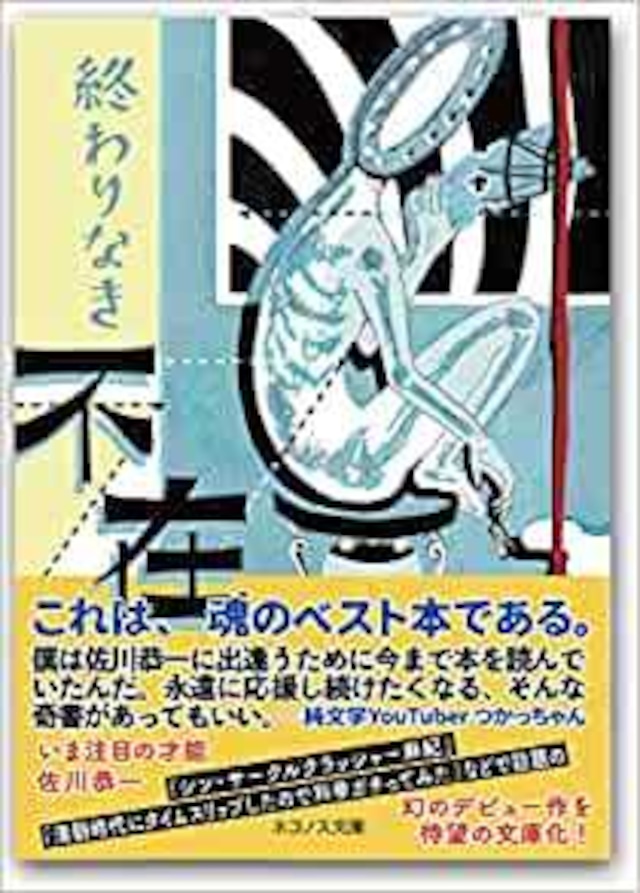
<新刊>『終わりなき不在』佐川恭一(ネコノス)*サイン本
¥1,210
SOLD OUT
<新刊>『終わりなき不在』佐川恭一(ネコノス)*サイン本 サイズ:文庫 ページ:208頁 もはや入手不可能とされていた幻の作品を待望の文庫化。 就職した銀行を一年で辞め、仕事も恋人も失った自堕落な青年は小説家を目指す。その果てに何が待っているかも知らずに……。「文章を書くためだけに脳をカスタマイズされ他の能力を全てスポイルされた俺という怪物の書く小説が、なぜ他者の作品に劣るのか?」 迷走する自意識、崩壊するモラトリアム。これは悲劇か? それとも喜劇なのか? 泣いた方がいいのか? 笑っていいのか? 渦巻くような自意識の階層構造に、やがて読者の意識も翻弄されていく……。 いま文芸界で熱い注目を集めている才能の一人、大人気カルト作家・佐川恭一の原点がここにある。第3回日本文学館出版大賞ノベル部門大賞受賞作。
-

【新刊】宮田愛萌『写真短歌集 わたしのをとめ』 (サイン本&オリジナルポストカード付)
¥4,708
A5判・上製・角背・144頁 本にはサインとメッセージを書いていただきました! また、オリジナルポストカード(FARMイベント仕様)も付きます。 ---- 現代を⽣きる、わたし。想像の世界のをとめ。リアルと仮想をつなぐ短歌。 撮り下ろし写真96点と新作50⾸、収録。短歌、縁の地でもある宮崎⽇向市の短歌甲⼦園審査員など短歌の良さを少しでも発信できるよう活動中。和装・洋装を着た本⼈写真と短歌のコラボ。制作全て本⼈監修し様々な分野のプロフェッショナル集結で出来上がった渾⾝の1冊です。 【収録作品より】 絶対に許されません許しません わたし以外が世界だなんて しらたまのようなふとももさらすのは望月だけであれと願わん ディオールもシャネルもなにも知らぬきみせめて色だけおんなじ口紅 ばらばらにしてしまったな。手のひらで。梅花空木は離弁花だから その人は綺麗なもので満ちていてふりむかないでわたしのをとめ 現代を生きる、わたし。想像の世界の、をとめ。 【著者プロフィール】 宮田愛萌(みやた・まなも) 小説家・タレント。1998年4月28日生まれ、東京都出身。2023年アイドル卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。現在は文筆家として小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。 本に関連するTV/トークイベント/対談などにも出演。 *バターの女王アンバサダー *TBSポッドキャスト「ぶくぶくラジオ」 *小説現代エッセイ連載「ねてもさめても本のなか」講談社 *短歌研究エッセイ連載「猫には猫の・犬には犬の」短歌研究社 *TV LIFEラジオ番組「文化部特派員『宮田愛萌』」パーソナリティ *著書『あやふやで不確かな』幻冬舎 *著書『春、出逢い』講談社 撮影/小石謙太
-

【新刊】『ディスクロニアの鳩時計』海猫沢めろん(サイン本)
¥3,960
四六判・上製本/536p/ 連載10年、原稿用紙1000枚を超える大長編、ついに完成。 SFにして変格ミステリ、思弁小説にして青春文学。 思想誌『ゲンロン』にて10年にわたり連載された話題作『ディスクロニアの鳩時計』。 あらゆるジャンルを横断しながら、現実と虚構を交錯させる、“メタリアルフィクションの極北”とも言うべき大長編。 圧倒的密度で疾走する、記憶と物語の迷宮へ。 ▼あらすじ 拡張現実〈カクリヨ〉と人工知能に覆いつくされた近未来の日本。 孤独な17歳の少年〈白鳥鳥彦〉は、夏祭りの夜、不思議な少女〈時彫幽々夏〉と出会う。 彼女は時間に関するあらゆる事物を収集する謎の大富豪〈時彫家〉の令嬢だった。 その瞳を覗き込んだ瞬間、鳥彦は激しい殺人衝動に貫かれるーー 国家権力、量子人工知能を巻き込み、少年の狂気に満ちた計画が始動する。 ▼帯コメント 21世紀のロートレアモンに称讃を、そして唾棄せよ。これは凶悪な進化を遂げた「マルドロールの歌」(暗黒詩篇)だ。 ーー竹本健治(作家・『匣の中の失楽』) 「時間とは何か」を巡る壮大な探求──崩壊と再構築を繰り返す巨大な謎を描いた、渾身のクロニクル。ノベルゲーム、加速器、機械知性、脳科学、最先端AIまで、あらゆるギミックを詰め込んだ現代の千夜一夜物語。 ーー三宅陽一郎(ゲームAI研究者)
-

【新刊】『ファンキー中国: 出会いから紡がれること』井口淳子・山本佳奈子
¥2,530
14.8x19.5 cm、並製/320ページ 音楽、クラフトビール、TikTok、豆腐屋、祭祀、ロックフェスに伝統劇―― 多彩な書き手が一堂に会し、それぞれの視点と切り口で描く、ファンキーな中国体験記! 音楽家や収集家、映画祭主催者、祭祀採音者、研究者など13人が集まり、自身の体験した「中国」をそれぞれが思う存分に綴ったエッセイ集を刊行。 80年代の「魔都」上海と食の記憶、中国の村に出現したド派手なステージでのライブ、TikTok で見つけた瀋陽公園で溌溂と踊る人々。70年代の文革期から現代中国という時代をまたにかけ、北京の胡同(フートン)から雲南省、 果てはフランスや台湾、モンゴルにまでエッセイの舞台が広がっていく。 報道では伝えられることのない、書き手たちが映し出す中国の姿。「伝統」に新しいものを豪快に取り入れる姿があり、厳しい規制があるなか、生活に染み入る絶妙な「ゆるさ」や「自由」がある。ときにはカルチャーギャップと呼ばれるような衝撃にも戸惑いながら、書き手ひとりひとりが経験した小さな「出会い」を紡ぎます。 中国といえば国家や政治や歴史という大きなイメージをつい頭に浮かべてしまいがちですが、人と人が出会う小さな瞬間にこそ、かけがえのないものがある。そんな、ひとつの希望を感じるような一冊を刊行します。 本文とカバーのイラスト及び装幀は、『送別の餃子』でお馴染みの佐々木優さん。「14人目の書き手」として、自身の記憶に残る中国の街並みをカバーに描いていただきました。
-

【新刊】『活字を拾う―グラフィックデザインと活版印刷をつなぐ』村田良平(サイン本)
¥2,530
B5判変形(178mm ×213mm) 並製/サイン本 カチャン、カチャン 活版機「チャンドラー」の乾いた音が、今日も工房に響いている。 ―――― 2012年、京都のある活版印刷所がその歴史に幕を降ろした。 大量生産と均一な品質を担保するオフセット印刷が主流の時代に、活版印刷所の存続は難しかった。しかし、その活版印刷所の道具や活版機が、ある人物によって引き継がれ、今もなお、活版機の心地よい音を響かせながらせっせと活字を刻んでいる。 グラフィックデザイナーであり、活版印刷工でもある「りてん堂」店主・村田良平さんが、活版印刷とそれに関わる道具や職人の姿への思いを綴り、写真家・マツダナオキさんの写真を添えて贈るフォト・エッセイを刊行します。 合理性が謳われる時代になぜ彼は活版印刷を始めたのか。グラフィックデザイナーとして出立した村田さんと活版印刷との出会い、「りてん堂」開業の決意、活版技術者としての独学の日々。 現代の印刷と対極にあるような活版を通して、デジタル化と合理化のなかで失ってしまったものがあるのではないかと村田さんは感じます。例えば、職人たちの手を渡ってきた道具そのものの存在だったり、活字の重みだったり――そういう本になりました。 初刷は特典付き 【著者紹介】 村田良平(むらた・りょうへい) 京都生まれ。創造社デザイン専門学校卒業。グラフィックデザイナー、エディトリアルデザイナー。二〇一二年、グラフィックデザインと活版印刷の工房「りてん堂」を京都の一乗寺にオープン。デザイナーとして、活版印刷技術者として活動を続けている。
-

【新刊】『お笑いを〈文学〉する〜「笑える/笑えない」を超える』小田垣有輝(サイン本)
¥1,210
新書判/120頁 双子のライオン堂書店で、開催した連続講義「笑いを〈文学〉する」が書籍になります。 2024年に小田垣有輝さんをお招きして開講した授業を、書籍化に伴い授業だけでは伝えきれなかった熱い思いと独自の論をブラッシュアップして展開します。 【目次】 はじめに 1、東京03と中島敦『山月記』~トリオネタの魅力/『山月記』って本当に二人? 2、ピン芸人の構造論―「語り」か「噺」か 3、「お笑い」と「コード」ー既存のコードへの「抵抗」と「逸脱」 4、トム・ブラウンをなぜ笑う?―文学史と小川洋子『貴婦人Aの蘇生』をヒントに 5、ランジャタイとラーメンズ―谷崎・芥川の文学論争と比較して 6、ランジャタイとシェイクスピア―文学と「おばけ」の関係 ―ランジャタイとは何か 付録 登場人物紹介&参考文献 おわりに 【基本情報】 書名:『お笑いを〈文学〉する 「笑える/笑えない」を超える』 著者:小田垣有輝 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:1100+税 判型:新書判、並製 ページ:120頁 発行元:双子のライオン堂出版部 【著者】 小田垣有輝(おだがき・ゆうき) 私立中高一貫校、国語科教員。今年で教員11年目。研究分野の専門は谷崎潤一郎、語り論。教員として働くかたわら、個人文芸誌『地の文のような生活と』を一人で執筆・編集・刊行(現在vol.1~vol.6まで刊行中)。本づくりを通じて、自らが帯びる特権性と向き合う。 <「はじめに」> なぜ人は、お笑いを観て笑うのでしょうか。 「お笑い」という名称からもわかるように、お笑いはお笑いを鑑賞する者に「笑う」という反応を要請します。小説であれば、もちろん笑える小説もあるし、泣ける小説もあるし、怒りを共有する小説もあるし、漠然としたもやもやを読者に植え付ける小説もあるし、小説を読む者の反応は様々である、ということが「当たり前」となっています。しかし、一般的にお笑いは「笑う」という反応に限定されます。ネタ番組では、観覧の人々はみな笑っているし、その中に泣いたり怒ったりする人はいません。 でも、お笑いを観て「笑う」以外の反応をしたっていいはずです。そうでなければ、「笑えるお笑い=良いお笑い」という評価軸しか存在しないことになります。お笑いの中には「笑えないけど良いお笑い」だって存在します。 本書では、物語論や社会学を媒介にしながら「お笑い」と「文学」の関係を考えていきます。そうすることによって「笑えるか否か」という評価軸とは違う軸が見えてきます。私たちが普段観ているお笑いを違った視点から批評することによって、お笑いが備えている豊かな世界が立ち現れるはずです。(小田垣有輝)
-

【新刊】『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉植本一子&太田靖久(Wサイン本)
¥990
新書判/84頁/Wサイン本 双子のライオン堂書店で、連続で開催している小説家の太田靖久さんと様々なクリエーターが「つくる」をテーマに語り合う配信イベントが、ZINEのシリーズになります。 第1弾は、2023年と2025年に植本一子さんと行った2つの対談を1冊の冊子にまとめました。 ZINEやリトルプレスについて考えて続けているお二人のそれぞれの視点が交差します。 自分でも”作ってみたい”人は必携の1冊です。 また、今後のシリーズとして刊行していきますので、ラインナップにもご注目ください! <基本情報> 書名:『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉 著者:太田靖久・植本一子 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:900+税 判型:新書判、並製 ページ:84頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)、『犬の看板探訪記 関東編』(小鳥書房)など。文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店や図書館での企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号で出店も行っている。 植本一子(うえもと・いちこ) 写真家。2003年にキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞。2013年、下北沢に自然光を使った写真館「天然スタジオ」を立ち上げる。著書に『かなわない』『愛は時間がかかる』、写真集に『うれしい生活』、小説家・滝口悠生との共著『さびしさについて』などがある。主な展覧会に『アカルイカテイ』(広島市現代美術館)、『つくりかけラボ07 あの日のことおぼえてる?』(千葉市美術館)。 <「はじめに」(太田靖久)> 植本一子さんとの2回のトークイベント(2023年9月と2025年3月開催)を再構成して追記等も行い、本書に収録しました。2回目は1回目の1年半後に行われたため、その間の変化も楽しんでいただけるはずです。 今企画は双子のライオン堂の竹田さんからの提案がきっかけでした。 「太田さんは質問がうまいのでゲストを迎える形式のトークイベントを定期開催するのはいかがですか?」 すぐに快諾しました。自分の話をするより、誰かの話を聞いていたいと思うのは、知らないことを知りたいというシンプルな好奇心が根っこにあるからです。 1回目のゲストは植本さんが良いなとひらめきました。植本さんの文章には親しみやすさがあるのに、決して安全なものではなく、深くえぐってくる強度もあります。そんな植本さんのやさしさと鋭さのバランスや、創作と事務作業の使い分けについてなど、様々に興味がありました。また、ZINEに関するトークイベントをほとんど行っていないとうかがい、貴重な内容になるという判断もありました。 植本さんには登壇だけでなく、〈つくるをかんがえる〉というタイトルも付けていただきました。それが企画の方向性を固めるうえで助けになったことも忘れずに記しておきます。(太田靖久)
-

【新刊】『随風02』(サイン本/誰のサインが届くかはランダム)
¥1,980
A5判/162ページ/サイン本(誰のサインが届くかはランダムです) 随筆復興を推進する文芸誌『随風』 創刊号は刊行後たちまち重版となり話題をさらった。 今号は執筆陣にpha、古賀及子、花田菜々子、絶対に終電を逃さない女、佐々木敦らを迎える。 【執筆者一覧】 宮崎智之、アサノタカオ、磯上竜也、今井楓、オルタナ旧市街、清繭子、古賀及子、早乙女ぐりこ、杉森仁香、絶対に終電を逃さない女、西川タイジ、花田菜々子、pha、吉田棒一、わかしょ文庫 批評 柿内正午、佐々木敦、和氣正幸 インタビュー 村井光男(ナナロク社) 編集後記 吉川浩満
-

【新刊】『こころはひとりぼっち』植本一子(サイン本)
¥1,540
SOLD OUT
B6変形/134ページ 最後に会って3カ月 別れの手紙から1カ月が経った パートナーとの関係を解消してからの数カ月の日記 友人・碇雪恵による寄稿も 目次 8月1日〜8月10日 毎日さびしい。毎日つらい。 9月11日〜9月20日 今はひとりでいることに挑戦しているのだ。 10月20日 誰かひとりでも、いてくれたらいいのだけど。 寄稿 ひとりぼっちじゃない 碇雪恵
-

【新刊】『ねこによろしく 赤』池谷和浩
¥1,320
B6判/ 124ページ/サイン本 著者の近況エッセイと『フルトラッキング・プリンセサイザ』『四季と機器』に架橋する小説がクロスして溶け込んでいく新しい散文。 猫は白い方のがゆっくりご飯を食べ、赤い方のはさっさと食べる。猫と暮らす日々の中で著者は新しい小説の創作に取り組んでいます。 小説で、うつヰは、ある家にたくさん保管された服を個人売買のサイトに登録して売っていくバイトをしています。 現実と小説の世界は、果たして本当に別のものなのでしょうか。 本作品の前編は『ねこによろしく 白 ウェアラブル・プロシージャ』です。 装画 にしさかきみこ
-

【新刊】『ねこによろしく 白』池谷和浩
¥1,320
B6判/112ページ/サイン本 著者の近況エッセイと『フルトラッキング・プリンセサイザ』『四季と機器』に架橋する小説がクロスして溶け込んでいく新しい散文。 猫は白い方のがゆっくりご飯を食べ、赤い方のはさっさと食べる。猫と暮らす日々の中で著者は新しい小説の創作に取り組んでいます。 小説で、うつヰは、ある家にたくさん保管された服を個人売買のサイトに登録して売っていくバイトをしています。 現実と小説の世界は、果たして本当に別のものなのでしょうか。 続刊は『ねこによろしく 赤 ウェアラブル・プロシージャ』です。 装画 にしさかきみこ
-

【新刊】『ききなし 浄化槽 二〇二三年愛と海』旗原理沙子(サイン本)
¥1,260
旗原理沙子さんの作品集。 大学を卒業してすぐバルザック研究者の七山と結婚し、アルバイト先の映画館で二人の男といびつな関係を結んで理解不能な時期を過ごした赤石の物語…第128回文學界新人賞最終候補作「ききなし」。政治思想が異なりわかりあえない家族を描いた「浄化槽」、あとがきエッセイ風の短歌ミュージカル「二〇二三年愛と海」、以上の三本を収録しています。
-

【新刊】『宇宙を編む: はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる』井上榛香(サイン本)
¥1,870
四六/202ページ/サイン本 大地を駆ける宇宙ライターの日常 野良宇宙ライターの道は険しい。 宇宙開発を取材して原稿を書くには、工学やサイエンスのほか、政治、国際関係、安全保障、歴史、法律、ビジネスなどの知識が求められ、まるで総合格闘技みたいだ。どれだけ勉強しても知らない専門用語や略語が湧いてくるし、赤字の取材旅行に取材の門前払いも日常茶飯事。出版や報道関係者と名刺交換をすれば「宇宙の記事だけで食べていくなんて絶対無理だ」といまだに叱られることもある。それでも、大好きな宇宙を身近に感じられたり、誰かの生活を支えていたりする瞬間に立ち会えるとうれしい。だからこの仕事を辞められない。 本書ではアメリカのケネディ宇宙センターや鹿児島の種子島宇宙センターをはじめとする取材先でのほっこりエピソード、誰かに話したくなる豆知識、取材先での失敗談、思わず泣いてしまったこと、本当にあった怖い話などを、宇宙開発と宇宙ビジネスの現状について綴った。笑いながら読んでいただきつつ、宇宙への興味を持ったり、自分らしい働き方を探ったりすることに役立ててもらえたらうれしい。 宇宙を書く仕事の舞台裏へようこそ。 【編集担当からのおすすめ情報】 はやぶさに憧れた高校生はいかに宇宙ライターになったのか? 宇宙に興味をもったきっかけ、ウクライナ・キーウへの留学、取材での苦労、先輩宇宙ライターや宇宙開発関係者との絆、知られざる宇宙開発の現場など、楽しみながら宇宙開発や宇宙ビジネスを学べます。誰もが宇宙を仕事にできる時代、宇宙をもっと身近に感じられる宇宙エッセイです。これからのキャリアを考えるきっかけにも。
-

【新刊】『しゅうまつのやわらかな』浅井音楽(サイン本)
¥1,980
四六判並製/224ページ(サイン本) ―鮮明に思い出せることほど、ほんとうは忘れられたことなのかもしれない。 忘却と喪失。停滞と安寧。異端の言語感覚で綴られる、過ぎ去った日々の心象。 随筆。小説。詩。日記。変幻自在に境界を超える筆致が織りなす待望の随想集。 装画:つくみず 装丁:名久井直子
-

【新刊】『SA001』杉森仁香(サイン本)
¥880
A5判/132ページ 『夏影は残る』で第30回(2021年度)やまなし文学賞を受賞した杉森さんの少し後味の悪い短編集。
-

【新刊】『文豪と犬と猫 偏愛で読み解く日本文学 』(サイン本)
¥1,760
四六判並製/160頁 こんな読み方があったのか! 文豪と作品の、意外な姿が見えてくる。 犬派と猫派、気鋭の文筆家ふたりが往復書簡で語り合う ニャンともワンダフルな文学世界、ここに誕生。 犬好き文芸評論家・エッセイスト宮崎智之(『平熱のまま、この世界に熱狂したい』)と、猫好き日本文学マニアの文筆家・山本莉会による、文豪×犬・猫トークが炸裂! 犬も猫も日本文学ももっと大好きになるエッセイ風の往復書簡です。 目次 ■はじめに 1、 夏目漱石+犬 「猫」ではない大文豪の真実 2、 内田百閒+猫 ノラ帰らず、涙目の日々 3、 志賀直哉+犬「駄犬」呼ばわりしていたのに 4、 谷崎潤一郎+猫 私は思い通りに使われたい 5、 川端康成+犬 涙をぼろぼろ流して泣く犬もいた 6、 森茉莉+猫 コカ・コーラの瓶の目から見た人間界 7、 幸田文+犬 動物のからだで一番かわいいところ 8,、室生犀星+猫 人はいかにして猫に目覚めるか 9、 坂口安吾+犬 「堕落論」と犬 10、三島由紀夫+猫 天才が愛した美の獣 11、遠藤周作+犬 「合わない洋服」を着こなすために 12、二葉亭四迷+猫 人畜の差別を撥無して ■おわりに 著者 宮崎智之(みやざきともゆき) 文芸評論家、エッセイスト。1982年、東京都出身。著書に『平熱のまま、この世界に熱狂したい 増補新版』(ちくま文庫)、『モヤモヤの日々』(晶文社)など。共著に『つながる読書 10代に推したいこの一冊』(ちくまプリマー新書)、日本文学の文庫解説を多数手掛ける。『文學界』にて「新人小説月評」を担当(2024年1月〜12月)。犬が好き。 山本 莉会(やまもとりえ) 文筆家。1986年、大阪府出身。大学では日本文学を専攻。広告代理店を経て編集プロダクションに入社。Après-midi 公式noteで「東京文学散歩」連載、ほか多数エッセイを執筆。猫が好き。 カバービジュアル 花松あゆみ カバーデザイン 小川恵子(瀬戸内デザイン) 本書の売上の一部は、公益社団法人アニマル・ドネーションを通じて全国の動物福祉活動を行う団体に寄付されます。
-

【新刊】『湖まで』大崎清夏(サイン本)
¥2,200
四六変形判並製/160p 歩いていった先に大きな水の塊があることは安心だった。 海でも川でも湖でも。 いまを生き、いまを描く詩人による 詩と散文のさきに見出された光り溢れる 初めての書き下ろし連作小説集。 ひとと出会い、土地に触れ、わたしはわたしになっていく。 みずからの世界の扉をひらく全5篇。 目次 湖畔に暮らす 眼鏡のバレリーナのために 次の足を出すところ みなみのかんむり座の発見 二〇二四年十一月三日 著者略歴 大崎清夏【著】 2011年、第一詩集『地面』刊行。『指差すことができない』で第19回中原中也賞受賞。詩集に『暗闇に手をひらく』『踊る自由』『新しい住みか』、その他の著書に『私運転日記』『目をあけてごらん、離陸するから』などがある。協働制作の仕事に、奥能登国際芸術祭「さいはての朗読劇」(22、23年)の脚本・作詞、舞台『未来少年コナン』(24年)の劇中歌歌詞、オペラ『ローエングリン』(24年)の日本語訳修辞、ダンスパフォーマンス『渋谷への手紙 ~LOVE HATE SHOW ~』(25年)の共同構成・語りなど多数。2025年春、山の暮らしをゆるゆると開始。
-

【新刊】『ぼちぼち』 藤岡みなみ
¥2,200
四六判・並製/324ページ ページを開くと勝手に話しかけてくる! 10年分の雑談をまとめた“読むラジオ” はるか昔「人気DJランキング」AM部門第1位を獲得したこともある著者による、大ボリュームの小ネタ集。 1分でニヤリとできる、どうでもいいのになぜか聴きたくなるエピソードトークの秘訣がここに(あるといいな)。 寝る前、トイレの中、入院時、通勤中など、生活のそばに置いてただ笑ってほしいだけの本です。 装画イラスト・題字は『夏がとまらない』『大丈夫マン』の藤岡拓太郎さん。 目次: マジシャンに間違えられた父/ タオルがないのに足湯/ めずらしいどんぐりじゃない/ 豚の睾丸を託された話/ オッケーオッケーの人になる/ ほじくりにくい苗字/ 仮面をリクエスト/ カニを持ってうろつく/ マンドリルの顔をまじまじ見る/ 普通の秘伝のタレ/お 坊さんの愚痴/ 茶色いピクニック/ 人面魚を見つける……などエピソードトーク約270本を収録。
-

【新刊】『人間的教育』 佐川恭一(サイン本)
¥2,200
SOLD OUT
四六判・並製/260ページ なぜ働かなくてはいけないのか―― すべての大人の心を抉る、不遇の天才・佐川恭一の“アンチお仕事小説”傑作選。 正直、面白すぎて、佐川恭一という存在に嫉妬!!!! ――三宅香帆(文芸評論家) 自分の分身を読んでいるような、生きることを肯定されるような感覚になった。 ――押見修造(漫画家) どうしようもなく惨めで情けない人間を愛し、競争社会の欺瞞を暴く文芸界の鬼才・佐川恭一。そのディープで人間臭い魅力をこの一冊に!受験・学歴と童貞のルサンチマンを描いてきた佐川恭一による「アンチお仕事小説」8篇を収録。電子書籍で人気を集めた「ナニワ最狂伝説ねずみちゃん」、小説すばるで話題となった「ジモン」「万年主任☆マドギュワ!」など社会人の悲哀をブラックユーモアたっぷりに描く傑作短編集。 装画=押見修造 解説=樋口恭介(SF作家) 「たとえば僕らがまだ、競争と勝利に取り憑かれているなら」