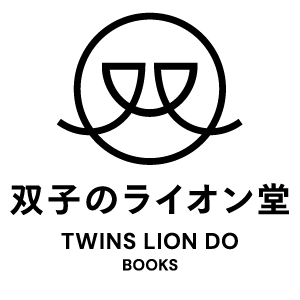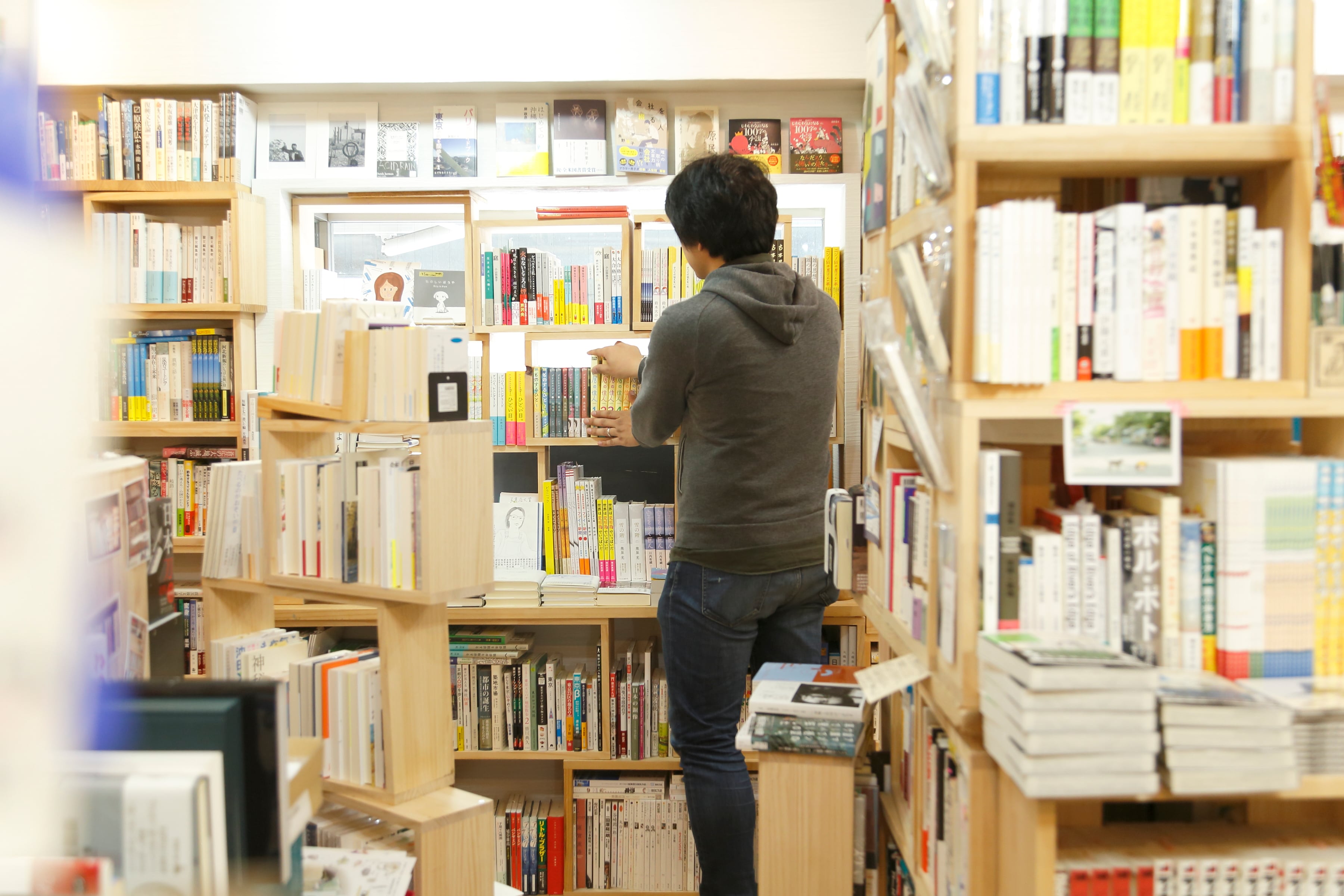-

【新刊】『本屋なんか好きじゃなかった』日野剛広
¥1,430
A6判 152ページ 12のエッセイ・6つの書評・5年間にわたる日記で構成された、文庫サイズの小さな本です。 書店員歴30年、千葉県佐倉市・志津の地で10年店長を務める著者が奮闘する日々の記録。 本屋として場を構えること。本を読むこと。音楽を聴くこと。文章を書くこと。 職業人としての矜持、政治に対しての怒り、店に足を運ぶお客への謝意、作家・出版社・同業者との連携の可能性。真摯でありながら、ちょっと抜けていたり、それでも飽くなき向上心がある著者の文章に心打たれます。
-

【新刊】『継続するコツ』坂口恭平
¥1,760
四六判・並製/240ページ みなさん、継続することは得意ですか? 得意な人はこの本は手に取っていないと思いますから、おそらくちょっと苦手ですよね。 一方、僕は継続することがむちゃくちゃ得意です。なんか自慢みたいで申し訳ありません。 でもその代わりといってはなんですが、別に質が良いわけではないと思います。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 執筆、絵描き、作詞・作曲、「いのっちの電話」…… どれも20年以上つづけてきた、スランプ知らずの継続マニア・坂口恭平さんが見つけた、 「やりたいこと」をつづけるコツが1冊に! 僕も挑戦している最中です。 最中であればいいんです。継続中ってことですから _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 多くの人は、何かをやろうとして、手をつけはじめて、 無事に完成することができたとしても、 それが売れないだとか、人から評価されないだとか、そういった不遇を味わい、 自信を失い、徒労感ばかりを感じるようになり、いずれはやめてしまうようです。 僕はいつも、もったいない!と思ってしまいます。 だって、作っているときのほうが楽しいですもん。 つまり、何かを継続しているときのほうが、楽しいんです。 この馬鹿みたいに単純なことに、僕は気づいたんです。
-

【新刊】『楽園』佐川恭一
¥1,980
四六判/264ページ これは前進か後退か? 幼い子供を抱えながら、日々の生活に疲弊する男。思い描く理想の人生と現実の狭間でもがき、ある決断を下そうとするが― 夫婦とは、家族とは何かを問う傑作小説。 「ことばとvol.7」掲載の「不服」に、書き下ろし作品「楽園」「パールライトタワー天王寺」を収録した、話題作『学歴狂の詩』の佐川恭一による最新小説! 蓄積した時間の厚みだけが二人をつなぎとめ、しかしそれは真に重要なものではない。確かにともに過ごした時間は、消え去ることのない絶対的なものかもしれない。だがそれだけだ。たんなる事実としてそれはあり、それに束縛されるかどうかは、これも信仰の問題にすぎない。
-

【新刊】『オリンピア』デニス・ボック、 (翻訳)越前敏弥
¥2,750
四六変形判/248ページ 記憶と鎮魂のファミリー・ヒストリー 第2次世界大戦をきっかけにドイツからカナダへ移住した家族を描く連作短編集。静かで平和に見える一族の生と死が詩情豊かに語られる。点景としてのオリンピック、断片としての家族の歴史。 ――レニ・リーフェンシュタールが編集したあとの映像から、この話を語ることはできないだろう。何マイルにも及ぶサブプロットや暗示的な映像が切り刻まれて黒いリボンに何度もまとめられ、忘れ去られた。 ――ぼくたち家族の才能は永遠のものだと思っていた。
-

【新刊】『ソウル (別冊 中くらいの友だち) 』
¥1,650
A5判 /144ページ 変わらぬ想いと、肯定するノスタルジー 韓国を語らい・味わい・楽しむ雑誌『中くらいの友だち』では、長年韓国とかかわってきた人々が、詩、エッセイ、翻訳、街歩き、韓国伝統食や韓国ロックなど、ユニークな視点で韓国を綴ってきました。 2024年に別冊として復活し、今回発売される別冊第2弾のテーマは<ソウル>。 豪華執筆陣の愛情と思い入れがあふれる一冊です。 ■あとがきより 「『肯定するノスタルジー』とは、都市と私たちがお互いをいたわる心象なのかもしれません。立ち尽くしてもいい。考える時間も必要なのだからと」
-

【新刊】『文学カウンセリング入門』チン・ウニョン 、キム・ギョンヒ
¥2,420
A5判 /228ページ 「読むこと」と「書くこと」が、こんなにも静かに人を癒やす。 ―文学が“カウンセリング”になるという、新しい読書のかたち― 韓国で出版された本書『文学カウンセリング入門』は、詩や文学作品を通じて、自分自身の心の模様を読み解き、癒し、育むための方法を丁寧に示した1冊です。 韓国相談大学院大学での詩人チン・ウニョンとギム・ギョンヒの講義や論文などをもとに構成された本書は、理論編(第1部、第2部)では、文学の癒しの力とその背景にある哲学・教育思想を豊富に紹介。実践編(第3部)では、シンボルスカ、メアリー・オリヴァーらの詩を用いた実践的な12のレッスンを通して、読む・書くことで自己理解と癒しを深める手法を紹介しています。 書き写しやリライトを通じて、自らの気持ちに寄り添い、誰かと分かち合う力を育てるカリキュラム。医療・教育・福祉関係者はもちろん、自分を見つめたいすべての人へ。
-

【新刊】『ちぇっくCHECK+ Vol. 2 韓国の文学と映画』
¥1,430
判/ページ K-BOOKとK-カルチャーをガイドする『ちぇっくCHECK+』はK-BOOKを愛する皆さんはもちろん、日本国内でも1つのカルチャーとして根付いてきた「K-カルチャー(韓国カルチャー)」をウォッチしたい皆さんにお届けする新媒体です。 特集 パク・ジョンミン Interview Books「MUZE」の本 Movies 俳優パク・ジョンミンの歩み 映画化してほしいと思う小説5選 映画『ケナは韓国が嫌いで』 チャン・ゴンジェ監督が綴る、小説から映画へ 「文学と映画の境界線」 映画『The Summer/あの夏』 チェ・ウニョンInterview ハン・ジウォン監督Interview 映画化したい日本と韓国が舞台の本 あなたと私のハッピーエンド イ・ミファ 映画化された文学作品の歴史を辿る 文学と映画がもっと近かった韓国(2000年以前) 成川彩 小説原作の映画(2000年以降) 佐藤結 キーワードで読み解く韓国文学と映画 「民主化」 崔盛旭 「再開発と「アパート」」 伊東順子 「ジェンダー」 佐藤結 翻訳者たちの妄想キャスティング 岡崎暢子/岡裕美/呉華順/オ・ヨンア/カン・バンファ 吉良佳奈江/清水知佐子/橋本智保/藤田麗子/古川綾子 牧野美加/吉川凪/柳美佐/渡辺麻土香 イラスト: 富田茜 Interview “部屋に飾りたくなるポスター”をつくるデザインスタジオPropaganda K-BOOKと映画ファンのための映画×BOOKスポット 光州のCinema Paradiso 稲川右樹 釜山国際映画祭に行く! Interview ストーリーマーケットの持続的発展のために 佐々木静代 K-BOOKフェスティバル2025 &「まじわる一冊」BOOKリスト 2025年秋に刊行するVol.2は、K-BOOKフェスティバル2025 in Japanの特集企画 「文学と映画」に連動。 韓国の映画界・出版界双方から注目を集めるパク・ジョンミンへの独占インタビューをはじめ、文学も映画も深く楽しむためのガイドとなる特集記事が満載です。
-

【新刊】杉森仁香『死期か、これが』(サイン本)
¥880
A5判・並製 『夏影は残る』で第30回(2021年度)やまなし文学賞を受賞した杉森仁香さんによるリトルプレス。
-

【新刊】『幸福論』アラン
¥1,760
新書判・並製/300ページ もっとも読みやすい幸福論 「本物の不幸もかなりあるにはある。そうだとしても、人々が一種の想像力の誘惑によって不幸をいっそう大きくしていることには、依然としてかわりない。自分のやっている職業について不平を言う人に、あなたは毎日、少なくともひとりぐらいは出会うだろう。そして、その人の言い分は、いつでも十分もっともだと思われるだろう。どんなことでも文句をつけられるものだし、なにも完全なものなどないからだ」 リセで哲学教授として長らく教鞭を執っていたアランの哲学は、想像力の暴走に身を委ねたり、抽象思考に終始するのでなく、また何か特別な状況を必要とするのでもない。日常を生きる場で、幸福への道筋を見つけだしていくのである。 自分自身の気分の揺らぎがときには不幸の悪循環をもたらす。不安に苛まれる時代にあって、いかに幸福を得るかの心の持ちようを教えてくれる、アラン畢生の名著。 【著者略歴】 アラン Alain 本名エミール・オーギュスト・シャルティエ(1868‐1951)。 「アラン」はペンネーム。フランスの哲学者で、パリのアンリ4世校など名門リセで哲学教授を務めた。抽象思考に終始するのではなく、わかりやすい日常生活の場面の中で、「幸福とは何か」を追究した。著書はほかに『人間論』『諸芸術の体系』『哲学講義』など。弟子にアンドレ・モーロワやシモーヌ・ヴェイユがいる。
-

【新刊】『ホントのコイズミさん YOUTH』小泉今日子(サイン本)
¥1,650
SOLD OUT
小泉今日子さんが毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくSpotifyオリジナルポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』が、本になりました。 〈YOUTH 収録ゲスト〉 松浦弥太郎さん(エッセイスト・COW BOOKS 創業者) 竹田信弥さん(双子のライオン堂 店主)、田中佳祐さん(ライター) 中村秀一さん(SNOW SHOVELING 店主) 江國香織さん(作家)
-

【新刊】『迂闊 in progress 『プルーストを読む生活』を読む生活』丹渡実夢
¥2,970
四六/564ページ 本を読む 思いだす プルーストのある日々 二十二歳の誕生日にマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』14巻セットをもらった著者は、迂闊にもプルーストを読む生活をはじめてしまう。 伴走(=併読)するのはもちろん柿内正午『プルーストを読む生活』だが、本家と同じく逸脱し、かつて読んだ本や観た映画、これまでの人生におけるさまざまなできごとを思いだし、また戻り、より重層的な思考と筆致になっていく。 そうして「プルーストを読む」ということが習慣になったとき。そこにあるのは回復と、その練習の日々だった――。 解説・柿内正午 巻末に「この日記の時期に読まれていた本」「この日記の時期に観られていた映画」のリストを収録。 日記の中で言及される作家や著者たち:多和田葉子、岡 真理、柴崎友香、植本一子、滝口悠生、町屋良平、濱口竜介、保坂和志、G・ガルシア= マルケス、ヴァージニア・ウルフ、ポール・B. プレシアド、シモーヌ・ヴェイユ……などなど。 絶え間ない思考の濁流のなかで、誰かを、わたしを想う。書くことも読むことも、すべてがわたしを作っていく。書いたことも書かなかったことも、すべてが血肉になっていく。いつだって、何かを思わずにはいられない。きっと何度でも、わたしは生まれ変わることができる。 僕のマリ(文筆家) 丹渡さんの度を越したインプット量にあてられて、もっと本が読みたくなったし、映画を観たくなってきた。 柿内正午(町でいちばんの素人) 本書はプルーストを1文字も読んだことがない私にも楽しく読めましたし、気がついたらプルーストを読み始めていました。 編集担当 関口竜平 冒頭部分の試し読みはこちらから 【著者略歴】 丹渡実夢(たんど・みゆ) 2001年、千葉県生まれ。文筆、ライター、フラヌーズ。ミニシアターでアルバイトをしつつ、映画館で映画を見ている。ポケモンパンのミニ蒸しケーキいちごが好き。リアルサウンド映画部にて記事執筆。
-

【新刊】『魂の声をあげる現代史としてのラップ・フランセ』陣野俊史(サイン本)
¥2,420
サイズ:四六判 ページ:365 ※サイン本です。 世界中で関心が高まっている、「声をあげる」ことの重要さ。 ラップをとおして世界を知ろう。 郊外の貧困、移民、宗教、暴動、テロ、#MeToo… 世界を取り巻く社会問題に対して放たれるラップのリリック(歌詞)は、国境を越えてわたしたちを鼓舞し、今につながる世界の歴史を知ることの大切さを気づかせてくれます。 移民社会フランスに生きるルーツもスタイルも多様なラッパーたち。 彼らのあげる声をとおして、広い世界に目を向けてみてはいかがでしょうか? わたしたちの「いま」と「ここ」がラップにはある――。
-

【新刊】『はじめて読む! 海外文学ブックガイド : 人気翻訳家が勧める、世界が広がる48冊』越前敏弥、金原瑞人、三辺律子、白石朗、芹澤恵 、ないとうふみこ
¥1,562
四六/224ページ 《NHK基礎英語2》のテキスト連載「あなたに捧げるとっておき海外文学ガイド」を書籍化。英語圏に加え、12名の各国語の翻訳家による推薦書を新規収録。新しい世界を覗いてみない? 18人の翻訳家がナビゲートする本は以下の通り、 毎週1冊、1年を通して48冊の本をご紹介します。 第1週〜3週はもとは英語で書かれた本、 第4週は世界のさまざまな言語で書かれた本の日本語翻訳版です。
-

【新刊】『四季と機器』池谷和浩
¥1,870
B6判無線綴じ/200ページ 二子玉川へ移転した大学の霧信号所キャンパスは、ずっと霧に包まれている。灯子はスタッフや教員たちと、学生たちの学ぶ場が快適であるよう、日々その運営にあたっていた。 キャンパスには猫が闊歩しているが、黒猫を、一度に二匹以上見たことが無い。 そして、そこに「あるはずのないもの」が発見される。 猫は何匹いるのか。キャンパスは正常に運営できているのか? 予定外の出来事やプライベートでの変化があっても、続く日常。 デバイス、アプリ。21世紀のテクノロジーが当たり前のベースとなった私たちの社会で、新しくなったことと変わらない人の営みの細部を描き切った小説。 デビュー小説『フルトラッキング・プリンセサイザ』から重なる登場人物たちは、池谷作品が文学の王道でもあるサーガとして構築されていること、池谷氏が大きな構想をもった作家であることを証している。 喪失の痛み、もうひとつの声を軸にシンフォニックな世界を描いた池谷和浩の新境地であり、この新しさは世界に通じる文芸作品である。 装画 加藤オズワルド 装丁 図工ファイブ
-

【新刊】『ひとり出版流通攻略ガイド』海猫沢めろん・江藤健太郎
¥1,300
B6判無線綴じ/106ページ 個人出版や同人誌から商業書籍、編集・デザイン・販売と出版に関する一通りのことはやってきた氷河期世代の作家・海猫沢めろんさんと、学生時代から文学賞に応募するも手応えなくひとり出版に舵を切り初単行本を爆誕させた新人・江藤健太郎さん。経緯は異なるものの、同時期に自身の作品を商業ベースで出版した二人に、ISBN取得に至る経緯、やってみてわかった事などを中心に、ひとり出版をたっぷり語っていただきました。 ほか注目のひとり出版社&レーベルへのアンケート、参考図書やコラムで印刷・出版・流通の実際や基礎知識をガイドします。自分の手の届く範囲から一歩先に本を届けてみたいあなたに! 70ページ超の対談部分は、自身が起したひとり出版社・泡影社から『ディスクロニアの鳩時計』を出した海猫沢めろんさんと、同じくひとり出版社のプレコ書房から『すべてのことばが起こりますように』を出した江藤健太郎さんによるもので、生活や執筆の場も兼ねた事務所で出版するがゆえのお悩みから、流通システムの問題まで自由に語っていただいています。 海猫沢 めろん 1975年生まれ。高校卒業後、紆余曲折を経て上京。文筆業に。2004年『左巻キ式ラストリゾート』でデビュー。『愛についての感じ』で第33 回野間文芸新人賞候補。『キッズファイヤー・ドットコム』で第39回野間文芸新人賞候補、第59回熊日文学賞受賞。2025年ひとり版元「泡影社」を設立、『ディスクロニアの鳩時計』刊行。 江藤 健太郎 1999年 神奈川生まれ。会社員。2019年から小説を書く。2025年ひとり出版レーベル 「プレコ書房」を立ち上げ、初小説集『すべてのことばが起こりますように」を自ら刊行。現在、第2作品執筆&制作中。2026年春刊行予定。名作の復刊計画も構想中。好きなものは、魚。
-

【新刊】『文化系トークラジオLife ZINE~ブックガイド582冊』
¥2,200
B6判・横・無線綴じ/フルカラー/ページ LifeのZINE第2弾。2014年から開催している「ブックトークイベント」で配布してきたおすすめ書籍と解説をまとめた「ブックリスト」を収録。扱った書籍は全582冊。
-

【新刊】『沈黙をあなたに』マリオ・バルガス=リョサ
¥2,750
四六/297ページ ノーベル賞作家でありラテンアメリカ文学を牽引した巨匠による、 喜劇と悲劇、そして音楽と本と祖国への愛に満ちた人間賛歌。 クリオーリョ音楽の研究者トーニョが出会った、世界で最も美しいギターの音色。そしてその奏者であるラロ青年の夭折。それらはリマ近郊でつつましく暮らすトーニョの人生をすっかり変えてしまった。彼について、そしてこの国の音楽について本を書かなくては! 使命感に燃えるトーニョだが、その熱意は様々な人を巻き込んでいき……。 2025年4月に逝去したペルーの巨匠、その最後の小説。 【著者プロフィール】 マリオ・バルガス=リョサ Mario Vargas Llosa 1936年、ペルーのアレキパに生まれる。20世紀後半の文学を代表する作家のひとり。 1959年に短篇集『ボスたち』でデビュー。初の長篇『都会と犬ども』で注目を浴び、生涯にわたってセルバンテス賞など数々の受賞歴を誇る。2010年にはノーベル文学賞を受賞した。 著書に『緑の家』『ラ・カテドラルでの対話』『フリアとシナリオライター』『世界終末戦争』『密林の語り部』『チボの狂宴』『楽園への道』『ケルト人の夢』『激動の時代』など多数。 2025年4月13日に逝去。本書は著者が生前に刊行した最後の小説となった。 【訳者プロフィール】 柳原孝敦 (やなぎはら・たかあつ) 1963年鹿児島県名瀬市(現・奄美市)生まれ。東京外国語大学大学院博士後期課程満期退学。東京大学大学院人文社会系研究科教授。著書に『ラテンアメリカ主義のレトリック』(エディマン/新宿書房)、『テクストとしての都市 メキシコDF』(東京外国語大学出版会)。訳書にアレホ・カルペンティエール『春の祭典』(国書刊行会)、ロベルト・ボラーニョ『野生の探偵たち』(共訳、白水社)、セサル・アイラ『文学会議』(新潮社)、フアン・ガブリエル・バスケス『物が落ちる音』(松籟社)など。
-

【新刊】『もうしばらくは早歩き』くどうれいん
¥1,760
四六/208ページ この世はわたしを動かすもので満ちている! 乗り物に動物、多彩な移動手段を使った先に立ち現れる、豊かでいとおしい風景たち。短歌から小説まで、言葉と心を通わせてきた書き手が贈る、一歩ふみ出すエッセイ集。
-

【新刊】『たまさかの古本屋 シマウマ書房の日々』鈴木創
¥2,200
四六/254ページ ◤推薦◢ 牟田都子(校正者) 「本が人間よりも長く生きるためには、鈴木さんのような人が必要なのだ。」 良書は巡る、バトンのように 名古屋・今池の古本屋店主が綴る、本と人の20年。 ぶらりと立ち寄るご近所さんから、学生などの若い世代、作家やクリエイター、大学の研究者まで、さまざまな人が訪れる町の古本屋・シマウマ書房。 活字離れといわれる昨今だが、新刊書店や図書館とはまた別の角度から、本と読者をつなぐ役割を担っている。日々の仕事のなかで多くの書物や人と接し、見て、考えてきた店主が、本の豊かな魅力、読書の醍醐味、活字文化のこれからを綴ったエッセイ集。 *** 「日常ということでいうならば、町の古本屋としてのシマウマ書房の日常は、とかく地味な仕事の繰り返しである。いつも同じ場所にいて、雨の日も風の日も決まった時間に店を開ける。お客さんが来るとは限らない。それでも、買い取りをした本の埃を払い、値段をつけて棚に並べておく。注文が入れば梱包して発送する。いつもそれだけのこと。でも、それを退屈とは感じていない。むしろこうした毎日の繰り返しにこそ、意味があると思っている。」 *** 【著者】鈴木 創(すずき・はじめ) 1973年、東京都生まれ。 2006年に名古屋市千種区の本山で古書店「シマウマ書房」を開業。 2019年に店舗を移転、現在は千種区の今池で営業をしている。 2014年より朝日新聞(東海・地域面)にてコラム「本の虫」を連載中。 編著書に『なごや古本屋案内』(風媒社)がある。 *** 【目次】 ⅰ 古本屋の日々 浜辺にて 古本の買い取り 小さな循環 遠方からの注文 レジのやりとり 本棚のある生活 振り子の人 郵送と注文 本の手触り いつか読もうと思いながら ページに挟まれた切符 列車ニテ読ム Aさんの『郷愁』 星を売る人々 「万置き」事件 古本屋の匂い AIの時代 頭のなかの地図 機が熟す 夏の終わりに ⅱ 本をつなぐ 本屋の曖昧さ 偶然の読書 ドイツの二人 影との対話 日記のなかの時間 栞を挟む こよりを撚る 読書の「あるある」ネタ 言葉は空を舞い、書はとどまる ランプと銭湯 小さな明かり 揺れる日々 本棚の向こう側 くじ 縞模様 手のひらほどの庭 ウミガメのシルエット 道徳と倫理 読むことのメカニズム ⅲ 生活と読書 家族について 子供たち 本を読み始めた頃 土のなかのスプーン 長針と短針 仮設住宅と猫たち 本の虫養い 本の本たる所以は 歴史と日常 あこがれの詩人 文字を刻む 祖母の田舎とリンゴの木 栗の木とスズメバチ 思い出の一ページ 年の瀬に 思いつくまま あとがき
-

【新刊】『10:04』ベン・ラーナー
¥2,530
新書/324ページ 《オースター、フランゼンが絶賛する期待の若手 小説の執筆に挑む詩人の、美しく愉快な語り》 「全ては今と変わらない――ただほんの少し違うだけで」 主人公の詩人を通じて語られる、「世界が組み変わる」いくつもの瞬間。身体感覚は失われ、過去と未来、事実と虚構(フィクション)……あらゆる境界が揺らめきだす。 オースター、フランゼンが才能を評価する米の若手作家による「遊歩(フラヌール)」小説。 「タコは手足に触れるものの味まで感じることができるが、身体感覚は鈍い。〔……〕局所的な肌理(きめ)の違いは分かっても、その情報を統合してより大きな像を描くことはできず、世界というリアルな虚構(フィクション)が読み取れない。何が言いたいかというと、僕の体は各部分が神経学的な自律性――空間的であると同時に時間的な――を持ち始めたということだ。心臓が収縮するたびに、柔軟すぎる大動脈がわずかとはいえ拡張し、未来が僕の中で崩れていった。」(本文より) 「私たちが本書で目にするのは、現実と『ほんの少し違う』世界だ。〔……〕語り手は冒頭で、『同時に複数の未来に自分を投影してみようと思う』と宣言する。それはつまりこの小説の中では、先ほど述べたような『ほんの少し違う』世界が、疑似時間旅行を経た複数の未来として表象されていることを意味している。」(「訳者あとがき」より)
-

【新刊】『高校のカフカ、一九五九』スティーヴン・ミルハウザー
¥2,750
四六/200ページ 内気な高校生カフカの思春期の情景を描く表題作、梯子を天高く伸ばす熱に浮かされる町を描く一篇など、職人技が光る不可思議な9篇。
-

【新刊】『ナラティヴの被害学』阿部幸大
¥2,420
四六/336ページ なにが暴力で、なにが暴力でないのか。誰が被害者で、誰が加害者なのか。あなたはその当事者なのか、それとも部外者なのか──本書は「ナラティヴの被害学」という方法論によって、こうした暴力にまつわる諸問題に取り組む。 ある複雑な事象を、加害者たる「やつら」と被害者たる「われわれ」という二元論によって単純化するナラティヴは、暴力は「やつら」の問題なのだとわれわれに教える。そうしたナラティヴが、いかにわれわれの思考を、感情を、言動を、そして誰に同情し、誰を嫌悪するかを強力に規定しているか。ナラティヴの被害学とは、そのことをクリティカルに検討するための枠組みである。 いま、暴力を「やつら」の手から奪還し、加害性を社会全体に再配分せねばならない──まさしく暴力を回避するために。 昭和天皇裕仁「玉音放送」を皮切りに、トニ・モリスン『ビラヴド』、ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』、ハーマン・メルヴィル「バートルビー」、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』、映画『トップガン』シリーズといった諸作品の分析をつうじて、本書『ナラティヴの被害学』は歴史理解における被害性と加害性の重層的なポリティクスを解きほぐす。 遊戯としての人文学から脱却し、人文学の存在意義をクリティカルに問う研究書の誕生! 本書は2024年に『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(光文社)を上梓した筆者が、どのように論文執筆力を培ってきたのか、その成長過程を追った実践例集でもある。 各章は執筆の時系列順に並んでおり、また各章の扉には、章の概要(アブストラクト)に加えて、いつどのような経緯で執筆し、どの学術誌に投稿し、ときに落とされ、どのような改稿を経て掲載に至ったのか、さらには現時点から振り返っての容赦ない批判コメントも付した。 これは研究書であると同時に、世界で活躍する人文学徒のための教育書でもある。 【じっさいは複雑でそのように整理すべきではない事象を被害と加害の二元論によって単純化しつつ、問題を善き「われわれ」と悪しき「やつら」の対立へと還元し、暴力と加害を他者の領域に追いやる、そのようなナラティヴの諸効果を暴くために、そしていかにわれわれが意図せずそのようなナラティヴに毒されているのかを暴くために、被害学はある。[…]いま、暴力を「加害者」の手から奪還し、加害性を社会全体に再配分せねばならない──まさしく暴力を回避するために。】……「第1章 ナラティヴの被害学」より ■各章で論じる対象・作家・作品 「玉音放送」/ノラ・オッジャ・ケラー『慰安婦』/トニ・モリスン『ビラヴド』/ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』/デブラ・グラニク『足跡はかき消して』/ハーマン・メルヴィル「バートルビー」/『トップガン』シリーズ/村上春樹…
-

【新刊】『文士が、好きだーっ!!: 或る書店主の文学偏愛ノオト』坂上友紀
¥1,870
四六/304ページ 紹介された文士にめろめろです! 人生でこんなに文士が魅力的に見えたことない! ──三宅香帆 縦横無尽に駆け抜ける自由な文体、笑っちゃうくらい熱い口調! 坂上さんの文士愛に呑み込まれ、楽しく酔わされました☆ 個性豊かな文士の面々に、新たな気持ちで出会えます。(豆知識も増えます)。 ──大島真寿美 井伏鱒二は“かわいい系”、室生犀星は“乙女子”、堀辰雄は”実は骨太”、そして神西清の知られざる“やさしさ”––! 読めば文士たちが綺羅星のごとく光り出す、前人未到の文学案内☆★☆ 「わたしが日々胸をときめかせているところの「文士」とは、つまりは剣一本で勝負する剣士のように、「文の腕一本で勝負している!」感が、その生きざまからも作品からも、バッシンバッシンに伝わってくるようなひとたちのことでございます!」──「はじめに」より
-

【新刊】『2人は翻訳している』すんみ・小山内園子
¥1,980
四六/163ページ 翻訳とは、ことばとは、それが生まれる世界とは。 気鋭の韓日翻訳者2人がつむぎ合う、仕事、社会、人生。母語で書いたエッセイをお互いが訳した一編を二言語で収録。