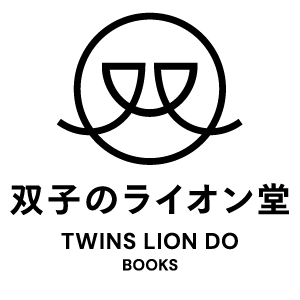-

【新刊】『幸福論』アラン
¥1,760
新書判・並製/300ページ もっとも読みやすい幸福論 「本物の不幸もかなりあるにはある。そうだとしても、人々が一種の想像力の誘惑によって不幸をいっそう大きくしていることには、依然としてかわりない。自分のやっている職業について不平を言う人に、あなたは毎日、少なくともひとりぐらいは出会うだろう。そして、その人の言い分は、いつでも十分もっともだと思われるだろう。どんなことでも文句をつけられるものだし、なにも完全なものなどないからだ」 リセで哲学教授として長らく教鞭を執っていたアランの哲学は、想像力の暴走に身を委ねたり、抽象思考に終始するのでなく、また何か特別な状況を必要とするのでもない。日常を生きる場で、幸福への道筋を見つけだしていくのである。 自分自身の気分の揺らぎがときには不幸の悪循環をもたらす。不安に苛まれる時代にあって、いかに幸福を得るかの心の持ちようを教えてくれる、アラン畢生の名著。 【著者略歴】 アラン Alain 本名エミール・オーギュスト・シャルティエ(1868‐1951)。 「アラン」はペンネーム。フランスの哲学者で、パリのアンリ4世校など名門リセで哲学教授を務めた。抽象思考に終始するのではなく、わかりやすい日常生活の場面の中で、「幸福とは何か」を追究した。著書はほかに『人間論』『諸芸術の体系』『哲学講義』など。弟子にアンドレ・モーロワやシモーヌ・ヴェイユがいる。
-

【新刊】藤井青銅『ラジオな日々』【愛蔵版】(サイン入り)
¥5,500
新書サイズ、上製本/頁/サイン入り/数量限定 2025年クラウドファンディングで話題を集めた『ラジオな日々』の愛蔵版がついに完成! 愛蔵版のみの書き下ろし+青銅さんが使っていた放送作家用原稿用紙のレプリカも! 長く読んでいただくために、特製のスリーブもご用意しました。 『ラジオな日々』は、70年代終わりに放送作家として歩み始めた著者が、80年代のラジオ業界で奮闘する日々を自伝的なタッチで描いた青春小説です 。右も左も分からない若者が、個性豊かなディレクターに鍛えられ、当時の人気アイドルたちと仕事をする中で、深夜放送のアニメ特番に熱狂するなど、当時の熱気が鮮やかに描き出されています 。 物語には、松田聖子、伊藤蘭、横山やすし、大滝詠一といった実在の人物も登場。「まだ何者でもない若者が何者かになろうとする姿」は、時代を超えた普遍的な青春小説として読者の心を捉えます。2007年4月に小学館より単行本として刊行されました。 *通常版として、朝日文庫からも同名の『ラジオな日々』が発売しています。併せてお楽しみください。 復刊への道のりは下記YouTubeにてまとめてあります。 https://www.youtube.com/playlist?list=PL1IqsZNwUAGYDQtxfhGGMcNJj-wiNx8vR クラウドファンディングに関しては下記サイトをご確認ください。 https://ubgoe.com/projects/864
-

【新刊】『モータープール』岸政彦(オリジナルポストカード付き)
¥2,750
B6判横・並製/224ページ/オリジナルポストカード付き 新境地。 社会学者・岸政彦が フィルムカメラで撮った静かな街の記憶。 185枚のスナップと1篇の書き下ろしエッセイを収録。 そこにあるものは——— 社会学者・小説家と活躍する岸政彦による初の写真集。 主に大阪の街を歩きながら見つけた風景をフィルムカメラで撮影した1冊です。 <書誌情報> 著者:岸政彦 構成:東万里江 ブックデザイン:中村圭佑 発売日:2025年10月31日ごろ 定価:2500円+税 判型:B6判、並製 ページ:224頁 ISBN: 978-4-910144-17-7 発行元:双子のライオン堂出版部 岸政彦 きしまさひこ/社会学者・作家。京都大学大学院文学研究科教授。主な著作に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版)、『街の人生』(勁草書房)、『断片的なものの社会学』(朝日出版社)、『ビニール傘』(新潮社)、『マンゴーと手榴弾─生活史の理論』(勁草書房)、『図書室』(新潮社)、『大阪』(柴崎友香と共著、河出書房新社)、『リリアン』(新潮社)、『東京の生活史』(筑摩書房)、『沖縄の生活史』(みすず書房)、『大阪の生活史』(筑摩書房)、『にがにが日記』(新潮社)、『調査する人生』(岩波書店)など。
-

【Tシャツ】双子のライオン堂12周年記念Tシャツ第3弾(イラスト・大谷津竜介)
¥3,300
SOLD OUT
双子のライオン堂実店舗12周年の記念に作家とコラボしたオリジナルTシャツを作ります! 第3弾は、大谷津竜介さんによるイラストです。 色:黒地 サイズ:フリーサイズ(身丈:72、身幅:56、肩幅53、袖丈22)
-

【新刊】『小説を書くこと、続けること、世界と繋がること』〈対談録 太田の部屋2〉太田靖久・旗原理沙子
¥990
新書判/82頁 双子のライオン堂書店で、連続で開催している小説家の太田靖久さんと様々なクリエーターが「つくる」をテーマに語り合う配信イベントのZINEのシリーズ第2弾を刊行します。 第2弾は、小説家・旗原理沙子さんと行った対談と、文学賞を受賞した旗原さんに太田さんが追加で7つの質問を送り、それに応答するエッセイを収録しました。 <基本情報> 書名:『小説を書くこと、続けること、世界と繋がること』〈対談録 太田の部屋2〉 著者:太田靖久・旗原理沙子 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年11月23日(文学フリマ東京) 予価:900+税 判型:新書判、並製 ページ:82頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)、『犬の看板探訪記 関東編』(小鳥書房)など。文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店や図書館での企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号で出店も行っている。 旗原理沙子(はたはら・りさこ) 小説家。1987年群馬県生まれ、東京、大阪など転々として育つ。2021年、「代わりになる言葉」を電子書籍で刊行しインディーズデビュー。2024年「私は無人島」で第129回文學界新人賞受賞。「犯罪者と私」( 文學界2024年12月号)など。 <「はじめに」> 本書には私と旗原さんの対談(2023年11月開催)を再構成したテキストに加え、その約2年後(20 25年8月)の私からの7つの問いに対する旗原さんの応答形式のエッセイを収録しました。 旗原さんは2024年に『文學界』新人賞を受賞されているため、対談はその前の出来事であり、エッセイはその後のこととなります。 社会通念としては新人賞の受賞を機に対外的にも作家と認められるのかもしれませんが、物事の本質はそれほど単純ではないでしょう。小説を書き続けていなければその人は小説家ではないのかもしれません。 旗原さんにとっての変わるもの/変わらないものの軌跡を追うことで見えてくる景色があります。それは旗原さんの独自の経験でありながら、たしかな普遍性があり、広く創作にかかわる人たちの参考にもなるはずです。(太田靖久)
-

【新刊】柿崎順一作品集『METAPHOR』(オリジナルポストカード付き)
¥7,700
29.3cm×22.7cm×2.7cm、上製本/全256頁(英日バイリンガル) ====================== *ただいま、神保町・passageにて柿崎順一さんの棚ができたことをお祝いして、新しく制作したオリジナルポストカードをおつけします! <オリジナルポストカード詳細> 作品名:柿崎順一《Mountain of passion》 写真:柿崎芽実 なくなり次第、終了となります。 ======================= このたび、双子のライオン堂は、現代美術家/フラワーアーティストの柿崎順一氏が製作した『METAPHOR』の編集協力および販売を担当することとなりました。 本書は、2019年5月下旬に長野県安曇野市の「信州花フェスタ2019」内で開催された柿崎氏の個展「METAPHOR | 比喩的な自然」に合わせて製作され、先行発売されました。 一つ一つの作品はもちろんのこと、造本設計にも力を入れており、集大成と呼ぶにはふさわしい素晴らしい仕上がりです。 ぜひ、多くの方にお手にとって頂ければ幸いです。 【柿崎順一さんからのメッセージ】 僕は作品を創るとき、植物や自然のフォルムや景色の中にいつも無意識に様々な比喩を見出だしていることに最近になってあらためて気付きました。それは例えば、木々が恋人同士に見えたり、木の実がチンパンジーになって僕をあざ笑っているように見えたりなど、たわいもないものですが、この様な実体験を皆様に提示できる形態に、それも自然の美しさを損なうことなく引き出せないかと、何とか落とし込もうとする行為をいつも繰返し行っているのです。これらの行為が一体何であるのかと振り返った時、初めて僕は自然を愉しんでいたことに気付いたのです。 <基本情報> 書名:METAPHOR 著者:柿崎順一 写真:岡本譲治、柿崎順一 翻訳:リチャード・ハート ISBN:9784990928384 価格:¥7000- +税 発行日:2019年6月21日 発行所:プラス環境芸術研究所(+PEALab.) 販売元:双子のライオン堂 製本:上製本 重さ:1.36g サイズ:29.3cm×22.7cm×2.7cm 全256頁 英日バイリンガル
-

【新刊】『太宰治『桜桃』読書会 めろんと『桜桃』を読む』
¥825
A6/中綴じ/36ページ ▼概要: 太宰治「桜桃」読書会。太宰晩年の作品、父の苦悩を描く桜桃……現代から見たその姿は、はたしてどのように見えるのか。
-

【新刊】『お笑いを〈文学〉する〜「笑える/笑えない」を超える』小田垣有輝(サイン本)
¥1,210
SOLD OUT
新書判/120頁 双子のライオン堂書店で、開催した連続講義「笑いを〈文学〉する」が書籍になります。 2024年に小田垣有輝さんをお招きして開講した授業を、書籍化に伴い授業だけでは伝えきれなかった熱い思いと独自の論をブラッシュアップして展開します。 【目次】 はじめに 1、東京03と中島敦『山月記』~トリオネタの魅力/『山月記』って本当に二人? 2、ピン芸人の構造論―「語り」か「噺」か 3、「お笑い」と「コード」ー既存のコードへの「抵抗」と「逸脱」 4、トム・ブラウンをなぜ笑う?―文学史と小川洋子『貴婦人Aの蘇生』をヒントに 5、ランジャタイとラーメンズ―谷崎・芥川の文学論争と比較して 6、ランジャタイとシェイクスピア―文学と「おばけ」の関係 ―ランジャタイとは何か 付録 登場人物紹介&参考文献 おわりに 【基本情報】 書名:『お笑いを〈文学〉する 「笑える/笑えない」を超える』 著者:小田垣有輝 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:1100+税 判型:新書判、並製 ページ:120頁 発行元:双子のライオン堂出版部 【著者】 小田垣有輝(おだがき・ゆうき) 私立中高一貫校、国語科教員。今年で教員11年目。研究分野の専門は谷崎潤一郎、語り論。教員として働くかたわら、個人文芸誌『地の文のような生活と』を一人で執筆・編集・刊行(現在vol.1~vol.6まで刊行中)。本づくりを通じて、自らが帯びる特権性と向き合う。 <「はじめに」> なぜ人は、お笑いを観て笑うのでしょうか。 「お笑い」という名称からもわかるように、お笑いはお笑いを鑑賞する者に「笑う」という反応を要請します。小説であれば、もちろん笑える小説もあるし、泣ける小説もあるし、怒りを共有する小説もあるし、漠然としたもやもやを読者に植え付ける小説もあるし、小説を読む者の反応は様々である、ということが「当たり前」となっています。しかし、一般的にお笑いは「笑う」という反応に限定されます。ネタ番組では、観覧の人々はみな笑っているし、その中に泣いたり怒ったりする人はいません。 でも、お笑いを観て「笑う」以外の反応をしたっていいはずです。そうでなければ、「笑えるお笑い=良いお笑い」という評価軸しか存在しないことになります。お笑いの中には「笑えないけど良いお笑い」だって存在します。 本書では、物語論や社会学を媒介にしながら「お笑い」と「文学」の関係を考えていきます。そうすることによって「笑えるか否か」という評価軸とは違う軸が見えてきます。私たちが普段観ているお笑いを違った視点から批評することによって、お笑いが備えている豊かな世界が立ち現れるはずです。(小田垣有輝)
-

【新刊】『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉植本一子&太田靖久(Wサイン本)
¥990
新書判/84頁/Wサイン本 双子のライオン堂書店で、連続で開催している小説家の太田靖久さんと様々なクリエーターが「つくる」をテーマに語り合う配信イベントが、ZINEのシリーズになります。 第1弾は、2023年と2025年に植本一子さんと行った2つの対談を1冊の冊子にまとめました。 ZINEやリトルプレスについて考えて続けているお二人のそれぞれの視点が交差します。 自分でも”作ってみたい”人は必携の1冊です。 また、今後のシリーズとして刊行していきますので、ラインナップにもご注目ください! <基本情報> 書名:『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉 著者:太田靖久・植本一子 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:900+税 判型:新書判、並製 ページ:84頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)、『犬の看板探訪記 関東編』(小鳥書房)など。文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店や図書館での企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号で出店も行っている。 植本一子(うえもと・いちこ) 写真家。2003年にキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞。2013年、下北沢に自然光を使った写真館「天然スタジオ」を立ち上げる。著書に『かなわない』『愛は時間がかかる』、写真集に『うれしい生活』、小説家・滝口悠生との共著『さびしさについて』などがある。主な展覧会に『アカルイカテイ』(広島市現代美術館)、『つくりかけラボ07 あの日のことおぼえてる?』(千葉市美術館)。 <「はじめに」(太田靖久)> 植本一子さんとの2回のトークイベント(2023年9月と2025年3月開催)を再構成して追記等も行い、本書に収録しました。2回目は1回目の1年半後に行われたため、その間の変化も楽しんでいただけるはずです。 今企画は双子のライオン堂の竹田さんからの提案がきっかけでした。 「太田さんは質問がうまいのでゲストを迎える形式のトークイベントを定期開催するのはいかがですか?」 すぐに快諾しました。自分の話をするより、誰かの話を聞いていたいと思うのは、知らないことを知りたいというシンプルな好奇心が根っこにあるからです。 1回目のゲストは植本さんが良いなとひらめきました。植本さんの文章には親しみやすさがあるのに、決して安全なものではなく、深くえぐってくる強度もあります。そんな植本さんのやさしさと鋭さのバランスや、創作と事務作業の使い分けについてなど、様々に興味がありました。また、ZINEに関するトークイベントをほとんど行っていないとうかがい、貴重な内容になるという判断もありました。 植本さんには登壇だけでなく、〈つくるをかんがえる〉というタイトルも付けていただきました。それが企画の方向性を固めるうえで助けになったことも忘れずに記しておきます。(太田靖久)
-

【新刊】『書かずにいられない味がある - 100年前の韓食文学』
¥2,200
四六判並製/244ページ 〈食〉は暮らしと文化の生命線 プルコギや冷麺がソウルで日常的に食べられるようになったのは、 今からたった約百年前のこと。 地方や海外の味が流入し、外食店が増え、 朝鮮半島の食文化が大きく変貌していった時代でもある。 当時の人々のいのちをつなぎ、生活を彩った〈食〉の数々が、 作家や記者らの筆によって臨場感をもって描かれる――。 どこから読んでも味のある、小説、エッセイ、ルポルタージュ40選。 ●訳者解説より すべての作品に共通する内容として、人々の食にかけるひたむきな姿勢があげられる。植民地下の厳しく、貧しかった時代、食べることは生きることと同義であった。大衆居酒屋でマッコリをあおる姿も、水っぽく薄い粟粥を懸命にすする姿も、病気の妻にソルロンタンを買って帰るため必死に働く姿も、日々を懸命に生きる人たちのリアルな日常である。そこには飽食の時代にあって、ついつい忘れがちな食への原初的な情熱が込められており、読めば読むほどに調理技術を超えた「味わい」が伝わってくる。 訳者としての立場ではあるが、一読者としても満腹度の高い一冊であった。 ――コリアン・フード・コラムニスト 八田靖史
-

【新刊】『すべてのことばが起こりますように』江藤健太郎(サイン本)
¥2,200
B6判並製/192ページ 愛、笑い、海、狂気、デジャブ、旅をめぐる「人間」たちの物語。 「書きたいから書いた。出したいから出した」 既存の文芸の枠の「外」から突如やってきた破格の初小説集。 発行所:プレコ書房 発売日:2025年4月28日 判型:128mm×182mm 造本:カバーなし ニス仕上げ 帯ステッカー付き 価格:2,000円(税込2,200円) 装画・装丁・本文レイアウト:柿木優 解説:郡司ペギオ幸夫 編集:江藤健太郎 印刷・製本:藤原印刷 ISBN:978-4-9913956-0-4 解説・推薦 郡司ペギオ幸夫(科学者・早稲田大学教授) 読み終わって、冬の浜辺で一人焚き火をしていた、存在しない記憶を思い出した。 「すべてのことばが起こりますように」の主人公であるウジャマ(内山)はデジャブとしての生を繰り返す。デジャブとして生き続けるこの感じをきっかけに、本解説もまたデジャブ体験のように書き連ねられることになる。 ああ、江藤くんですか、知ってますよ。よく覚えてます。彼は私の授業の第一回の講義で、授業が終わると教卓に走り込んできましてね、言うんですよ。「郡司さん、早稲田の理工で郡司さんの授業わかるの、俺以外いませんよ」ってね。《解説より》
-

【新刊】『いま批評は存在できるのか』三宅香帆/森脇透青/松田樹/大澤聡/東浩紀/植田将暉
¥2,200
新書判/216頁 批評の役割とは何か。どのような言葉が必要なのか。 90年代生まれの批評家たちが集まった白熱のイベントに、批評家・大澤聡と東浩紀をくわえたふたつの座談会、そして充実の書き下ろし論考まで。 いま「批評」を考えるために必読の一冊。(版元サイトより) はじめに 東浩紀 [論考]聴く批評 大澤聡 [座談会1]批評を若返らせるには──『批評の歩き方』に応答する 松田樹+森脇透青+大澤聡+東浩紀 [座談会2]2025年に批評は存在するのか? 三宅香帆+森脇透青+松田樹[司会=植田将暉] [座談会3]ひとり勝ち、あるいは批評の男子性について 森脇透青+大澤聡+東浩紀 [登壇後記]語りにくさとタイムトラベル 松田樹 [登壇後記]批評とは何か 森脇透青 [登壇後記]なぜ批評なのか 三宅香帆 おわりに 植田将暉
-

【Tシャツ】双子のライオン堂12周年記念Tシャツ第1弾(絵・くれよんカンパニー)
¥3,300
双子のライオン堂実店舗12周年の記念に作家とコラボしたオリジナルTシャツを作ります! 第1弾は、くれよんカンパニーさんの絵です。 色:白地 サイズ:フリーサイズ(身丈:72、身幅:56、肩幅53、袖丈22)
-

【新刊】『エレベーターのボタンを全部押さないでください』川内有緒
¥1,980
SOLD OUT
四六判・並製/256ページ いつも広い世界を見せてくれるノンフィクション作家・川内有緒、初のエッセイ集。 『パリでメシを食う。』でデビューし、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』で「Yahoo! ニュース|本屋大賞ノンフィクション本大賞」を受賞した川内有緒が、連載していた「日経新聞」、雑誌「ひととき」など、さまざまな媒体に寄稿したエッセイをセレクトして収録。 メキシコの走る民族、飼っていた2匹の個性的な猫、大反響を巻き起こした「荒れた海で愛を叫ぶ」……。海外での驚くべき旅や出会い、日常に潜む冒険のような出来事、死生観などを綴り、読者を新しい場所へ誘う。 ユーモラスで味わい深い文章に心が揺さぶられ、温かな感情が湧き上がる。なぜか一歩を踏み出したくなる川内有緒ならではの一冊。 川内さんは丸腰で荒海に飛び込んでいって、宝物のような出会いをつかみ取ってくる。 この本そのものが、冒険で、旅なのだ。――岸本佐知子(翻訳家) 並外れた行動力と筆致。見たことない球をぶんぶん投げてくる。――こだま(作家・エッセイスト)
-

【新刊】『ゲーム作家 小島秀夫論: エスピオナージ・オペラ』藤田直哉
¥2,970
四六判・並製/352ページ ゲームを超えた総合芸術 もはや、その作品は、詩であり、文学であり、映画であり、何よりも芸術そのものである。――ゲームクリエイターを超えた存在=小島秀夫に迫る。 全世界で六〇〇〇万本以上の売り上げを誇る『メタルギア』シリーズや、『DEATH TRANDING』などを生み出し、ゲーム作家として史上二人目に芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。 本書は、特に、監督・脚本・ゲームデザインなどを本格的に手掛けた「A KOJIMA HIDEO GAME」と呼ばれる作品群を対象に、その一貫性と全体性から、ゲームデザイナーを超えた存在=小島秀夫に迫る。 「本書は、ゲームについての研究・評論である。ゲームデザイン、システム、主題、物語などのゲーム作品についての分析と、小島秀夫という人間そのものの作家論を往還するのが、本書の方法論である。ゲーム制作は集団創作なので作家論的アプローチがどこまで可能なのか、どこまでを特定の作家に帰属させられるのかについては議論の余地があり、確立された方法論があるとは言えないが、本書は現時点でアクセス可能な資料を元に最大限の努力を試みた。」 ――本書より
-

【新刊】『偶像の黄昏/アンチクリスト』ニーチェ
¥1,980
SOLD OUT
新書判・並製/335ページ 「私はキリスト教に有罪の判決を下す。」 「私以前にはいかにいっさいの物事が逆立ちしていたかについて、手取り早く知りたいと思う方がいたら、まずこの本から取り掛かって頂きたい」(『この人を見よ』より) 「ニーチェは歴史を頭から否定し、またいちばん最後から否定する」(吉本隆明、本書解説より) ニーチェ最晩年に書かれ、彼の否定の系譜をたどる二作品を収録。キリスト教世界における神、真理、道徳、救済を否定し、ソクラテス、プラトン、カントを否定し、いま生きる現実と身体の価値を見つめなおす、いわばニーチェによるニーチェ思想の概説書。 一九九一年「イデー選書」より吉本隆明の解説を再録し、三島憲一書き下ろしの解説を追加し、ニーチェの入門書としても読むことができる一冊。
-

【新刊】『立ち読みの歴史』小林昌樹
¥1,320
SOLD OUT
新書並製/200ページ 立ち読みの歴史は読書の歴史。 かつてない読書史! 「本屋は知の狩り場であり、誰もが通える大学だった。本書はその理由を思い出させてくれる」 読書猿(『独学大全』著者)推薦! 私たちのご先祖さまは、どんな姿で本を読んでいたのか? かつて洋行知識人は口々に言った――「海外に立ち読みなし」。日本特有の習俗「立ち読み」はいつ、どこで生まれ、庶民の読書文化を形作ってきたのか? 本書はこれまで注目されてこなかった資料を発掘し、その歴史を描き出す。明治維新による「本の身分制」の解体、ニューメディア「雑誌」の登場、書店の店舗形態の変化……謎多き近代出版史を博捜するなかで浮かび上がってきたのは、読む本を自ら選び享受する我々「読者」の誕生だった! ベストセラー『調べる技術』著者がその技を尽くす野心作。 【本書の内容の一部】 ・江戸時代の本屋は「座売り」(閉架式)だった ・日本人の識字率と「本の身分制」の歴史 ・万引き犯を水責めに! 大正7年神保町の光景 ・「ハタキ」の漫画的ミームはいつ頃からあったのか
-

【新刊】『ホントのコイズミさん WANDERING』小泉今日子(303 BOOKS)
¥1,650
Spotifyオリジナルの大人気ポッドキャスト『ホントのコイズミさん』 待望の書籍化!2冊目「WANDERING」 小泉今日子が毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』。書籍シリーズ2冊目が登場します。 一部未公開部分も含み、各ゲストと連動した本だけの企画ページと一緒に、ゲストとのトークが活字と写真でよみがえります。 『WANDERING、流離、さすらい、あてもなく彷徨う。あてもなく彷徨う、そういう散歩が好きです。そういう旅が好きです。人生もそうであったほうが私らしいかなと思います。 小泉今日子』(本書あとがきより) 【豪華なゲストとの特別企画】 吉本ばななさん(小説家) 世界の『キッチン』をめぐる旅:世界各国で刊行されている『キッチン』を紹介。また吉本ばななさんに翻訳版にまつわるあれこれについて、スペシャルインタビューを行いました。 和氣正幸さん(BOOKSHOP TRAVELLER) わざわざ行きたい 祖師ヶ谷大蔵の「BOOKSHOP TRAVELLER」:お店が下北沢から祖師ヶ谷大蔵にお引っ越し。その様子をレポートします。新店舗には「コイズミ書店」ができました。 佐藤健寿さん(写真家) 佐藤健寿×小泉今日子「厚木」:「奇界遺産」で知られる佐藤さんが、コイズミさんの地元・厚木を訪ね、60年代のオールドレンズで撮影しました。 林紗代香さん 菅原信子さん(TRANSIT) 「コイズミさんと、旅の持ちもの鑑賞会」:3人それぞれ旅先を決め、実際にパッキングしたスーツケースをもちより披露しました。三者三様のこだわりのパッキングには、参考になるポイントもたくさん。 番組ファンの声に応えたミニコーナー そのほかに「WANDERING」にちなんだ内容の一問一答や、対談時にコイズミさんが着ていた服を紹介する「#コイズミさん Outfit of The Day」など、ミニコーナーも。
-

【新刊】『ホントのコイズミさん YOUTH』小泉今日子(303 BOOKS)
¥1,650
小泉今日子さんが毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくSpotifyオリジナルポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』が、本になりました。 〈YOUTH 収録ゲスト〉 松浦弥太郎さん(エッセイスト・COW BOOKS 創業者) 竹田信弥さん(双子のライオン堂 店主)、田中佳祐さん(ライター) 中村秀一さん(SNOW SHOVELING 店主) 江國香織さん(作家)
-

【新刊】『芥川龍之介「蜜柑」読書会 めろんと「蜜柑」を読む』
¥880
文庫判/52頁 「芥川龍之介『蜜柑』読書会 めろんと『蜜柑』を読む」は、名作『蜜柑』を題材にした読書会の内容をまとめた冊子です。 今回は本作をめぐる多くの謎が解かれます。
-

【Tシャツ】双子のライオン堂12周年記念Tシャツ第2弾(絵・くれよんカンパニー)
¥3,300
双子のライオン堂実店舗12周年の記念に作家とコラボしたオリジナルTシャツを作ります! 第2弾も、くれよんカンパニーさんの絵です。 色:白地 サイズ:フリーサイズ(身丈:72、身幅:56、肩幅53、袖丈22)
-

【グッズ】双子のライオン堂12周年記念トート(看板文字)
¥2,200
双子のライオン堂実店舗12周年の記念のトートバッグです。 当店のロゴや「しししし」を手がけるデザイナー中村圭佑さんが作ってくれたお店の看板の文字をデザインしました。 色:ナチュラル サイズ:高さ25cm×幅32cm×マチ10m
-

【グッズ】双子のライオン堂12周年記念トート(新ロゴ)
¥2,200
双子のライオン堂実店舗12周年の記念のトートバッグです。 当店のロゴや「しししし」を手がけるデザイナー中村圭佑さんが記念ロゴを作ってくれました。 色:ナチュラル サイズ:高さ(持ち手まで)76cm×幅45cm×マチ15cm
-

【新刊】「窓/埋葬」著:平野明/原作:横田創(Wサイン本)
¥1,100
SOLD OUT
<新刊>「窓/埋葬」著:平野明/原作:横田創(発行:双子のライオン堂) <基本情報> 書名:窓/埋葬 著者:平野明 原作:横田創(『埋葬』早川書房・2010年) 挿画:飯田千晶 校正:矢木月菜 ブックデザイン:中村圭佑 発売日:2023年4月15日(同年3/31〜4/2の上演時に先行発売) 価格:1000円+税 判型:B6判、並製、ソフトカバー ページ:72頁 ISBN:9784910144092 発行元:双子のライオン堂出版部 <概要> 双子のライオン堂は、平野明/横田創『窓/埋葬』を刊行します。本作は、2010年に早川書房から「想像力の文学」シリーズとして刊行された横田創『埋葬』の舞台化のために書かれた戯曲です。ぜひ、約10年を経て生まれたあたらしい『埋葬』をお楽しみください。 ■ 『埋葬』を読んだことがないひとはこの『埋葬』から読んでください。『埋葬』を読んだことがあるひとはこの『埋葬』をあたらしい、まだ読んだことのない『埋葬』だと思って読んでください(2023年03月04日 横田創) <著者> 平野明(ひらの・めい) 舞台作家。青森県出身。1997年生まれ。武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業。在学中(2017年)に手手(元・夜のピクニック)を結成し、劇作をし始める(『ショートケーキと往復書簡[2018]』『シアノタイプ[2019]』『まぶたのルート[2020]』『髪の島[2021]』など)。2023年『窓/埋葬』を執筆する。本書は初の著書である。 手手 公式サイト https://twitter.com/teteotetetetote <原作者> 横田創(よこた・はじめ) 作家。埼玉県出身。1970年生まれ。早稲田大学教育学部中退。演劇の脚本を書くかたわら小説の執筆を始め、2000年『(世界記録)』で第43回群像新人文学賞を受賞。2002年『裸のカフェ』で第15回三島由紀夫賞候補となる。著書に『(世界記録)』『裸のカフェ』(以上講談社)『埋葬』(早川書房)『落としもの』(書肆汽水域)がある。読書会や書籍の販売・発行を通じて読者の自由を追求する小さな書店「双子のライオン堂(東京・赤坂)」から短編小説を無料で配布・配信するプロジェクト『わたしを見つけて』を進行中。 『わたしを見つけて』公式サイト http://findme.liondo.jp/