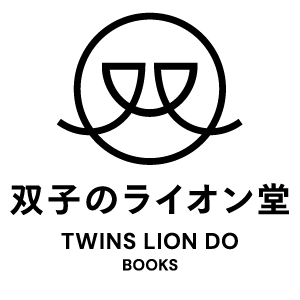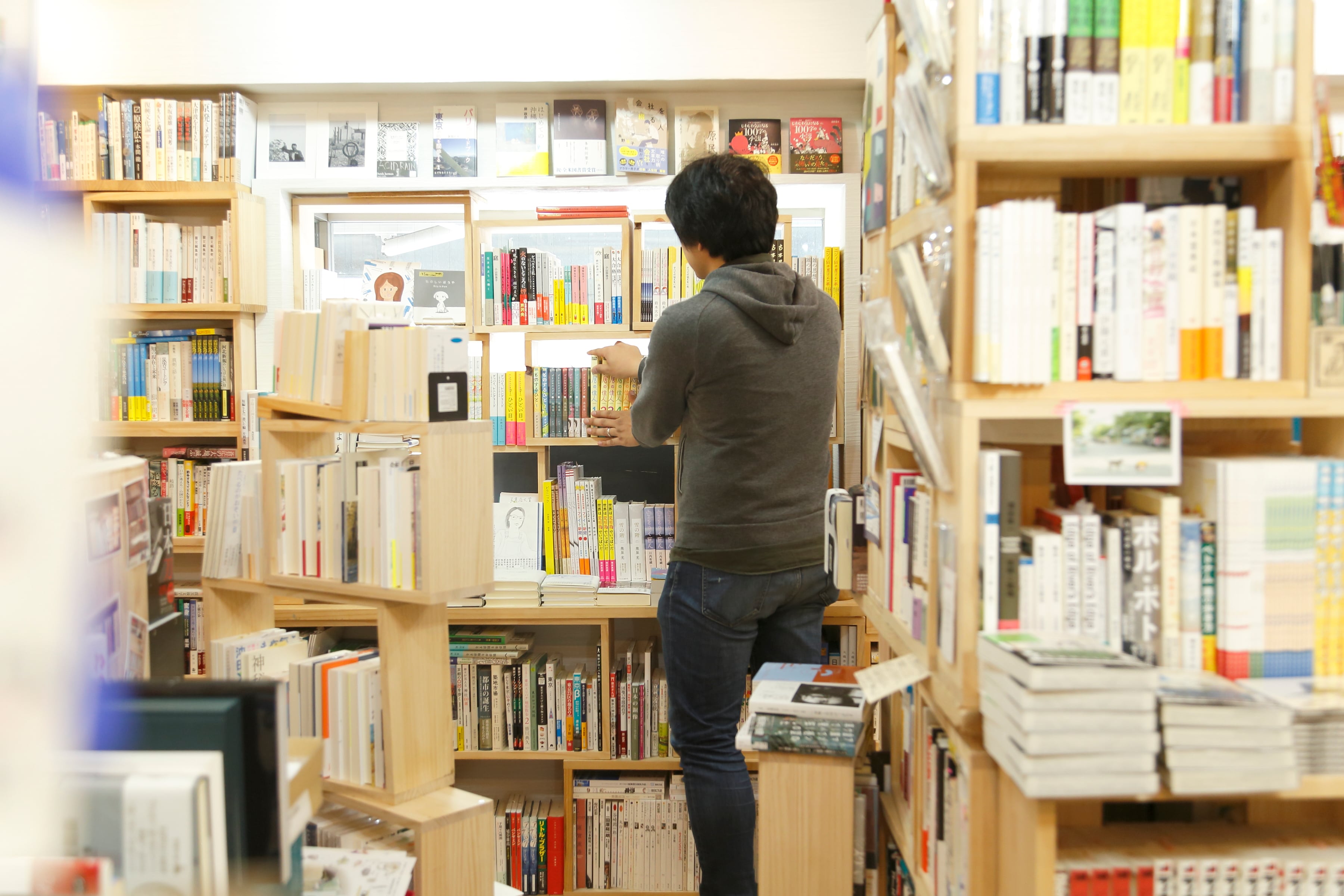-

【新刊】『お笑いを〈文学〉する〜「笑える/笑えない」を超える』小田垣有輝
¥1,210
新書判/120頁 双子のライオン堂書店で、開催した連続講義「笑いを〈文学〉する」が書籍になります。 2024年に小田垣有輝さんをお招きして開講した授業を、書籍化に伴い授業だけでは伝えきれなかった熱い思いと独自の論をブラッシュアップして展開します。 【目次】 はじめに 1、東京03と中島敦『山月記』~トリオネタの魅力/『山月記』って本当に二人? 2、ピン芸人の構造論―「語り」か「噺」か 3、「お笑い」と「コード」ー既存のコードへの「抵抗」と「逸脱」 4、トム・ブラウンをなぜ笑う?―文学史と小川洋子『貴婦人Aの蘇生』をヒントに 5、ランジャタイとラーメンズ―谷崎・芥川の文学論争と比較して 6、ランジャタイとシェイクスピア―文学と「おばけ」の関係 ―ランジャタイとは何か 付録 登場人物紹介&参考文献 おわりに 【基本情報】 書名:『お笑いを〈文学〉する 「笑える/笑えない」を超える』 著者:小田垣有輝 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:1100+税 判型:新書判、並製 ページ:120頁 発行元:双子のライオン堂出版部 【著者】 小田垣有輝(おだがき・ゆうき) 私立中高一貫校、国語科教員。今年で教員11年目。研究分野の専門は谷崎潤一郎、語り論。教員として働くかたわら、個人文芸誌『地の文のような生活と』を一人で執筆・編集・刊行(現在vol.1~vol.6まで刊行中)。本づくりを通じて、自らが帯びる特権性と向き合う。 <「はじめに」> なぜ人は、お笑いを観て笑うのでしょうか。 「お笑い」という名称からもわかるように、お笑いはお笑いを鑑賞する者に「笑う」という反応を要請します。小説であれば、もちろん笑える小説もあるし、泣ける小説もあるし、怒りを共有する小説もあるし、漠然としたもやもやを読者に植え付ける小説もあるし、小説を読む者の反応は様々である、ということが「当たり前」となっています。しかし、一般的にお笑いは「笑う」という反応に限定されます。ネタ番組では、観覧の人々はみな笑っているし、その中に泣いたり怒ったりする人はいません。 でも、お笑いを観て「笑う」以外の反応をしたっていいはずです。そうでなければ、「笑えるお笑い=良いお笑い」という評価軸しか存在しないことになります。お笑いの中には「笑えないけど良いお笑い」だって存在します。 本書では、物語論や社会学を媒介にしながら「お笑い」と「文学」の関係を考えていきます。そうすることによって「笑えるか否か」という評価軸とは違う軸が見えてきます。私たちが普段観ているお笑いを違った視点から批評することによって、お笑いが備えている豊かな世界が立ち現れるはずです。(小田垣有輝)
-

【新刊】『北欧フェミニズム入門』枇谷玲子
¥1,200
SOLD OUT
A5/84ページ 翻訳者・枇谷玲子編著の北欧で刊行されたフェミニズムに関連した本をを介するブックガイド。 詳しくはこちら。https://note.com/reikohidani/
-

【新刊】『大喜びした日』
¥1,540
新書判/80p それでもつづく私たちの感情を巡る日々のエッセイ集 人生にはいろんな日々がある。大喜びした日、大泣きした日、大笑いした日。けれどふりかえってみれば、なんであんなに喜んだのか、泣いたのかわからないことだってある。嬉しすぎて泣いたのか、悲しすぎて笑えてきたのか。エモくもなければ、かっこよくもない。それでもつづく、私たちの感情を巡る日々のエッセイ集。 【書き手】 〈エッセイ〉ムカイダー・メイ、佐野裕一、あさのりな、石原空子、後藤花菜、小島あかね、竹田ドッグイヤー、逸見実奈、屋良朝哉、松本慎一、杉山由香、堀江昌史〈短歌〉たろりずむ、謀楽しお、domeki 【概要】 『大喜びした日』は編集とデザインのユニット・三点倒立の制作するリトルプレス。計12名の書き手が「大笑いした日」「大泣きした日」「大喜びした日」の3つのテーマに分かれて、大きく感情が揺さぶられた日のことを書いたエッセイ集です。合わせて3人の歌人が、テーマに沿った短歌を制作しました。 【本文抜粋】 思春期の春菜ちゃんにはそれがつらいこと、そしてそれがわかっていながら母としてどうしたらいいかわからないことを泣きながら話してくれた。何も言えなくて私も泣いた。家の前で立ち尽くしたまま、なにもできずに二人で泣いた。(大笑いした日・石原空子「母の涙」) それらがトドメとなり、これまで堆積したものが一気に崩壊した。帰りの電車に乗り込むと、突然耐えがたい悲しみや怒りが込み上げてきて、まわりに乗客がいるにも関わらず涙が出ては頬をすべり落ちていった。(大泣きした日・小島あかね「パンパンに腫れたまぶたで生きる」) タケノコの香りに小麦の香りが加わり、口の中を満たしてゆく。窓の外を見ると、晴れ渡った空が見えた。遠くの景色は霞でぼやけている。ふと、私がしたかったのはこういう暮らしだったのではないかと思った。採れたての旬の野菜をすぐに調理して食べられるというよろこびは何にも変え難い。(大喜びした日・松本慎一「タケノコを茹でた日」) 【仕様】 新書判(W105mm × H182mm× D5mm)/小口折り製本 80ページ/モノクロ
-

【新刊】『青天』若林正恭
¥1,980
四六判/304p 人にぶつかっていないと、自分が生きているかどうかよくわからなくなる―― 総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち破れた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。 青春の苦みと悦びに満ちた、著者渾身の初小説。
-

【新刊】『図書室の記録』岸波龍(サイン本)
¥1,760
SOLD OUT
四六判/160p 著者の岸波さんとイラスト担当のくれよんカンパニーのwサイン! イラスト:くれよんカンパニー 学校図書室を巡る消えかかる淡雪のようなミステリを──推薦・竹本健治(ミステリ作家) 花鞠学園2年3組の越後智也は図書室のヌシと呼ばれるほどに本が好き。同じく本好きな佐野雅は気さくで明るく、読了した本の感想を誰もが興味をそそるように伝えることができる書評の名人。2人は図書委員として放課後、図書の貸出や棚の整理、おすすめ本を紹介する新聞づくりに取り組むが、本を読んでものおもいにふけっているばかりではいられない。図書の紛失や、文化祭のオバケ屋敷の準備中に起きる怪事件など、学園の至る所で奇妙な事件や謎が湧き上がる。謎があるとつい考えてしまう智也は、いつしか学園の名探偵に……!? 著者の岸波龍は、東京・水道橋の雑居ビルの一室で本屋「機械書房」を営む。大学在学中からミステリ小説の投稿を10年ほど続けるも、作家デビューには至らず小さな書店を開業した。文学フリマ等で知り合った作家の卵や既にデビューした作家たちによる、小部数の自主制作本(ZINE)を店頭に取り揃えると話題となった。本を愛する仲間に囲まれながら再び筆をとり、読書好きの高校生が活躍する学園ミステリが、ここに誕生した……。
-

【新刊】『ミモザ』vol.2
¥2,750
四六判/572p 宮田愛萌と渡辺祐真によるzine「ミモザ 」 この度、「ミモザ vol.2」(#ミモザvol2)を刊行いたします。 今回のテーマは「存在しない街」。東京のどこかにある架空の街「宮平門」をテーマにした、小説、エッセイ、短歌、俳句、研究、地図などを集めました。 存在しないのにもかかわらず妙にリアルなものから、存在感の希薄さ故に自由なものまで、架空の街をたっぷり楽しんでいただけるはずです。 ◯編集・執筆 宮田愛萌 渡辺祐真 ◯執筆(五十音順) 石山蓮華(電線愛好家) 伊藤将人(社会学者) 今和泉隆行(空想地図作家) 岡田悠(文筆家) 小川公代(英文学者) 小津夜景(俳人) 川本直(作家) 佐々木チワワ(ライター) 竹田ドッグイヤー(書店員) 田中佑樹(プロデューサー) 谷頭和希(ライター) たられば(編集者) 俵万智(歌人) つる・るるる(エッセイスト) 松浦やも(歌人)︎ 宮田まゆ(主婦) 柳瀬博一(東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授) ◯イラスト INEMOUSE ◯装丁 成原亜美 ◯編集協力 田畑書店
-

【新刊】『ホームページ』仲西森奈
¥2,970
四六判/572p 「小説」や「随想」という形式は、読みながらそうした形式であることを忘れるときに、本当の姿を現している。 しかしだからこそ、この形あるものを私たちは手に取るのだと思う。書いて、残すのだと思う。生きるのだと。 ――駒田隼也(小説家) 阪神淡路大震災、東日本大震災、能登半島地震。新興宗教、高速バスの床、だれにも見せずに書き続けてきた日記。ゼロ年代、テン年代、そしていま……。震災を経て、疫病を経て、逃れ逃れて個はどこへ。タイ国営鉄道の切符にCoCo壱を見出し、竹としての生をまなざし、墓標/アディクションを背負って記憶を越えて、室生犀星とメダロットを手掛かりに、やがてたどり着くたったひとつの場所――。 「何時何分何秒地球が何周回ったとき?」という煽り文句に、今回は地球の周回数以外、答えることができる。 可視の限界が水平線を作るのではない。地球の形が水平線を作る。現に、星の光は幾光年先のわたしの眼に届く。それを眼は拾う。問題なのは距離ではなく形だ。 ――作家・仲西森奈による、小説、随想、短歌、詩、日記から成る五芒星。 【所収6首抜粋】 雪は隘路に町は記憶に溶け残りラナンキュラスは眼裏を消す General Anesthesia あなたもいつか逝く 教えることはできないけれど コストコを山は許してないかもね 産業道路に雲は被さる やさしくはなれなかった 都会的な怒りを童話みたいに聞いて 駆け抜けろさみしさどもよ海神もわたしも自分以外を飼わず 老いるほど涙が容易に伝うのはまばたきすらもまばゆいからだ 【目次/作品別】 長編小説 どこに行ってもたどり着く場所 あくびもせずに、しずかに話す。 カルシファーのようだ これか? もしもしそれから花と芋 そんぐらいん 詩 山、あるいはピザーラお届け。 川、あるいはあなたとコンビに。 盆と散歩 自己紹介 料理番組になる前 短歌 Still Alive 異性愛 The same flowers bloom in different places. わたしの雲海 拝啓、無料版、 べあーず・はず・かむ! 〜ぼくらの夏の一里塚〜 懐かしさ レアケース 今年 あなたは トカゲ・インタビュー 随想 Coco壱と国鉄 あるいは野良のフェムテック 竹といくつかの(いくつもの)疵 墓守とハルマゲドン(誰が墓穴を掘るのか) 金魚娘のモーフィング あるいは室生犀星とメダロット 日記 2023年12月29日(金) 掌編小説 桜雪 【著者略歴】 仲西森奈(なかにしもりな) 1992年東京都生まれ千葉県育ち。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)文芸表現学科卒業。石川県金沢市在住。著書に歌集『起こさないでください』、私家版歌集『日記』、連作掌編小説シリーズ『そのときどきで思い思いにアンカーを打つ。』『名付けたものどもを追う道筋を歩きながら、』。2025年、散文「真夜中の乾燥わかめ」の英訳原稿(訳者:Heidi Clark)が海外文芸誌『Asymptote』にて掲載される。その他の活動に、音楽グループ□□□(クチロロ)契約社員、朗読バンド筆記体など。メールマガジン「My friend is not dead.」を(ほぼ)毎月配信中。
-

【新刊】『うた子と獅子男』 古谷田奈月(サイン本)
¥1,940
四六判/211ページ 安居酒屋で働く、190センチ超の大男・獅子男。人生を持て余した困窮高校生のうた子。松戸駅前で出会ったふたりの奇妙な連帯。生と暴力の火花が飛び散る、ヤンキー×哲学青春長編!
-

【新刊】『珍獣に合鍵』 早乙女ぐりこ
¥2,035
四六判/192ページ 日々積み重なる小さな絶望に抗う、血みどろの闘いの記録。 「大丈夫なふりをしたことがある、全ての人に読んでほしい」高瀬隼子(作家) 中高一貫男子校で教員として働く鍵岡奏。 女性が極端に少ない職場で、 彼女はまるで「珍獣」のような存在。 無秩序で制御不能な生徒たちに翻弄され、無神経な同僚に削られながら 壊れかけギリギリの日々を過ごしている。 ある日、心の拠り所にしていた先輩教員から発せられた一言から歯車が狂いだす ……。 社会に絶望しながらも、もがき生きる人間のリアルを圧倒的解像度で綴る。
-

【新刊】『neoコーキョー4 「ウイルス」という一文字の漢字をつくう』
¥1,760
A5判/96ページ 身の周りをフィールドワークするハンドブックシリーズ第4巻。 令和に新しい漢字誕生! ――漢字研究者とウイルス学者にインタビューして、一文字の漢字をつくるまで。その全記録。 “この本は、見慣れてしまった文字たちの物質感や手触りを再発見するための本です。読み終えるころには、あなたが文字を見るときのチャンネルがひとつ、あるいはいくつか増えていることでしょう。楽しみにしていてください。”――(本文より) ・カタカナ語は増えるのに漢字が増えないのはなぜか? ・漢字は令和に生きる私たちでもつくってもいいものなのか? ・新しい漢字がひろまるプロセスは? ・ウイルスはどのような共通点を持っている存在なのか? ・「ウイルス」という一文字の漢字をどのようにつくったか? ・文字は絵画なのか? neoコーキョーシリーズ初期の集大成。 文字の可能性に自然とひらかれる一冊。 【目次】 はじめに|令和に新しい漢字誕生! 〈特集1〉ウイルスを表す一文字の漢字をつくろう 対話 漢字研究者・笹原宏之教授と話す 「いま漢字を造ろうとすること――令和を生きる私たちにとっての文字」 インタビュー ウイルス研究者・中屋敷均教授にきく 「わたしたちはウイルスをどうイメージしたらいいですか?」 漢字創作 編集部|ハウ・ドゥー・ユー・メイク・カンジ? 編集部|「ウイルス」の漢字発表/あなたも漢字をつくってみよう 〈特集2〉新しい文字体系をつくる人 アーティスト・村橋貴博さんにきく 「どのように架空の文字を創るのか?――読めなさが秘める力」 美術家・藤田紗衣さんと話す 「文字とは絵画なのか?――線画から文字を創ること」 寄稿 志良堂正文|手書きの文字を散策する――手書きは文字を創ること? 新島汐里|あてはめるとこぼれていく、あてはめないとこぼれていく 辻本達也|果てなき波紋 〈連載〉 マンガ 鮎川奈央子「ここ草っぱらキック」 第4話 いつも居るように 占い&コラム SUGAR「失われた世間を求めて」 第4回 占いセミナーの講師 絵巻物 林丈二「ボクは林丈二の思考です」 第4回 自分の「素」を探っているときのアタマのなか コラージュ hcy|小さなものたちのあいだで
-

【新刊】『旧ソビエト連邦を歩く』星野藍
¥2,420
SOLD OUT
A5判/192ページ 気鋭の女性写真家による、前世紀の夢の跡をめぐる旅 それはまるで近未来のような、あるいはディストピアのような風景 【内容紹介】 共産主義を掲げ理想の国家建設を目指すも、1991年に崩壊を迎えたソビエト連邦。直後の混乱も30年以上経過した現在ではほぼ収束し、立ち入りが難しかった旧ソ連の構成国に興味を持つ人や、失われた国家の痕跡を見るために実際に足を踏み入れる人も増えています。 本書は、旧ソビエト連邦に何度も足を運んできた経験を持つ女性写真家・星野藍による旅行記です。彼女は、旧ソ連の構成国15カ国をすべて旅して写真に収めてきました。さらに、国として認めておらず、入国が極めて困難な“未承認国家”4カ国(ナゴルノ・カラバフ、アブハジア、南オセチア、沿ドニエストル)にも入っています。 フォトグラファー・星野藍がこれまで撮影してきた“巨大建造物”をはじめ、旅を進める中で目にしてきた景色や街中の生活風景、人々との出会いなど、多数の写真と紀行文で構成する一冊です。 【構成】 ■第1章 ロシアほか4カ国 ウクライナ、ロシア、モルドバ、沿ドニエストル、ベラルーシ ■第2章 中央アジア5カ国 ウズベキスタン、キルギス、トルクメニスタン、カザフスタン、タジキスタン ■第3章 バルト三国 リトアニア、ラトビア、エストニア ■第4章 コーカサス3国ほか ジョージア、南オセチア、アブハジア、 アルメニア、アゼルバイジャン、ナゴルノ・カラバフ ■コラム ……etc. 【著者】 星野藍 福島県出身。写真家・グラフィックデザイナー。軍艦島をきっかけに、廃墟を被写体として撮影を始める。旧共産圏や未承認国家に強く惹かれ、近年縦横無尽に巡っている。「APAアワード2024」金丸重嶺賞、「名取洋之助写真賞」奨励賞を受賞。著書に『幽玄廃墟』『旧共産遺産』『未承認国家アブハジア 魂の土地、生きとし生けるものと廃墟』などがある。
-

【新刊】『高校のカフカ、一九五九』スティーヴン・ミルハウザー
¥2,750
四六/200ページ 内気な高校生カフカの思春期の情景を描く表題作、梯子を天高く伸ばす熱に浮かされる町を描く一篇など、職人技が光る不可思議な9篇。
-

【新刊】『オルタナティブ民俗学』島村恭則・畑中章宏
¥1,980
四六判/182P 民俗学がオルタナティブ 民俗学のオルタナティブ 在野のネットワークを重視し、新たな記述法を模索、アカデミアが重視しない周縁や身の回りにこそ目を向けた、「未来の学問」を語り尽くす! 農政官僚であった柳田國男が志した、地方学であり、民間学でもあった民俗学とはどのような学問か。民俗学にとって東北や沖縄は辺境か中心か。民俗学と民藝運動はどのように接近し、どのように袂を分かったのか。民俗学に女性たちはどのように参加し、民俗学は女性たちとどのように関わったのか。そしてこれからの世界的学問である民俗学の行方は。 在野に位置する編集者であり、民俗学者畑中章宏と、21世紀の日本民俗学をリードする島村恭則が、膨大な人名書名を連ねながら語り尽くす民俗学のオルタナティブ性。2024年、誠光社にて開催された前六回の連続対談レクチャーに加筆修正を施し書籍化。ブックデザインは『アウト・オブ・民藝』と同じく、軸原ヨウスケ・中野香によるもの。帯を広げると柳田國男を中心とした民俗学相関図を掲載。 大学に在籍せずとも、年齢性別を問わず身近な関心から始まる学問を知り、学びを再び身近なものに。
-

【新刊】『仮面の告白(初版本復刻版)』三島由紀夫
¥3,960
四六判・箱入り/284ページ 1949(昭和24)年に刊行、日本文学史を揺るがした自伝的書き下ろし小説の初版本を限定復刻。発表当時の「『假面の告白』ノート」「作者の言葉」も収録する。生誕100年記念出版。 本文のみならず、カバー、表紙、扉、帯、そして、三島氏自身による「「假面の告白」ノート」を含む、当時の「書き下ろし長篇小説」シリーズの月報までを再現。 三島氏が広告宣伝のために書いたという「作者の言葉」、三島氏の死去の直後に書かれた坂本一亀氏による回想エッセイ「『仮面の告白』のころ」を含む小冊子も封入。 ※部数限定復刻につき、重版はいたしません。 平野啓一郎氏推薦! 「私は永遠に私でしかない。──絢爛たるペダントリーと華麗な技巧、瑞々しくも官能的な詩情に酔わされながら、読者が最後に向き合うのは、素顔の三島の孤独な自己認識だ。この告白は悲痛だが美しく、そして確かに、天才の開花だ。」
-

【新刊】『これがそうなのか』永井玲衣
¥1,980
四六/320ページ ことばと出会い、ことばと育ち、ことばを疑い、ことばを信じた。 『水中の哲学者たち』で一躍話題となった著者は、 ことばに支えられながら、世界を見つめ続ける――。 過去から現在までの著者自身を縦断し、 読者とともにこの社会を考える珠玉のエッセイ集。 【第一部 問いはかくれている】 日々生まれる「新語」。 新語は、現代社会が必要とするから生まれるはず――。 けれど、なぜ私たちはそのことばを作ることにしたのだろう? 新語の裏に潜む問いを探り出し、私たちの「いま」を再考する12篇。
-

【新刊】『到来する女たち 石牟礼道子・中村きい子・森崎和江の思想文学』渡邊英理
¥2,640
SOLD OUT
四六判/400ページ じんぶん大賞2026 18位 不揃いなままで「わたし」が「わたしたち」になる──。 1958年に創刊された雑誌『サークル村』に集った石牟礼道子、中村きい子、森崎和江が聞書きなどの手法で切り拓いた新たな地平を、『中上健次論』が話題を呼んだ著者が「思想文学」の視点で読み解く。 「『サークル村』を通して、彼女たちが手に入れたのは、儚い「わたし」(たち)の小さな「声」を顕すための言葉であったにちがいない。この新しい集団の言葉は、異質なものと接触し遭遇することで自らを鍛え、異質な他者とともに葛藤を抱えながらも不透明な現実を生きようとする言葉でなければならなかった。支配や権力、垂直的な位階制や序列的な差別から自由で、不揃いなままで水平的に「わたし」は「わたしたち」になる。 三人の女たちは、そのような「わたし」と「わたしたち」を創造/想像し、「わたし」と「わたしたち」とを表現しうる言葉を発明しようとしたのではなかったか」(渡邊英理) ・石牟礼道子(1927-2018)【熊本】……熊本県天草生まれ。詩人、作家。生後すぐに水俣へ。著書に『苦海浄土』『椿の海の記』『西南役伝説』ほか。 ・中村きい子(1928-1996)【鹿児島】……鹿児島生まれ。小説家、作家。母をモデルにした小説『女と刀』は大きな話題を呼び、木下恵介監督によりドラマ化もされた。 ・森崎和江(1927-2022)【福岡】……朝鮮大邱生まれ。詩人、作家。17歳で単身九州へ渡り、58年筑豊炭鉱近郊の中間に転居、谷川雁らと『サークル村』創刊。著書に『まっくら』『慶州は母の呼び声』『非所有の所有』など。
-

【新刊】『ケアと編集』白石正明
¥1,056
新書判/254p じんぶん大賞2026 13位! もはやこれまでと諦めてうなだれたとき、足元にまったく違うモノサシが落ちている。与えられた問いの外に出てみれば、あらふしぎ、あなたの弱さは克服すべきものじゃなく、存在の「傾き」として不意に輝きだす──。〈ケアをひらく〉の名編集者がみんなの弱さをグッと後押し。自分を変えずに生きやすくなる逆説の自他啓発書。 内容説明 もはやこれまでと諦めてうなだれたとき、足元にまったく違うモノサシが落ちている。与えられた問いの外に出てみれば、あらふしぎ、あなたの弱さは克服すべきものじゃなく、存在の「傾き」として不意に輝きだす―。〈ケアをひらく〉の名編集者が一人ひとりの弱さをグッと後押し。自分を変えずに生きやすくなる逆説の自他啓発書。 目次 1 いかにして編集の先生に出会ったか 2 ズレて離れて外へ 3 ケアは現在に奉仕する 4 ケアが発見する 5 「受け」の豊かさに向けて 6 弱い編集―ケアの本ができるまで
-

【新刊】水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』
¥1,760
SOLD OUT
四六判/240ページ じんぶん大賞2026 2位! 会話で相手に返事をするまでの間に、頭の中で何が起きている? 「ゆる言語学ラジオ」の著者が、日常の奇跡を解き明かす、大興奮の一冊。 言葉で悩んでしまうあなたに。
-

【新刊】『35歳からの反抗期入門』碇雪恵(サイン本)
¥1,210
SOLD OUT
B6版/128頁/サイン本 目次 はじめに べつに自由じゃない リクナビペアーズマイナビティンダー しあわせな村人だったときのこと やさしさもSEXも両方あっていい ーー映画『この星は、私の星じゃない』をみて STOP神格化(そして健康に目を向ける) この世のすべての人のためには泣けない 東京の価値観 善き行動の一部始終 俺の値段は俺が決める トイレその後に(男性ver.) 産まれたらもう無力ではないーー映画『ハッピーアワー』をみて 花束には根がない 遅れてきたレイジアゲインスト花束 いまさらですけど花束雑感ーー映画『花束みたいな恋をした』をみて 夢のよう、っていうか実際夢だった 愛に気がつくためのケアをーー映画『すばらしき世界』をみて 派遣とフリーランス兼業の現状と悩み 打算のない関係だけが美しいのかーー映画『愛について語るときにイケダの語ること』をみて 雑な言葉に抵抗したい STOP神格化2022(というかBreak the ファンタジー)
-

【新刊】『斜め論―空間の病理学』松本卓也
¥2,420
SOLD OUT
四六/320ページ ケアは、どうひらかれたのか? 「生き延び」と「当事者」の時代へと至る「心」の議論の変遷を跡付ける。 垂直から水平、そして斜めへ。時代を画する、著者の新たな代表作! === 「現代は、ケア論の隆盛に代表されるように、人と人との水平的なつながりの重要性をいうことがスタンダードになった時代である。けれども、単に水平的であればよいわけではない。 水平方向は、人々を水平(よこならび)にしてしまう平準化を導いてしまうからだ。けれども、水平方向には日常を捉え直し、そこからちょっとした垂直方向の突出を可能にする契機もまた伏在している。ゆえに、垂直方向の特権化を批判しつつ、しかし現代的な水平方向の重視に完全に乗るわけでもなく、「斜め」を目指すこと……。 そのような弁証法的な思考を、精神科臨床、心理臨床、当事者研究、制度論的精神療法、ハイデガー、オープンダイアローグ、依存症といったテーマに即して展開したのが本書のすべてである。」 (あとがきより抜粋)
-

【新刊】『お金信仰さようなら』ヤマザキOKコンピュータ
¥1,980
四六/224ページ 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 労働と成長ばかり求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 しかし、一部の間ではもう新たな時代が始まっている。 ーーーーー ・どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? ・売れないものには価値がないのか? ・経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 金融界のみならず、国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培った独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 投資家でパンクスの著者による最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日』惣田大海水
¥1,430
A6判/232ページ 【内容】 わたしはきっと父親と同じように、いつか首を吊って死ぬだろうを思いこんで、でも残った家族に、もう一度自殺した人間の骨を見せるわけにいかないと必死だった生活を抜け、いつの間にか死ななくてもよい日々がそこにあった。しかし、だからといって、その後は楽しく幸せに生きていきました、めでたしめでたし、とはならなかった。ある日、父親が首を吊る原因となった土地を、売ってほしいという手紙が届く。ヤングケアラーがヤングでなくなった後、どう生きれば穏やかな日々を手に入れられるか、死にたかった人が死にたくなくなった後、どう生きれば人生を楽しめるのか、を模索した日日の日記。(2023年7月から2024年4月までの日記を収録)
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日2』惣田大海水
¥1,320
A6判/163ページ 【内容】 私が求めているのは、死にたい気持ちのその先にもきっとあるであろう、穏やかな生活である。穏やかな生活を手に入れるためには、きっと今のままでは駄目で、私は自分の土台を固める必要がある。しかし、仕事の環境が変化し、どうにもこうにも慌ただしく、自分と向き合うどころではない。カウンセリングに行くべきか、行かざるべきか三万光年ほど検討し、ついに心理士の元へ行く、そんな日々の記録。(2024月5月から2024年10月までの日記を収録)
-

【新刊】『死ななくてよくなった後の日日3』惣田大海水
¥1,650
A6判/299ページ 【内容】 死ななくてよくなったからこそ、やっと通うことが出来るようになったカウンセリング。父親とは、母親とは、自分とは、いったいどういう人間なのか。体内に残存する子供のころの家庭環境というブラックボックスを、心理士との対話の中で再度考え直していく「カウンセリング日記」を含む日日の記録。(2024年11月から2025年7月までの日記を収録)