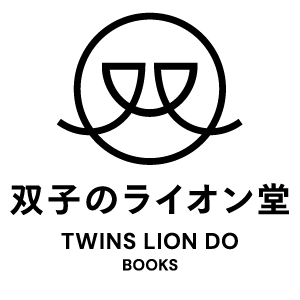-

【新刊】『大喜びした日』
¥1,540
新書判/80p それでもつづく私たちの感情を巡る日々のエッセイ集 人生にはいろんな日々がある。大喜びした日、大泣きした日、大笑いした日。けれどふりかえってみれば、なんであんなに喜んだのか、泣いたのかわからないことだってある。嬉しすぎて泣いたのか、悲しすぎて笑えてきたのか。エモくもなければ、かっこよくもない。それでもつづく、私たちの感情を巡る日々のエッセイ集。 【書き手】 〈エッセイ〉ムカイダー・メイ、佐野裕一、あさのりな、石原空子、後藤花菜、小島あかね、竹田ドッグイヤー、逸見実奈、屋良朝哉、松本慎一、杉山由香、堀江昌史〈短歌〉たろりずむ、謀楽しお、domeki 【概要】 『大喜びした日』は編集とデザインのユニット・三点倒立の制作するリトルプレス。計12名の書き手が「大笑いした日」「大泣きした日」「大喜びした日」の3つのテーマに分かれて、大きく感情が揺さぶられた日のことを書いたエッセイ集です。合わせて3人の歌人が、テーマに沿った短歌を制作しました。 【本文抜粋】 思春期の春菜ちゃんにはそれがつらいこと、そしてそれがわかっていながら母としてどうしたらいいかわからないことを泣きながら話してくれた。何も言えなくて私も泣いた。家の前で立ち尽くしたまま、なにもできずに二人で泣いた。(大笑いした日・石原空子「母の涙」) それらがトドメとなり、これまで堆積したものが一気に崩壊した。帰りの電車に乗り込むと、突然耐えがたい悲しみや怒りが込み上げてきて、まわりに乗客がいるにも関わらず涙が出ては頬をすべり落ちていった。(大泣きした日・小島あかね「パンパンに腫れたまぶたで生きる」) タケノコの香りに小麦の香りが加わり、口の中を満たしてゆく。窓の外を見ると、晴れ渡った空が見えた。遠くの景色は霞でぼやけている。ふと、私がしたかったのはこういう暮らしだったのではないかと思った。採れたての旬の野菜をすぐに調理して食べられるというよろこびは何にも変え難い。(大喜びした日・松本慎一「タケノコを茹でた日」) 【仕様】 新書判(W105mm × H182mm× D5mm)/小口折り製本 80ページ/モノクロ
-

【新刊】『珍獣に合鍵』 早乙女ぐりこ
¥2,035
四六判/192ページ 日々積み重なる小さな絶望に抗う、血みどろの闘いの記録。 「大丈夫なふりをしたことがある、全ての人に読んでほしい」高瀬隼子(作家) 中高一貫男子校で教員として働く鍵岡奏。 女性が極端に少ない職場で、 彼女はまるで「珍獣」のような存在。 無秩序で制御不能な生徒たちに翻弄され、無神経な同僚に削られながら 壊れかけギリギリの日々を過ごしている。 ある日、心の拠り所にしていた先輩教員から発せられた一言から歯車が狂いだす ……。 社会に絶望しながらも、もがき生きる人間のリアルを圧倒的解像度で綴る。
-

【新刊】『neoコーキョー4 「ウイルス」という一文字の漢字をつくう』
¥1,760
A5判/96ページ 身の周りをフィールドワークするハンドブックシリーズ第4巻。 令和に新しい漢字誕生! ――漢字研究者とウイルス学者にインタビューして、一文字の漢字をつくるまで。その全記録。 “この本は、見慣れてしまった文字たちの物質感や手触りを再発見するための本です。読み終えるころには、あなたが文字を見るときのチャンネルがひとつ、あるいはいくつか増えていることでしょう。楽しみにしていてください。”――(本文より) ・カタカナ語は増えるのに漢字が増えないのはなぜか? ・漢字は令和に生きる私たちでもつくってもいいものなのか? ・新しい漢字がひろまるプロセスは? ・ウイルスはどのような共通点を持っている存在なのか? ・「ウイルス」という一文字の漢字をどのようにつくったか? ・文字は絵画なのか? neoコーキョーシリーズ初期の集大成。 文字の可能性に自然とひらかれる一冊。 【目次】 はじめに|令和に新しい漢字誕生! 〈特集1〉ウイルスを表す一文字の漢字をつくろう 対話 漢字研究者・笹原宏之教授と話す 「いま漢字を造ろうとすること――令和を生きる私たちにとっての文字」 インタビュー ウイルス研究者・中屋敷均教授にきく 「わたしたちはウイルスをどうイメージしたらいいですか?」 漢字創作 編集部|ハウ・ドゥー・ユー・メイク・カンジ? 編集部|「ウイルス」の漢字発表/あなたも漢字をつくってみよう 〈特集2〉新しい文字体系をつくる人 アーティスト・村橋貴博さんにきく 「どのように架空の文字を創るのか?――読めなさが秘める力」 美術家・藤田紗衣さんと話す 「文字とは絵画なのか?――線画から文字を創ること」 寄稿 志良堂正文|手書きの文字を散策する――手書きは文字を創ること? 新島汐里|あてはめるとこぼれていく、あてはめないとこぼれていく 辻本達也|果てなき波紋 〈連載〉 マンガ 鮎川奈央子「ここ草っぱらキック」 第4話 いつも居るように 占い&コラム SUGAR「失われた世間を求めて」 第4回 占いセミナーの講師 絵巻物 林丈二「ボクは林丈二の思考です」 第4回 自分の「素」を探っているときのアタマのなか コラージュ hcy|小さなものたちのあいだで
-

【新刊】『私は私に私が日記をつけていることを秘密にしている』古賀及子
¥1,870
四六判/p280ページ/ 人気の日記エッセイ作家が明かす、 みんなに読まれる日記の秘密。 「文学フリマ」が毎回入場者数を更新し、日記本がブームになり、自分でも日記を書きたい・noteで公開したい・ZINEにまとめたい……という人が増えているなか、日記エッセイストの第一人者が、日記を書く際の独自の経験知と秘密を大公開。その実践例としての日記もあわせて収録。日記を読みたい人にも、書きたい人にも、いますぐ役立つアイデアと実例が満載の、これからの日記作家に捧ぐメタ日記エッセイ。
-

【新刊】『つくって食べる日々の話』
¥2,420
四六判・ソフトカバー/160ページ これ絶対、おいしい本! 食の文芸、最前線の一冊がついに発売 人気小説家や食エッセイの第一人者、ノンフィクションライターなど様々な分野で活躍する16名の表現者による「料理と生活」をテーマにした書き下ろしエッセイ集。 執筆 平松洋子/円城塔/スズキナオ/春日武彦/大平一枝/白央篤司/牧野伊三夫/阿古真理/絶対に終電を逃さない女/辻本力/オカヤイヅミ/島崎森哉/宮崎智之/松永良平/ツレヅレハナコ/滝口悠生
-

【新刊】『シティガール未満』絶対に終電を逃さない女
¥1,650
四六/192ページ 早くこんなところを抜け出して、 誰も私を知らない場所に行きたい。 そう思って18歳で上京した。 魔法みたいに東京がすべてを解決してくれる気がしていた。 高層ビルも人混みもいつしか日常風景となり、 待ち合わせ場所が東京の固有名詞というだけで光って見えた日々も過ぎ去った。 思い描いていたよりは輝けていない自分が、ここにいる。 東京には東京の残酷さがあって、 けれど、東京には東京の優しさがあることも知った。 平成の終わりから令和、そしてコロナ禍の東京。 その様々な街で、起こったこと、考えたこと、思い出したことが、 都心の路線図のごとく複雑に絡み合っていく。 これはそんな私の個人的な記録だが、 きっと見知らぬあなたの記憶とも、どこかで交差するだろう。 「言葉にしてくれて、発信してくれて、ありがとう」 「泣いちゃうけど、何度も聴きたくなる歌みたい」 「上滑ったイメージでなく、地に足のついた東京」 刊行前から共感の声続々、 「絶対に終電を逃さない女」待望のデビューエッセイ!
-

【新刊】『本と偶然』キム・チョヨプ
¥1,980
四六判/280ページ 世界が注目する作家キム・チョヨプ初のエッセイ、待望の邦訳! 「書きたい」わたしを見つける読書の旅 「わたしをとびきり奇妙で輝かしい世界へといざなってくれた。そんな偶然の瞬間を、及ばずながらここに記していこうと思う。」 本が連れていってくれた偶然の瞬間、 「作家キム・チョヨプ」になるまで 「なぜ物語を書くのか。その根底にある思いを探るとき、わたしは街灯に沿って家路をたどっていた十七歳の夜を思い出す。」 キム・チョヨプ初のエッセイ『本と偶然』は、読書の道のりを振り返りながら、そこに「書きたい」自分を見つける探検の記録だ。 SFというジャンルについて説明を求められ答えを探すために本を読み、専門外のノンフィクションを書くために本を読む。そして小説を書くために本を読む。 「物語と恋に落ちるときのあの気分、それを再現したいという願いが、わたしの「書きたい」という気持ちのまんなかにある。」 読むことがどんなふうに書くことにつながるのか、出会った本が書き手としてのわたしをどんなふうに変えたのか、「読む人の読書から、書く人の読書へ」と変化するなかで「偶然本に出会う喜び」をありのままに綴ったエッセイ集。 冷たくも美しい世界の上に キム・チョヨプが描くユートピア 「ひとりの人間の心を、内面世界を揺さぶり、消すことのできない痕跡を残して去っていく物語」。「わたしもいつかああいうものをつくりたい」という純粋な気持ちが、今日、「作家キム・チョヨプ」という世界の出発点となった。 日韓大ベストセラー『わたしたちが光の速さで進めないなら』、『地球の果ての温室で』、『この世界からは出ていくけれど』、『派遣者たち』、『惑星語書店』まで、リアルな創作秘話も垣間見られる貴重な一冊。 * * * いまでも自分は引き出しのない作家だと思うけれど、以前ほど不安には思わない。わたしのなかで文章を書くことは、作家の内にあるものを引っ張り出すというより、自分の外にある材料を集めて配合し、積み上げていく、料理や建築に近いものに感じる。学び、探検すること、なにかを広く深く掘り下げること、世界を拡張すること。これらすべてが、わたしにとっては執筆の一環と言える。(「詰めこんでいればいつかは」より) 【目次】 日本語版への序文 はじめに 第1章 世界を拡張する 第2章 読むことから書くことへ 第3章 本のある日常 謝辞 キム・チョヨプの偶然出会った本たち
-

【新刊】『緑をみる人』村田あやこ
¥2,640
四六変形/384ページ 名もなき緑を日々見守る、世界の“隙間植物愛好家”たち アスファルトのひび割れやマンホール蓋のふち、側溝の奥底、室外機の下……。 整備された都市空間の隙間で、人知れず芽吹き繁茂する植物たち。 「路上園芸鑑賞家」として発信を続ける著者は、街の隙間に生きる緑に自身の秘めた「野性」を重ね、その制御不能さに心惹かれ続けている。 本書では、著者が世界13カ国18人の“隙間植物愛好家”にコンタクトを取り、約2年にわたって取材を重ねた。 水抜き穴協会・モリタケンイチは、水抜き穴という小さな穴に広がる生態系に「小宇宙」をみる。 イタリア在住のパオロ・カスパーニは、路上の植物に「勇敢さ」と「しぶとさ」をみる。 スウェーデンの元テレビマン、スタファン・フィッシャーは植物が生きる隙間に「ミニチュアの世界」をみる。 オランダの芸術家・アン・ゲーネは植物の「不完全さ」に「完璧」をみる。 メキシコのデザイナー・アストリッド・ストゥーペンと文化人類学者のステファニー・スアレスは、都市の植物から「パラレルな時間の流れ」を垣間みる。 日本、フランス、トルコ、メキシコ、韓国、台湾、イタリア、スウェーデン、ブラジル、シンガポール、アメリカ、オランダ、ニュージーランド。ぜんぶで19人の緑をみる人たち。それぞれのストーリーと総数800枚もの写真をとおしてみえてくるのは、日常にひそむ地球の「野生」だ。 (巻末に英訳掲載) <目次> PART1:著者が15年ほど前から撮りためてきた、日本の路上でみつけた隙間植物の写真395枚を掲載。 ●はみ出す緑に自身の「野性」を重ねる/村田あやこ(botaworks) PART2:著者がSNSで知り合った「中の人」など、世界の隙間植物愛好家18人にコンタクトをとりインタビュー。それぞれが撮りためた写真も紹介する。 ●植物はどんな場所でも生きるすべを見つける/フランソワ・デコベック(Plants of Babylon) ●小さな穴の中に広がる小宇宙/モリタ ケンイチ(水抜き穴協会) ●定形の空間に、不定形のものが生まれる楽しさ/まつ(東京自由植物) ●人間も、足元の植物たちも、自然の一部/エレクトリックアイ(parts.of.nature) ●都市の植物は、自然と人工物とを融合させる存在/ケレム・オザン・バイラクター(Sokak Otları) ●都市の植物から垣間見える、パラレルな時間の流れ/アストリッド・ストゥーペン&ステファニー・スアレス(Planta De Asfalto) ●都市の小さな亀裂から、命が始まる/イ・ユンジュ(botanicity) ●植物は、都市にぬくもりと活気をもたらす/トム・ルーク(Treehouses of Taiwan) ●路上の植物たちは勇敢でしぶとい/パオロ・カスパーニ(being_weeds) ●植物が生きる小さな隙間は、まるでミニチュアの世界/スタファン・フィッシャー(Trottoaser) ●どんな場所でも、植物はただそこに存在する/エリサ・ヌネス(arvorexiste) ●人間と同じように、都市には多様な植物が生きている/サラ・セオ(Urban Lithophytes) ●人間界のルールの隙間に、植物のエネルギーが噴出する/山田泰之(路上盆栽) ●都市に自生する植物は、生態系にとって重要な存在/デビッド・サイター(Spontaneous Urban Plants) ●不完全さこそ植物の完璧な姿/アン・ゲーネ(Book of Plants) ●道端の草たちが、街への愛着を取り戻してくれる/重本晋平(まちくさ) ●困難な状況でも生きる植物たちの美しさ/ダニエラ・フエンザリダ(Aesthetics Of The Resistance) PART3:PART2に登場する18人+著者が撮影した写真215枚を、シチュエーションごとに整理して掲載。 あとがき
-

【新刊】『継続するコツ』坂口恭平
¥1,760
四六判・並製/240ページ みなさん、継続することは得意ですか? 得意な人はこの本は手に取っていないと思いますから、おそらくちょっと苦手ですよね。 一方、僕は継続することがむちゃくちゃ得意です。なんか自慢みたいで申し訳ありません。 でもその代わりといってはなんですが、別に質が良いわけではないと思います。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 執筆、絵描き、作詞・作曲、「いのっちの電話」…… どれも20年以上つづけてきた、スランプ知らずの継続マニア・坂口恭平さんが見つけた、 「やりたいこと」をつづけるコツが1冊に! 僕も挑戦している最中です。 最中であればいいんです。継続中ってことですから _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 多くの人は、何かをやろうとして、手をつけはじめて、 無事に完成することができたとしても、 それが売れないだとか、人から評価されないだとか、そういった不遇を味わい、 自信を失い、徒労感ばかりを感じるようになり、いずれはやめてしまうようです。 僕はいつも、もったいない!と思ってしまいます。 だって、作っているときのほうが楽しいですもん。 つまり、何かを継続しているときのほうが、楽しいんです。 この馬鹿みたいに単純なことに、僕は気づいたんです。
-

【新刊】『利尻島から流れ流れて本屋になった』工藤志昇(サイン本)
¥1,870
SOLD OUT
四六判/168ページ 書店は、故郷だ――。ゴールの見えない多忙で多様な仕事と、ふとした拍子に思い起こされる大切な記憶――。絶景絶品の島・利尻島で生まれ育った三省堂書店札幌店係長が綴った最北の風味豊かなエッセイ集。〈解説〉北大路公子
-

【新刊】『プルーストを読む生活』柿内正午(刊行:HAB)
¥3,245
タイトル『プルーストを読む生活』 著:柿内正午 装画:西淑 装丁・組版 中村圭佑+平本晴香(ampersands) 出版:エイチアンドエスカンパニー(H.A.B) 本体:2950円+税 判型:四六版(127☓188☓45mm) デザイン:並製・フォローバック製本 ISBN:9784990759643 Cコード:0095 〈概要〉 プルーストを読んでどうなるというのですか? プルーストを読んでいると楽しいです。 そんだけ! うっかり神保町で『失われた時を求めて』ちくま文庫版全10巻セットを買ってしまった。せっかく買ったので毎日読んでいる。せっかく読んでいるので、読みながら毎日ものを書くことにした。読書と、生活と、脱線の記録。いつもリュックにプルースト。毎日読んで、毎日書く。それだけを決めて、ほとんどプルーストではない本ばかり引用し、役にも立たなければ、読んだ端から忘れていくので物知りにもならない、ただ嬉しさだけがある読書日記。 解説:友田とん(代わりに読む人) <柿内正午> 1991年生まれ。会社員。 休日はお芝居をつくったり、価値のないものを愛でるユニット「零貨店アカミミ」としての細々とした活動を企てています。 noteにて、読書日記を毎日更新中。( https://note.mu/amokgoodish ) 夫婦で「家」づくりの試行錯誤の記録も書いてます。 (版元サイトより引用)
-

【新刊】『傷病エッセイアンソロジー 絶不調にもほどがある!』
¥1,540
165mm × 110mm・並製/136ページ 生きていれば、予期せぬ苦難に見舞われることがある。 心も体も、いつも健康でいられるわけじゃない。 孤独や不安、思わぬ心境の変化や、誰にも言えない気持ち―― 病気や怪我に直面したときの心模様のリアルを、15名の書き手が綴った。 生きることの痛みと希望を映し出す、傷病エッセイアンソロジー! 【目次】 上坂あゆ美 起きてしまったことはどうしようもないから 金川晋吾 繊細な私の胃 尾崎大輔 明るくなっただけだった 堀道広 鎖骨の思い出(漫画) 鳥井雄人 血、恐い こだま せっかく病気になったので 星野文月 骨折と婚約 武田砂鉄 サボってるって思ってるみたいよ 碇雪恵 1997年8月11日 中村一般 歯医者ビビリが外科手術で親知らずを抜いたレポ(漫画) 三田三郎 人間的な「悪意」の気配 小原晩 ぬう 玉置周啓 玉置 いとうひでみ 心のゆくえ(漫画) 飯村大樹 おいしそうな怪我 イラスト・題字 堀道広 装丁 飯村大樹 企画・編集 尾崎大輔 星野文月 発行 BREWBOOKS 印刷・製本 モリモト印刷株式会社
-

【新刊】『随風02』(サイン本/誰のサインが届くかはランダム)
¥1,980
A5判/162ページ/サイン本(誰のサインが届くかはランダムです) 随筆復興を推進する文芸誌『随風』 創刊号は刊行後たちまち重版となり話題をさらった。 今号は執筆陣にpha、古賀及子、花田菜々子、絶対に終電を逃さない女、佐々木敦らを迎える。 【執筆者一覧】 宮崎智之、アサノタカオ、磯上竜也、今井楓、オルタナ旧市街、清繭子、古賀及子、早乙女ぐりこ、杉森仁香、絶対に終電を逃さない女、西川タイジ、花田菜々子、pha、吉田棒一、わかしょ文庫 批評 柿内正午、佐々木敦、和氣正幸 インタビュー 村井光男(ナナロク社) 編集後記 吉川浩満
-

【新刊】『neoコーキョー1 勝手にカウント調査をはじめよう: 14日間路上に座ってひとの数をかぞえつづけたらどうなったか? 』
¥1,694
A5判/92ページ 身の周りをフィールドワークするハンドブックシリーズ第一弾。 日々、なにげなく通っている 歩道 や 街 の見えかたが変わる本。 14日間路上に座って、ひとの数をかぞえた記録。 「心細かった。いまからおれは池袋の路上で人の数をかぞえようとしている。街は日曜なりにそこそこ賑わっている。すわれそうな場所を探し歩くけれど、どこにすわっても白い目で見られる気がした」――(本文より) 歩道のすみっこに座る。前をひとが通る。親指でボタンを押す。カウンターがしめす数字が「000」から「001」になる。また、ひとが通る。親指を動かす――「002」になる。これを14日間続けながら、見えたもの、考えたこと、調べたことを記録した調査誌です。 ・どうして歩道には自分しか勝手に座っているひとがいないのだろう? ・コロナウィルス感染症による緊急事態宣言下の街路はどんなふうだったか? ・人を「数」として捉えるとは、どういうことなのか? ・かぞえるのに飽きてきたら、人は何をかぞえるようになるのか? ・この道はいつからここにあるのか? ・街ゆく人からどんなふうに見られ、どんな言葉をかけられたか? かぞえる対象は、通行人の数から、性別、姿勢、持ち物などと変わっていき、最後は? 連載陣による「マンガ」、「占い」、「フィクション」あり! 路上観察学の仕掛け人 林丈二による「絵巻物」あり! シリーズ創刊一冊目だからこそ、全力で冒険した一冊。 【目次】 はじめに:neoコーキョーシリーズと焼き鳥 勝手にカウント調査2021(04.25-05.03) #1 池袋の路上 #2 公共空間=チューブ #3 接近 #4 1059人 #5 カバンの持ちかたは六種類しかない #6 雨 #7 ひとびとを六つにふりわけてボタンを押す マンガ 鮎川奈央子「ここ草っぱらキック」 第1話 なんだ!? 勝手にカウント調査2023(10.22-10.30) #8 起用著名人 #9 装い #10 (ノン)フィクション #11 声 #12 スマホを手に持って歩く人の数 #13 ダンス #14 発見の大小 占い&コラム SUGAR「失われた世間を求めて」 第1回 世間師 世間をひろげる十二星座ラッキーモチーフ――脱社畜する島耕作編 絵巻物 林丈二「ボクは林丈二の思考です」 第1回 映画『シェーン』を観ようとし…
-

【新刊】『neoコーキョー2 アプリの地理学』
¥1,694
A5判/96ページ 身の周りをフィールドワークするハンドブックシリーズ第2巻。 あなたはホーム画面にどんなふうにアプリを配置していますか? アプリの配置のしかたについて10人に訊いた対話の記録。 親しいひとがスマホを使っているところを目にすることはよくある。 でもホーム画面を見たことはない。 こんなに近くにあるものなのに見たことがなかったことにハッとして、作った本です。 “今回、最初に話をしたのはSさんだったのですが、そのホーム画面に出会った途端、ガツンと殴られたような衝撃がありました。その後もつぎつぎぼくは『自分の考え方は唯一のものではない』と感じさせられることになります”――(本文より) ・アプリを「物欲」「食欲」「雑多」のフォルダで分けるようになった理由は? ・ガラケーを使っていたころの意識でスマホのホーム画面を見ている? ・間違って押すのがいやだから市松模様にアプリを配置している? ・目的のアプリがすぐに見つからないように色で分けている? ・え、アプリを整理するってなに?整理するもんなの? Spot.1にひきつづき、多彩な連載陣による占い・漫画・絵巻物あり! もっとも身近な場所からダイバーシティを見出せるようになる本 【目次】 はじめに:ミクロな差異をひろう アプリの地理学 Noontide #1 ポケモンを乱獲するWEBディレクター #2 哲学からBTSまで語れる噺家占星術師 #3 建築科出身照明デザイナー #4 もうすぐ子供が生まれる製薬会社社員 #5 ラップするイラストレーター マンガ 鮎川奈央子「ここ草っぱらキック」 第2話 僕はこう 占い&コラム SUGAR「失われた世間を求めて」 第2回 騒動師 世間をひろげる十二星座ラッキーモチーフ――騒動準備する日雇労働者編 絵巻物 林丈二「ボクは林丈二の思考です」 第2回 映画『シェーン』の悪役ジャック・パランスからひきだされた思考 アプリの地理学 Sunset #6 朝から晩まで下町の定食屋で働く実直店長 #7 気分転換に鉄道時刻表を読むテレビマン #8 クリエイターのハブとなる美容院 #9 組織の境界をまたぐデザイナー #10 暗渠のヘドロに飛び込んだ美術家
-

【新刊】『neoコーキョー3 自宅の見えない力: あなたの自宅は、実際のところ、なにをしているのか? 』
¥1,694
A5判/96ページ 身の周りをフィールドワークするハンドブックシリーズ第3巻。 自宅がなにをしているか、具体的に考えたことはありますか? ――日々、あたりまえに過ごす「自宅」の見え方が変わる本。 “この本の制作を通して、ぼくは自宅のことを共に歩んでいく船のように感じるようになりました。漁師が信頼を込めて船を扱うように。SF映画の主人公が宇宙船に名をつけ、声をかけるように。”――(本文より) ・屋根はどのようにして雨水をはじき続けているのか? ・わたしたち水道ネイティブは、なにを失っているのか? ・自宅のない生活がはじまると「街」が自宅になる? ・自宅の内壁と外壁のあいだにはどのような空間がひろがっているのか? ・「トイレの水」は「キッチンの水」より汚いか? 多彩な連載陣による占い・漫画・絵巻物あり! 「自宅」にはわざわざ言葉にされない力がある。それはどのようなものか? 10本の記事で編んだドキュメント。 【目次】 はじめに|キッチンのピストル 対話 防水職人 杉田萌さんと話す 「屋根が受け止めているもの 屋根をメンテナンスする仕事」 寄稿 佐々木ののか|家がなくなり、街が家になった インタビュー 建築家 山田伸彦さんに聞く 「建築家になる前と後で、住宅の見方はどう変わりましたか?」 エッセイ 編集部|インフラがあらわれた! #1 二重の家 #2 水道ネイティブな私たち #3 未明の屋根 #4 ガスが自動で止まる世界で #5 家から離れていくこと 対話 美容室dollsと語る「美容室はインフラか?」 寄稿 新島汐里|靴を履く動物 創作 辻本達也|蛇の口先 コラージュ hcy|いし、へび、まくら マンガ 鮎川奈央子「ここ草っぱらキック」 第3話 猿に憧れている。かっこいいのだ。 占い&コラム SUGAR「失われた世間を求めて」 第3回 ろくでなし 絵巻物 林丈二「ボクは林丈二の思考です」 第3回 ボタモチがどこから落ちてくるのか探っているときのアタマのなか Booklink
-

【新刊】『ねこによろしく 赤』池谷和浩
¥1,320
B6判/ 124ページ/サイン本 著者の近況エッセイと『フルトラッキング・プリンセサイザ』『四季と機器』に架橋する小説がクロスして溶け込んでいく新しい散文。 猫は白い方のがゆっくりご飯を食べ、赤い方のはさっさと食べる。猫と暮らす日々の中で著者は新しい小説の創作に取り組んでいます。 小説で、うつヰは、ある家にたくさん保管された服を個人売買のサイトに登録して売っていくバイトをしています。 現実と小説の世界は、果たして本当に別のものなのでしょうか。 本作品の前編は『ねこによろしく 白 ウェアラブル・プロシージャ』です。 装画 にしさかきみこ
-

【新刊】『ねこによろしく 白』池谷和浩
¥1,320
B6判/112ページ/サイン本 著者の近況エッセイと『フルトラッキング・プリンセサイザ』『四季と機器』に架橋する小説がクロスして溶け込んでいく新しい散文。 猫は白い方のがゆっくりご飯を食べ、赤い方のはさっさと食べる。猫と暮らす日々の中で著者は新しい小説の創作に取り組んでいます。 小説で、うつヰは、ある家にたくさん保管された服を個人売買のサイトに登録して売っていくバイトをしています。 現実と小説の世界は、果たして本当に別のものなのでしょうか。 続刊は『ねこによろしく 赤 ウェアラブル・プロシージャ』です。 装画 にしさかきみこ
-

【新刊】『海猫沢めろん随筆傑作選 生活』海猫沢めろん
¥2,750
四六変形判/256ページ 文筆業を生業としてから確実に人生が狂っている――現代を生きる流浪の作家。海猫沢めろんの珠玉のエッセイ集。苦悩と笑いが織りなす、人生の軌跡と奇蹟20年の記録。 海猫沢 めろん 1975年、大阪府生まれ。2004年『左巻キ式ラストリゾート』でデビュー。『キッズファイヤー・ドットコム』(野間文芸新人賞候補)で熊日文学賞を受賞。近著に『ディスクロニアの鳩時計』がある。
-

【新刊】『エレベーターのボタンを全部押さないでください』川内有緒
¥1,980
SOLD OUT
四六判・並製/256ページ いつも広い世界を見せてくれるノンフィクション作家・川内有緒、初のエッセイ集。 『パリでメシを食う。』でデビューし、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』で「Yahoo! ニュース|本屋大賞ノンフィクション本大賞」を受賞した川内有緒が、連載していた「日経新聞」、雑誌「ひととき」など、さまざまな媒体に寄稿したエッセイをセレクトして収録。 メキシコの走る民族、飼っていた2匹の個性的な猫、大反響を巻き起こした「荒れた海で愛を叫ぶ」……。海外での驚くべき旅や出会い、日常に潜む冒険のような出来事、死生観などを綴り、読者を新しい場所へ誘う。 ユーモラスで味わい深い文章に心が揺さぶられ、温かな感情が湧き上がる。なぜか一歩を踏み出したくなる川内有緒ならではの一冊。 川内さんは丸腰で荒海に飛び込んでいって、宝物のような出会いをつかみ取ってくる。 この本そのものが、冒険で、旅なのだ。――岸本佐知子(翻訳家) 並外れた行動力と筆致。見たことない球をぶんぶん投げてくる。――こだま(作家・エッセイスト)
-

【新刊】『おこさま人生相談室 おとなのお悩み、おこさまたちに聞いてみました』小林 エリカ
¥2,200
四六判並製/348p 「なに? もっとこどもみたいにいうと思った?」 ――Ricoさん(7歳) 自分をかわいいと思えない。 父を老人ホームに入れたい。 地球温暖化への無関心が気になる――。 おとなたちの本気の悩みに、おこさまたち102人が本気で向き合う「いつもと逆」の人生相談。人気WEB連載、待望の書籍化! 「よくよく考えてみれば、年を重ねたからといって偉くなれるわけでもないし、いつも正しい答えを知っているとはかぎらない。 おとなだって悩むこともあるよね。 ひょっとすると、こどもの方が答えを知っていることだって、あるかもしれないよね。 というわけで、おこさま人生相談室、始めました。」 ――「はじめに」より ★本書に収録された、おこさまたちの回答より 「しあわせだったらいいかな」 「アニメ観て、ちょっといっぷく」 「2回深呼吸」 「軽い嘘とか役に立つこととかありますんで」 「わがままでいいよ」 「ほしゅわ ほしゅわは~」 「あさ娘さんを抱きしめて」 「理解を深めれば自分の気持ちも変わる」 「神様がくれた命を大切にしてほしい」 【著者略歴】 小林エリカ〈こばやし・えりか〉 1978年生まれ。作家、アーティスト。 著書に小説『女の子たち風船爆弾をつくる』(毎日出版文化賞受賞)、『最後の挨拶 His Last Bow』、『トリニティ、トリニティ、トリニティ』、他。エッセイ『彼女たちの戦争 嵐の中のささやきよ!』、コミック『光の子ども』シリーズ、絵本『わたしは しなない おんなのこ』。訳書にサンギータ・ヨギ『わたしは なれる』。国内外の美術館やギャラリーでテキストと呼応するような展示もおこなう。 現在、「MilK MAGAZINE japon」で「おこさま人生相談室」第2弾を連載中。
-

【新刊】『よくわからないまま輝き続ける世界と 気づくための日記集』古賀及子
¥1,870
四六判並製/304ページ 岸政彦さん・花田菜々子さん推薦! ZINE発!日記文学の新星が綴る小さな試み“やってみた” いつもの日常に小さな試みを取り入れてみたら――? *** 2024年の6月から10月のあいだ、週に3日から4日、“暇をふせぐ”ための簡単なトピックを生活に組み入れてみることにした。その日々の日記をまとめたのがこの本だ。 ポリシーを破ってめぐりめぐって日記を書くために何かし続けた。そこには非日常ではない、日常がかすかにふるえるような手応えがあった。 *** 23年ごしでハーゲンダッツのクリスピーサンドを食べる / 喫茶店で回数券を買う / 朝のラジオを外で聴く / かつてのバイト先に行く / 小学生の頃に読んでいた少女漫画雑誌を買う / 資格を取ろうと思い立つ / 駅にあるワーキングブースを使う 等々…! やったことないけど、ちょっと気になる…日常にあふれている小さな試み。 よくわからないまま輝き続ける世界に飛び込んで、得た気づきを集めた日記本です。
-

【新刊】『不確かな日々』星野文月
¥1,980
四六判並製/ページ 半年間の揺れる日々の記録。 思うようにいかない日々の中で、自分の現在地を確かめるように書きながら暮らした、半年間の記録。 まとまらない気持ちを抱きとめながら、今ここで感じていることに耳を澄まし続けた時間。 『私の証明』『プールの底から月を見る』、me and you little magazine連載「呼びようのない暮らし」を経て綴られた、全編書き下ろしの3年ぶりの新刊です。(版元サイトより)
-

【新刊】『しゅうまつのやわらかな』浅井音楽(サイン本)
¥1,980
四六判並製/224ページ(サイン本) ―鮮明に思い出せることほど、ほんとうは忘れられたことなのかもしれない。 忘却と喪失。停滞と安寧。異端の言語感覚で綴られる、過ぎ去った日々の心象。 随筆。小説。詩。日記。変幻自在に境界を超える筆致が織りなす待望の随想集。 装画:つくみず 装丁:名久井直子