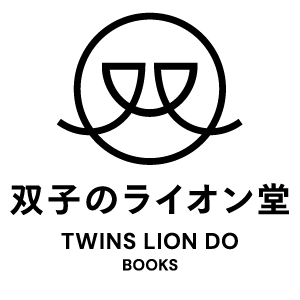-
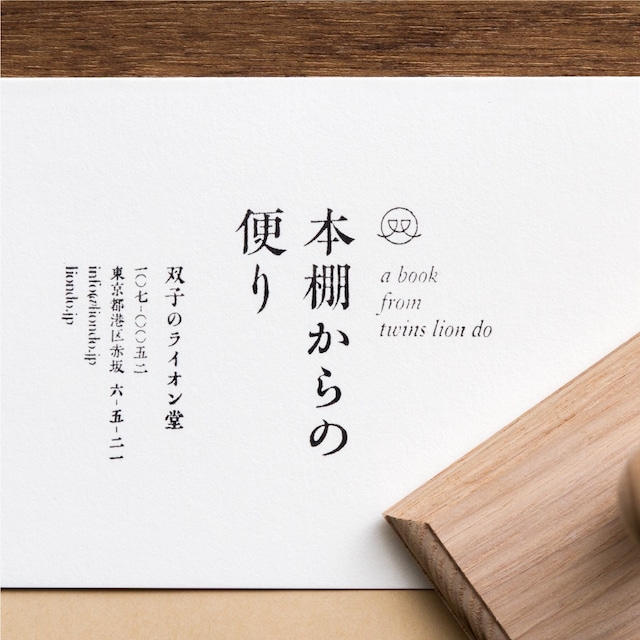
【選書配本サービス】『本棚からの便りー新刊プランー(3ヶ月間)』
¥14,600
***サービス内容をご理解のうえご注文ください*** 双子のライオン堂が、提供している選書配本サービス『本棚からの便り』の新刊3ヶ月プランです。 店主が、あなたの本棚を見て、書店員として「この本棚のラインナップなら、この本も合うだろうな」「この本も一緒に読んでほしいな」と思う本を届けます。 毎月「半年以内に発刊された新品の本」と「既刊の新品の本」が1〜2冊、届きます。 1冊の場合は、なるべく「半年以内に発刊された新品の本」(やむおえず既刊や古典が1冊の場合もあります)を予定。 *3ヶ月の期間合計額は10000円(税抜)で、1ヶ月平均3300円(税抜)分の本が届きます。 <例>(全て税抜) 1ヶ月目に「2000円の単行本」と「500円の文庫本」 2ヶ月目に「3000円の単行本」 3ヶ月目に「2500円の単行本」と「1500円の新書」と「500円の文庫」 が届きます。 ★確認事項★ (1)本サービスは、お客様の本棚の写真を見せて頂き、その本棚に書店員の視点で追加したい本を選びます。いつか出会っていて良かったと思えるような本をなるべくお届けします。 (2)普段は手を出さない、読まない分野の本に出会いたい方向けです。すでに欲しい本が決まっている、固定の好きなジャンルしか読みたくない、という方にはおすすめできません。 【新刊プラン(3ヶ月)】 費用:14,600円(税込) 期間:3ヶ月 ・期間の合計で、税込11,000円分の新刊本が届きます。 ・税込3600円分は、3回分の送料と選書費用です。 ◯留意(ご注文してくださった場合、下記に同意したものといたします)◯ ※当サービスは、あなたに今すぐマッチした本が届くというものではございません。 ※こちらの商品は後払い・着払いが出来ない商品です。 【システムの関係で、後払い・着払いを不可にできません。選ばれた場合は、再度注文をお願いすることになります。ご注意下さい。】 ※システムからのメールの中に、アンケートフォームがあります。到着後1週間程度でご回答をお願い致します。アンケート返信の翌月末から配本開始します。 ※商品画像はサンプルです。デザインが多少変更する場合があります。 ※実際に注文後にサービスが合わない場合は、1ヶ月目の到着から20日以内であり、本を返送いただければ、1回目の送料を除く全額を返金致します。(返金手数料はお客様負担にてお願います)
-

対話型選書サービス「ブックディアロゴス」(β)
¥6,600
SOLD OUT
新しいサービスを開始します。 名前を「対話型選書サービス「ブックディアロゴス」(β)」と言います。 ディアロゴスは、ギリシャ語で対話を意味する言葉です。 「選書ディアロゴス」は「本に関する対話」という意味の造語です。 「選書」も日常では聞きなれない言葉ですが、いろいろな本屋さんが選書サービスを始めていることもあり、少しずつではありますが「本を選ぶ」こととして認知されていっているように感じます。 双子のライオン堂でも、2015年から「本棚からの便り」という選書配本サービスはじめました。約8年間続けて、延べ人数900人をこえる方に選書をしてきました。 「本棚からの便り」では、思いも寄らない本と出会っていただくために、あえてお客様との直接のコミニュケーションを減らし、お客様の本棚の写真を送っていただいて、「この棚主には、いつかこの本を読んで欲しい」と思う本をお送りしています。 「ブックディアロゴス」では、お客様としっかりお話しをした上で、いま必要だと思う本を選びます。(当店ですぐに買わなくてもいいですし、他の最寄りの本屋さんで買ってもOKです。) お話の内容はなんでも構いません。 仕事の悩み、プライベートのこと、最近読んだ本、観た映画、本の読み方、好きな本屋さんのこと・・・など。 「本は読みたいけど何を読んだらいいかわからない」「面白いって話題の本を読んだけどモヤモヤする」「自分の本の読み方は正しいの?」「本の感想を話したい」という人におすすめです。 【内容】 オンラインまたはリアルで、45分間の対話をして、それを元に本を3冊程度、選書します。 <選書の流れ> ■事前 ・日程調整(メールまたはお電話) ・アンケートと本棚の写真を送る。 ↓ ■当日 ・概要説明(2〜3分) ・事前アンケートの確認(2〜3分) ・対話(20分) ・選書(15分) ・まとめ(5分) ↓ ■事後 選書した本のリストを送付。 *本をお送りするサービスではありません。 *オンラインはZOOMを使用します。 *都合があえば24時間対応します。 *リアルでの対話がご希望の場合は、基本店舗(東京赤坂)にご来店いただきます。 *出張も承りますが、別途交通費を実費でいただきます。
-

「百年ししの友」第5期(2025/08/01〜2026/7/31)
¥10,000
いつも当店をご利用、応援いただきありがとうございます。 「100年残る本と本屋」をモットーに、本屋が生き残る方法を日々模索している双子のライオン堂ですが、2025年4月27日で12周年を迎えました。 これまでも、これからも100年先まで残るための試行錯誤をしています。 そんな双子のライオン堂を応援してくだい。 どうぞ、よろしくお願いいたします! ============== 【「百年ししの友」第5期の内容】 期間:2025年8月1日から2026年の7月末まで。 料金:10,000円(1年間分) 【特典】 1)会員証 *入会時にお送りします。 2)3000円分の双子のライオン堂通貨(GAO)発行券。 *リアル店舗で使えます。期限は100年。 *譲渡も可能。 *入会時にお送りします。 3)双子のライオン堂出版部のグッズプレゼント(年1回) *2〜3種類から1つ選ぶ。 *入会時にお送りします。 4)読書会(イベント)ポイントカード *5個、10個で粗品(12個スタンプで次回ゴールド会員) *オンライン・現地(要申請) 5)会員限定のその他のコンテンツをお届け! (たまに会報メールや限定ラジオなど送るかも) 6)会員限定イベントの参加 (交流会を2025年12月、2026年7月に予定。オンライン現地ハイブリット。上半期下半期におすすめだったコンテツ紹介する) <会費の用途> ・双子のライオン堂の運営・宣伝広報および実験的企画。 ・本屋・文芸創作活動への支援・後援。
-

【イベントチケット】講座「お笑いを〈文学〉する」(講師:小田垣有輝)【4回〜6回の通しチケット】
¥5,400
SOLD OUT
※この商品は、4回〜6回の通しチケットです。 ※チケットをお送りさせていただきます。 このたび双子のライオン堂では、小田垣有輝さんを講師にお招きして講座「お笑いを〈文学〉する」を開催します。 「お笑いを〈文学〉する」は、ワークショップ形式で、現代の「お笑い」のネタを軸に、古今東西の文学との比較を通じて、どうしてそのネタが「笑える」のか、「文学的」とも言えないだろうか、という問いを、参加者の感想や批評もお聞きしつつ、分析していきます。 講師は、国語教師であり、作家としても活動している小田垣有輝さんです。小田垣さんは「地の文のような生活と」という文芸誌を発行し、小説や批評作品も精力的に発表しています。また実際に学校の授業でも文学作品を教える際に、生徒に馴染みのある「お笑い」ネタを活用して、文学理論を教えています。 講座は、全部で6回を予定しています。全部参加してもらえると嬉しいですが、毎回完結した内容なのでどこから参加してもOKです。(前半後半に分けての通しチケットと各回のチケット販売があります) 課題の作品やネタは事前に見たり読んだりしてきて頂く前提で会は進行します。 <基本情報> 開催日:毎月第3金曜日、19時半〜 場所:双子のライオン堂(東京都港区赤坂6−5−21−101) 費用:2000円(お得な4〜6回通しチケットもあり) <講座全体の概要> 「お笑い」とはなんでしょうか。 漫才、コント、コンビ、トリオ、ピン芸人、王道、シュール…その形態やジャンル、ネタの内容は多岐に渡っています。 ただ、いずれのネタも、それを観た人々は「笑う」という同一のリアクションを取ります。それぞれの芸人のネタは千差万別なのに、どうしてみんな「笑う」のでしょう。 千差万別に見えるそれぞれのネタも、「笑い」というリアクションに繋がる同一の構造を持っていると考えられます。 お笑いのネタもフィクションの一種です。そして、言葉を媒介にして構成されている。つまり、同じように言葉によって構成される「文学」と近しい場所にあるはずです。 このワークショップ(教室?)では、お笑いの構造を文学理論を用いて明らかにしつつ、類似した文学作品と比較検討することで、文学との共通点・差異を考えていきます。 東京03、ラーメンズのような緻密なネタから、トム・ブラウン、ランジャタイなどの不条理ネタも扱っていきます。 なぜ私たちは笑うのか。そもそも笑うとは何か。お笑いと文学の関係を考えながら、それらの問いに接近していきましょう。 各回の詳細は、下記ページよりご確認ください。 https://liondo.jp/?page_id=3972 <スケジュール> ※このチケットは1回〜3回の通しチケットです。 前半 第1回 6月21日(金) 19:30〜21:00 第2回 7月19日(金) 19:30〜21:00 第3回 8月16日(金) 19:30〜21:00 後半 第4回 9月20日(金) 19:30〜21:00 第5回 10月18日(金) 19:30〜21:00 第6回 11月22日(金) 19:30〜21:00
-

【イベントチケット】講座「お笑いを〈文学〉する」(講師:小田垣有輝)【1回〜3回の通しチケット】
¥5,400
SOLD OUT
※この商品は、1回〜3回の通しチケットです。 ※チケットをお送りさせていただきます。 このたび双子のライオン堂では、小田垣有輝さんを講師にお招きして講座「お笑いを〈文学〉する」を開催します。 「お笑いを〈文学〉する」は、ワークショップ形式で、現代の「お笑い」のネタを軸に、古今東西の文学との比較を通じて、どうしてそのネタが「笑える」のか、「文学的」とも言えないだろうか、という問いを、参加者の感想や批評もお聞きしつつ、分析していきます。 講師は、国語教師であり、作家としても活動している小田垣有輝さんです。小田垣さんは「地の文のような生活と」という文芸誌を発行し、小説や批評作品も精力的に発表しています。また実際に学校の授業でも文学作品を教える際に、生徒に馴染みのある「お笑い」ネタを活用して、文学理論を教えています。 講座は、全部で6回を予定しています。全部参加してもらえると嬉しいですが、毎回完結した内容なのでどこから参加してもOKです。(前半後半に分けての通しチケットと各回のチケット販売があります) 課題の作品やネタは事前に見たり読んだりしてきて頂く前提で会は進行します。 <基本情報> 開催日:毎月第3金曜日、19時半〜 場所:双子のライオン堂(東京都港区赤坂6−5−21−101) 費用:2000円(1〜3回の通しチケットもあり) <講座全体の概要> 「お笑い」とはなんでしょうか。 漫才、コント、コンビ、トリオ、ピン芸人、王道、シュール…その形態やジャンル、ネタの内容は多岐に渡っています。 ただ、いずれのネタも、それを観た人々は「笑う」という同一のリアクションを取ります。それぞれの芸人のネタは千差万別なのに、どうしてみんな「笑う」のでしょう。 千差万別に見えるそれぞれのネタも、「笑い」というリアクションに繋がる同一の構造を持っていると考えられます。 お笑いのネタもフィクションの一種です。そして、言葉を媒介にして構成されている。つまり、同じように言葉によって構成される「文学」と近しい場所にあるはずです。 このワークショップ(教室?)では、お笑いの構造を文学理論を用いて明らかにしつつ、類似した文学作品と比較検討することで、文学との共通点・差異を考えていきます。 東京03、ラーメンズのような緻密なネタから、トム・ブラウン、ランジャタイなどの不条理ネタも扱っていきます。 なぜ私たちは笑うのか。そもそも笑うとは何か。お笑いと文学の関係を考えながら、それらの問いに接近していきましょう。 各回の詳細は、下記ページよりご確認ください。 https://liondo.jp/?page_id=3972 <スケジュール> ※このチケットは1回〜3回の通しチケットです。 前半 第1回 6月21日(金) 19:30〜21:00 第2回 7月19日(金) 19:30〜21:00 第3回 8月16日(金) 19:30〜21:00 後半 第4回 9月20日(金) 19:30〜21:00 第5回 10月18日(金) 19:30〜21:00 第6回 11月22日(金) 19:30〜21:00