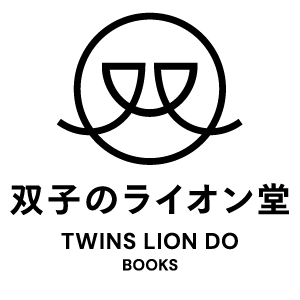-

【新刊】『高円寺グルメガイド 青』海猫沢めろん
¥750
A6横とじ/32P 海猫沢めろんさんによる高円寺グルメガイドの最新版、青です。 最初の「高円寺グルメガイド」はこちら! https://shop.liondo.jp/items/103640701
-

【新刊】『「若者の読書離れ」というウソ: 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』飯田一史
¥1,078
新書判・ソフトカバー/264ページ この20年間で、小中学生の平均読書冊数はV字回復した。そんな中、なぜ「若者は本を読まない」という事実と異なる説が当たり前のように語られるのだろうか。各種データと10代が実際に読んでいる人気の本から、中高生が本に求める「三大ニーズ」とそれに応える「四つの型」を提示する。「TikTok売れ」の実情や、変わりゆくラノベの読者層、広がる短篇集の需要など、読書を通じZ世代のカルチャーにも迫る。
-

【新刊】『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』飯田一史
¥1,540
新書判・ソフトカバー/288ページ 日本人の本の「読む量」は減っていない。「買う量」が減っている。 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の著者による、本の「売上を伸ばす」ための提言。 「本が売れない」と1990年代後半から言われ始め、四半世紀以上経った。書店の閉店が相次ぐなか、2024年以降、国策による書店振興への取り組みが話題を集めた。だが、それらで語られている現状分析には誤りが含まれている。出版産業の問題は読書(読む)量ではなく購買(買う)量である。本書ではまず、出版業界をめぐる神話、クリシェ(決まり文句)を排して正しい現状を認識する。その上でデジタルコミック、ウェブ小説、欧米の新聞や出版社、書店の先進事例やマーケティングの学術研究から判明した示唆をもとに、出版社と書店に共通する課題ーー「売上を伸ばす」ために何ができるかを提案していく。
-

【新刊】『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか: 知られざる戦後書店抗争史』飯田一史
¥1,320
新書判・ソフトカバー/366頁 かつて本屋は「帰り道にふらっと寄る」場所だった。だが、いつのまにか町から本屋の姿はなくなり、「わざわざ行く」場所になってしまっている。いったいいつから、どのようにして、本屋は消えていったのか? 本書では、出版社・取次・書店をめぐる取引関係、定価販売といった出版流通の基本構造を整理した上で、戦後の書店が歩んだ闘争の歴史をテーマごとにたどる。 公正取引委員会との攻防、郊外型複合書店からモール内大型書店への移り変わり、鉄道会社系書店の登場、図書館での新刊書籍の貸出、ネット書店の台頭――。 膨大なデータの分析からは、書店が直面してきた苦境と、それに抗い続けた闘争の歴史が見えてくる。「書店がつぶれていく」という問題の根幹を明らかにする一冊。
-

【新刊】『AI先生のSF小説教室 ─ クリエイティブVibe ライティング入門』樋口恭介
¥1,980
四六/280ページ 読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している!AIによる小説執筆入門の決定版。 書き始めない言い訳として、「時間がない」も「才能がない」もLLM(Large Language Model/大規模言語モデル)の前では)通用しない。 ── 九段理江 ChatGTP、Claude、Geminiなど生成AIによって、SF、ミステリ、ホラー、ライトノベルなどジャンル小説の書き方は劇的に変わった。 AI推進のコンサルタントであり、作家・批評家でもある著者が、作家を志す人に向けてAIを活用した小説執筆のプロセスを詳細に解説。 SF短編小説『量子図書館の調律師』を執筆する全過程(アイデア、主題、キャラクター設定、プロットづくり、シーン設計からブラッシュアップまで)をさまざまなプロンプトとともに公開。 ソフトウェア開発のトレンドである「Vibe Coding」の手法を小説執筆に応用したメソッドで、読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している。AIによる小説執筆入門の決定版! ──────────────────────── “創作の世界において、まさに革命的な時代が始まっています。100年前の作家たちがタイプライターの登場に目を見張り、その可能性に胸を躍らせたように、私たちは今、LLMという新たな創作メディアの黎明期に立ち会っているのです。未来の作家たちは、この時代をどのように回顧するでしょうか。おそらく、「テクノロジーと人間の創造性が、かつてない形で融合し始めた、刺激的な転換点」として記憶されるのではないでしょうか。”(「はじめに」より) ──────────────────────── 【目次】 はじめに LLM(Large Language Model/大規模言語モデル)初心者のための基礎知識 序章 Creative Vibe Writing とは Chapter 1 5分でAI小説を書いてみよう(超速ハンズオン) Chapter 2 Vibe設計ワークショップ Chapter 3 キャラクターを生成する Chapter 4 世界観を構築する Chapter 5 プロットとシーン設計 Chapter 6 スタイル & 声のコントロール Chapter 7 反復改良と編集術 Chapter 8 小説のブラッシュアップと完成 Chapter 8.5 AI時代の創作倫理と著作権:共創の未来を考える(特別コラム) 付録1:他ジャンルへの応用──CVWの可能性を広げる 付録2:AI共創コミュニティと未来のコラボレーション 付録3:実践トラブルシューティングガイド──AIとの対話で困ったときに 付録4:用語集と推薦リソース──CVWの旅をさらに深めるために あとがき
-

【新刊】『小説を書くこと、続けること、世界と繋がること』〈対談録 太田の部屋2〉太田靖久・旗原理沙子
¥990
新書判/82頁 双子のライオン堂書店で、連続で開催している小説家の太田靖久さんと様々なクリエーターが「つくる」をテーマに語り合う配信イベントのZINEのシリーズ第2弾を刊行します。 第2弾は、小説家・旗原理沙子さんと行った対談と、文学賞を受賞した旗原さんに太田さんが追加で7つの質問を送り、それに応答するエッセイを収録しました。 <基本情報> 書名:『小説を書くこと、続けること、世界と繋がること』〈対談録 太田の部屋2〉 著者:太田靖久・旗原理沙子 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年11月23日(文学フリマ東京) 予価:900+税 判型:新書判、並製 ページ:82頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)、『犬の看板探訪記 関東編』(小鳥書房)など。文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店や図書館での企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号で出店も行っている。 旗原理沙子(はたはら・りさこ) 小説家。1987年群馬県生まれ、東京、大阪など転々として育つ。2021年、「代わりになる言葉」を電子書籍で刊行しインディーズデビュー。2024年「私は無人島」で第129回文學界新人賞受賞。「犯罪者と私」( 文學界2024年12月号)など。 <「はじめに」> 本書には私と旗原さんの対談(2023年11月開催)を再構成したテキストに加え、その約2年後(20 25年8月)の私からの7つの問いに対する旗原さんの応答形式のエッセイを収録しました。 旗原さんは2024年に『文學界』新人賞を受賞されているため、対談はその前の出来事であり、エッセイはその後のこととなります。 社会通念としては新人賞の受賞を機に対外的にも作家と認められるのかもしれませんが、物事の本質はそれほど単純ではないでしょう。小説を書き続けていなければその人は小説家ではないのかもしれません。 旗原さんにとっての変わるもの/変わらないものの軌跡を追うことで見えてくる景色があります。それは旗原さんの独自の経験でありながら、たしかな普遍性があり、広く創作にかかわる人たちの参考にもなるはずです。(太田靖久)
-

【新刊】『ひとり出版入門』宮後優子
¥2,420
SOLD OUT
四六判/ どうやって本をつくる? どうやって運営していく? ひとり出版ノウハウのすべて。 本の制作と販売、出版社登録、書誌情報登録、書店流通、在庫管理、翻訳出版、電子書籍、さまざまなひとり出版の運営についてまとめられています。 著者 宮後優子 装幀 守屋史世(ea) 編集 小林えみ、宮後優子 校正 牟田都子 印刷 藤原印刷 <目次> はじめに 1章 本のつくり方 本をつくるプロセス 1 企画を立てる 2 著者と打ち合わせする 3 企画書をつくる 4 原価計算をする 5 企画内容を確定する 6 台割とスケジュールをつくる 7 著者に原稿を依頼する 8 原稿整理をする 9 写真撮影や図版の手配をする 10 デザイナーに中ページのデザインを依頼する コラム:デザイナーの探し方 11 ISBNを割り振る 12 デザイナーに表紙のデザインを依頼する 13 束見本を発注する 14 用紙を確定して印刷代を計算する コラム:コストをおさえ美しい本をつくるコツ コラム:書店流通で避けたほうがいい造本 15 著者編集者が校正する 16 校正者が校正する コラム:校正者、翻訳者の探し方 17 文字や画像をDTP で修正する 18 定価を決めて注文書を作成する 19 受注して刷り部数を決める コラム:書店への訪問営業 20 書誌データを登録する 21 印刷所へ入稿する コラム:紙見本の入手方法 コラム:印刷所の選び方(おすすめ印刷所リスト) 22 色校をチェックする 23 色校を印刷所へ戻す(校了) 24 電子書籍を作成する(必要があれば) 25 刷り出しや見本をチェックする 26 制作関係者やプレスに見本を送付する 27 販促をする(イベント企画やプレスリリースの作成) 28 請求書をもらい支払い処理をする 29 書店で確認する 30 発売後の売れ行きを見ながら追加受注する コラム:売上の入金時期 コラム:直販サイトのつくり方 コラム:本の発送料をおさえるコツ コラム:倉庫のこと 番外編 翻訳出版 1 翻訳したい本の原書、PDFを入手する 2 原書出版社に版権の問い合わせをし、オファーする 3 版権取得可能なら、契約と支払いをする 4 翻訳書を制作し、原書出版社のチェックを受ける 5 翻訳書を出版する 2章 本の売り方 書店流通のために必要なこと 書店への配本の流れ 出版物の流通方法を決める 1 版元直販(直販サイト、イベントでの販売) 2 別の出版社のコードを借りる(コード貸し) 3 Amazonと直取引で売る(e 託) 4 書店と直取引で売る 5 トランスビューの取引代行で流通 6 中小取次経由で流通 7 大手取次経由で流通 電子書籍の流通 コラム:Book&Design の場合 コラム:図書館からの注文 3章 ひとり出版社の運営 ビーナイス 烏有書林 西日本出版社 よはく舎 ひだまり舎 コトニ社 みずき書林 Book&Design URLリスト、索引 参考文献 おわりに 宮後 優子 (ミヤゴ ユウコ) (著/文) 編集者。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業後、出版社勤務。1997年よりデザイン書の編集に従事。デザイン専門誌『デザインの現場』『Typography』の編集長を経て、2018年に個人出版社・ギャラリーBook&Design を設立。日本デザイン学会会員。共著『要点で学ぶ、ロゴの法則150』(BNN)。 https://book-design.jp/
-

【新刊】『お笑いを〈文学〉する〜「笑える/笑えない」を超える』小田垣有輝(サイン本)
¥1,210
新書判/120頁 双子のライオン堂書店で、開催した連続講義「笑いを〈文学〉する」が書籍になります。 2024年に小田垣有輝さんをお招きして開講した授業を、書籍化に伴い授業だけでは伝えきれなかった熱い思いと独自の論をブラッシュアップして展開します。 【目次】 はじめに 1、東京03と中島敦『山月記』~トリオネタの魅力/『山月記』って本当に二人? 2、ピン芸人の構造論―「語り」か「噺」か 3、「お笑い」と「コード」ー既存のコードへの「抵抗」と「逸脱」 4、トム・ブラウンをなぜ笑う?―文学史と小川洋子『貴婦人Aの蘇生』をヒントに 5、ランジャタイとラーメンズ―谷崎・芥川の文学論争と比較して 6、ランジャタイとシェイクスピア―文学と「おばけ」の関係 ―ランジャタイとは何か 付録 登場人物紹介&参考文献 おわりに 【基本情報】 書名:『お笑いを〈文学〉する 「笑える/笑えない」を超える』 著者:小田垣有輝 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:1100+税 判型:新書判、並製 ページ:120頁 発行元:双子のライオン堂出版部 【著者】 小田垣有輝(おだがき・ゆうき) 私立中高一貫校、国語科教員。今年で教員11年目。研究分野の専門は谷崎潤一郎、語り論。教員として働くかたわら、個人文芸誌『地の文のような生活と』を一人で執筆・編集・刊行(現在vol.1~vol.6まで刊行中)。本づくりを通じて、自らが帯びる特権性と向き合う。 <「はじめに」> なぜ人は、お笑いを観て笑うのでしょうか。 「お笑い」という名称からもわかるように、お笑いはお笑いを鑑賞する者に「笑う」という反応を要請します。小説であれば、もちろん笑える小説もあるし、泣ける小説もあるし、怒りを共有する小説もあるし、漠然としたもやもやを読者に植え付ける小説もあるし、小説を読む者の反応は様々である、ということが「当たり前」となっています。しかし、一般的にお笑いは「笑う」という反応に限定されます。ネタ番組では、観覧の人々はみな笑っているし、その中に泣いたり怒ったりする人はいません。 でも、お笑いを観て「笑う」以外の反応をしたっていいはずです。そうでなければ、「笑えるお笑い=良いお笑い」という評価軸しか存在しないことになります。お笑いの中には「笑えないけど良いお笑い」だって存在します。 本書では、物語論や社会学を媒介にしながら「お笑い」と「文学」の関係を考えていきます。そうすることによって「笑えるか否か」という評価軸とは違う軸が見えてきます。私たちが普段観ているお笑いを違った視点から批評することによって、お笑いが備えている豊かな世界が立ち現れるはずです。(小田垣有輝)
-

【新刊】『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉植本一子&太田靖久(Wサイン本)
¥990
新書判/84頁/Wサイン本 双子のライオン堂書店で、連続で開催している小説家の太田靖久さんと様々なクリエーターが「つくる」をテーマに語り合う配信イベントが、ZINEのシリーズになります。 第1弾は、2023年と2025年に植本一子さんと行った2つの対談を1冊の冊子にまとめました。 ZINEやリトルプレスについて考えて続けているお二人のそれぞれの視点が交差します。 自分でも”作ってみたい”人は必携の1冊です。 また、今後のシリーズとして刊行していきますので、ラインナップにもご注目ください! <基本情報> 書名:『書く人の秘密 つながる本の作り方』〈対談録 太田の部屋1〉 著者:太田靖久・植本一子 ブックデザイン:竹田ドッグイヤー 発売日:2025年5月11日(文学フリマ) 予価:900+税 判型:新書判、並製 ページ:84頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『ののの』(書肆汽水域)、『犬たちの状態』(金川晋吾との共著/フィルムアート社)、『ふたりのアフタースクール』(友田とんとの共著/双子のライオン堂出版部)、『犬の看板探訪記 関東編』(小鳥書房)など。文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店や図書館での企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号で出店も行っている。 植本一子(うえもと・いちこ) 写真家。2003年にキヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞。2013年、下北沢に自然光を使った写真館「天然スタジオ」を立ち上げる。著書に『かなわない』『愛は時間がかかる』、写真集に『うれしい生活』、小説家・滝口悠生との共著『さびしさについて』などがある。主な展覧会に『アカルイカテイ』(広島市現代美術館)、『つくりかけラボ07 あの日のことおぼえてる?』(千葉市美術館)。 <「はじめに」(太田靖久)> 植本一子さんとの2回のトークイベント(2023年9月と2025年3月開催)を再構成して追記等も行い、本書に収録しました。2回目は1回目の1年半後に行われたため、その間の変化も楽しんでいただけるはずです。 今企画は双子のライオン堂の竹田さんからの提案がきっかけでした。 「太田さんは質問がうまいのでゲストを迎える形式のトークイベントを定期開催するのはいかがですか?」 すぐに快諾しました。自分の話をするより、誰かの話を聞いていたいと思うのは、知らないことを知りたいというシンプルな好奇心が根っこにあるからです。 1回目のゲストは植本さんが良いなとひらめきました。植本さんの文章には親しみやすさがあるのに、決して安全なものではなく、深くえぐってくる強度もあります。そんな植本さんのやさしさと鋭さのバランスや、創作と事務作業の使い分けについてなど、様々に興味がありました。また、ZINEに関するトークイベントをほとんど行っていないとうかがい、貴重な内容になるという判断もありました。 植本さんには登壇だけでなく、〈つくるをかんがえる〉というタイトルも付けていただきました。それが企画の方向性を固めるうえで助けになったことも忘れずに記しておきます。(太田靖久)
-

【新刊】『Hukyu』GAMABOOKS(サイン本)
¥2,200
A5判/279ページ/諸星めぐるさんのサイン入り! 今をつなぐバーチャル文化普及史マガジン「Hukyu(ふきゅう)」創刊号です。 創刊号特集は「VTuber×民俗学」と題し、総勢26名のVTuber(&VTuber関係者)の インタビューを収録しています。 純粋にVTuberを楽しみながら、+αで新たな視点も得られる本になっていますので、 VTuber好きの方は是非気軽な気持ちでお手に取っていただけますと幸いです。 ---------------------------- 21世紀以降、私たちを取り巻く文化は想像以上に急激に変化し続けている。 かの柳田國男が闊歩した平地の都会や農村は、鉄の車が様々な燃料を元に動き回り、道行く人々は異世界につながる四角い窓を持ち歩いている。そしてかつての農耕文化の営みが都市民俗に変わっていったように、バーチャル文化と呼ばれるインターネット上にも様々な民俗がリアルタイムに生まれ、増殖し、息をしている。 雑誌『Hukyu』では、このような社会生活に包括されるバーチャル文化を、学際的な視点から立体的に取り上げていくことを目的とする、いまを生きる「私たちのための」普及誌である。このため、雑誌名には普及・不朽・不急・負笈などの意味を込めさせていただいた。 『Hukyu』における民俗学とは、伝統的民俗文化の回帰という、過去との懐古的な伝言ゲームを知ることだけが目的ではない。歴史は必ずしも一つではなく、語り継ぐ過去の先には現代に生きる日常と価値観が、同時多発的に存在している。 そして本誌は、ありのままをいまを「つなぎ」留め置くが、その後の変化やいまある他の見方を否定することはしない。掲載されるすべての人々の視点は導き出された「答え」であり、それぞれの「可能性」でもある。読者の方々には、ゆたかな好奇心に身を任せ、好きなページから手に取っていただき、自分自身の価値観との対話を楽しんでいただきたい。 (~Hukyu序文より一部抜粋~)
-

【新刊】『夏目漱石 美術を見る眼』ホンダ・アキノ
¥2,750
SOLD OUT
四六判/264ページ 「芸術は自己の表現に始つて、自己の表現に終るものである」 明治40年、東大教授を蹴って朝日新聞に入社した漱石は、折にふれ芸術に関する記事を紙面に綴り、自由で忖度のない持論を堂々と展開した。同時代の美術に漱石は何を見たのか、繰り返し強調した「自己の表現」とは何を意味するのか──。 “美術の門外漢”として書きのこした言葉から浮かび上がる独自の芸術観、そこから浮かび上がる、漱石の生きる姿勢とは? 各紙で書評続々の『二人の美術記者 井上靖と司馬遼太郎』著者による〈小説家×美術〉第二弾。 【目次】 はじめに 1 漱石の美術遍歴と美術批評の背景 一 子ども時代から積み重ねた美術体験 二 小説にあらわれた美術 三 教師をやめて新聞社員となる 四 過渡期にあった明治〜大正の日本美術界 2 同時代の美術を見る眼 一 独自の着眼点と向き合い方 二 「文展と芸術」 三 「素人と黒人」について 四 津田青楓君は「ぢゞむさい」 五 西洋美術と同時代の日本美術へのまなざしの違い 六 芸術批評が浮き彫りにした“生きる姿勢” 3 「自己の表現」とは何か 一 絵筆をとる漱石 二 「自己の表現」再考 おわりに あとがき 関連年表 主な参考文献
-

【新刊】『到来する女たち 石牟礼道子・中村きい子・森崎和江の思想文学』渡邊英理
¥2,640
四六判/400ページ/ 不揃いなままで「わたし」が「わたしたち」になる──。 1958年に創刊された雑誌『サークル村』に集った石牟礼道子、中村きい子、森崎和江が聞書きなどの手法で切り拓いた新たな地平を、『中上健次論』が話題を呼んだ著者が「思想文学」の視点で読み解く。 「『サークル村』を通して、彼女たちが手に入れたのは、儚い「わたし」(たち)の小さな「声」を顕すための言葉であったにちがいない。この新しい集団の言葉は、異質なものと接触し遭遇することで自らを鍛え、異質な他者とともに葛藤を抱えながらも不透明な現実を生きようとする言葉でなければならなかった。支配や権力、垂直的な位階制や序列的な差別から自由で、不揃いなままで水平的に「わたし」は「わたしたち」になる。 三人の女たちは、そのような「わたし」と「わたしたち」を創造/想像し、「わたし」と「わたしたち」とを表現しうる言葉を発明しようとしたのではなかったか」(渡邊英理) ・石牟礼道子(1927-2018)【熊本】……熊本県天草生まれ。詩人、作家。生後すぐに水俣へ。著書に『苦海浄土』『椿の海の記』『西南役伝説』ほか。 ・中村きい子(1928-1996)【鹿児島】……鹿児島生まれ。小説家、作家。母をモデルにした小説『女と刀』は大きな話題を呼び、木下恵介監督によりドラマ化もされた。 ・森崎和江(1927-2022)【福岡】……朝鮮大邱生まれ。詩人、作家。17歳で単身九州へ渡り、58年筑豊炭鉱近郊の中間に転居、谷川雁らと『サークル村』創刊。著書に『まっくら』『慶州は母の呼び声』『非所有の所有』など。
-

【新刊】『どれから読む? 海外文学ブックガイド 英語編』
¥1,540
B6判 166ページ/越前さんのサイン入り! これはNHK《基礎英語2》テキストの2022年4月号から2025年3月号までにリレー連載された中高生向けの海外文学紹介コラムをまとめて再構成・加筆したもので、2022年7月に河出書房新社から出た『はじめて読む! 海外文学ブックガイド』の続編にあたる本です。今回はページ数の関係で「英語編」を出すことにしましたが、将来、英語以外の作品を紹介するブックガイドの刊行も検討しています。
-

【新刊】『mg. vol.10 ふたたび珈琲をめぐる』
¥1,000
A5版/60ページ 食べものをテーマに思いをめぐらせるmg.の10冊目は、 初心にかえって珈琲をふたたび見つめます。 珈琲好きも珈琲嫌いもいるメンバーの企画をどうぞお楽しみください。 ふたたび珈琲をめぐる 目次 NOBEL 保留コーヒーは誰がために ESSAY 甘いパンとミルクコーヒー SPECIAL CONTENTS わたしとコーヒーのこと ESSAY 珈琲語りたがり COLUMN コーヒーオンチのデカフェモーニング COLUMN リキッドコーヒーばかり飲んでます GUEST COLUMN コーヒー&ホニャララ COLUMN MY BELOVED COFFEE CUP COLUMN 三つの街をめぐるコーヒーマグ COLUMN コーヒーリキュールであそぶ ESSAY アウェイな公園と、家のコーヒー おすすめぐり コーヒーがあるお気に入りの場所 NOBEL 心、凪ぐ
-

【新刊】『あの人の調べ方ときどき書棚探訪: クリエイター20人に聞く情報収集・活用術』平山亜佐子
¥2,530
SOLD OUT
四六判並製/360ページ 作家やライター、研究者、翻訳家、漫画家、編集者など各分野の第一線で活躍している総勢17組計19名(プラス著者で計20名)が、情報の収集方法や整理・活用のコツ、自慢の書棚と愛読書などを対談形式で紹介! 自分ならではの表現がしたい、興味あるテーマについて調べたい、視野を広め教養を深めたい……そのためにはどんな本を読み、どうやって情報を集めればいい? また、集めた情報をどんな風に整理して活用すればいいの? そんな疑問を抱いている人にとって、役立つヒントを探す宝庫になる1冊です。 本書は、自身も文献調査や情報収集・整理を得意とする著者が、動画プラットフォーム「シラス」で2023~2024年に配信していた人気動画シリーズをもとに、プラスαの内容を加えてまとめ直したもの。 主に情報収集・整理術を教えてもらう「1章 文献調査」と、実際に蔵書を拝見しながら本の扱い方や愛着などをお聞きする「2章 書棚探訪」による構成となっております。 書棚やピックアップされた本、デジタル化するためのツールなど豊富な写真を交えながらそれぞれのゲストの“流儀”を垣間見ることができます。
-

【新刊】『個展のつくりかた 展覧会を開きたい人のためのガイドブック』竹氏倫子
¥2,200
四六/224ページ 「個展を開くまでにどんな準備が必要?」 「作品は何点ぐらいあったらいいの?」 はじめて個展を開こうとする際には、さまざまな疑問が出てくるはずです。 本書は、絵画や写真、イラストなど日々制作活動をしている人が個展を開くまでのプロセスやポイントをまとめたガイドブックです。 具体的な作業内容だけでなく、展覧会の意義や心構え、美術館から得られるヒントなども分かりやすく解説。さらに「個展を開いて変わること」をテーマに作家やギャラリーとの対談も収録しています。個展だけでなく、二人展や三人展、グループ展にも生かせるヒントやアイデアが詰まった一冊です。 [目次] 1章 なぜ個展を開いたほうがいいのか ・展覧会もひとつの表現 ・展覧会はご縁をつくるところ ・展覧会は作家として名乗りを上げる機会 ・展覧会の種類 コラム 適切な出品作品の点数とは ・経費の考えかた ・リアルな展覧会とネット上の発表との違い コラム SNSやホームページ等をどう活用していくか 2章 個展をつくるための準備とプロセス ・個展ができるまで ・展覧会のスタイルを決める ・会期を検討する ・会場を選ぶ コラム 会期中のイベント ・作品をしぼり込む ・展覧会タイトルを考える ・作品の見せかたを考える コラム 額縁の役割とは ・展示構成を考える ・DM(案内はがき)をつくる ・ごあいさつ・ステートメント・作家略歴を作成する ・キャプションのつくりかた ・搬入・展示・撤去・搬出の計画を立てる 3章 開催中の過ごしかた・展覧会が終わったら ・展覧会がオープンしたら ・来場者の言葉をどう聞くか ・展覧会は、自作をふりかえるタイミング ・展覧会が終わった後 4章 より自分らしい作品をつくるために、美術館からヒントを得る ・美術館はヒントの宝庫 ・作品のサイズと空間の大きさの関係 コラム 実際に作品の前に立ち、その存在感を体験しよう ・作品の魅力を引き出すタイトル ・サインに注目する コラム さまざまな技法を知る ・展示方法のアイデアを得る ・ポスター、チラシをチェックする ・作家の姿勢に学ぶ 対談 個展を開いて変わること ・イラストレーター Claraさん ・農学博士、日本山岳写真協会員 時本景亮さん ・ギャラリーそら 安井敏恵さん、池田真木さん
-

【新刊】『軟式ボールの社会学: 近代スポーツの日本的解釈の可能性』三谷舜
¥3,300
A5/240ページ 軟式に向けられる「損なイメージ」を覆す 野球、ソフトボール、テニスで使用されるボールの1種である「軟式ボール」に着目し、スポーツの構成要素である「用具」が、スポーツが持つおもしろさや教育性といった内在的な価値にいかに関わっているのか、人々がそれらをどのように受容し、発展させてきたのかを明らかにする。 軟式野球、軟式テニスといった軟式ボール競技は、敗戦後の物資不足と教育現場での普及の中で日本独自に発展した。そのような軟式ボールの発明と普及は、「近代スポーツの日本的解釈」の発明と普及の系譜であるとも言えよう。 おもな目次 序 章 軟式ボールを取り巻く状況 スポーツ用具をめぐるポリティクス スポーツ用具とスポーツの価値を軟式ボールから考える 各章の概要 第1 章 スポーツ文化の誕生を「興奮の探求」から読み解くことの可能性 第1 節 スポータイゼーションとは何か 第2 節 スポーツにおける興奮の探求─ルールの制定と暴力の抑制 第3 節 近代スポーツの原理とスポータイゼーション 第2 章 軟式スポーツの現状と課題 第1 節 軟式スポーツを統括する中央競技団体の現状 第2 節 軟式スポーツの競技人口の推移と学校教育 第3 節 軟式スポーツのイメージ 第3章 軟式スポーツの文化はいかにして作られたのか 第1 節 軟式ボール誕生小史 第2 節 戦後日本のスポーツと軟式野球 第3 節 軟式スポーツの発展を「スポータイゼーション」として読む 第4 章 スポーツ用具とスポーツの「おもしろさ」の関係 第1 節 スポーツ用具と技術の分類 第2 節 テクノロジーがスポーツに与えた影響 第3 節 現代のスポーツと用具の関係 第5 章 軟式スポーツの今 第1 節 スポーツの都市化とアーバンスポーツの登場 第2 節 Baseball 5 とは何か? 第3 節 アーバンスポーツと「興奮の探求」 終 章
-

【新刊】『ゼロからの読書教室』 読書猿
¥1,760
四六/208ページ 読書猿、初の「薄い」本?! 秘伝の読書術をどこまでもやさしく、深く 読むのが遅い、面倒くさい、何を読んだらいいのかわからない……読書にあこがれはあっても、悩みは尽きないものです。そんな、読書にまつわる悩みの数々を、「正体不明の読書家」読書猿が一挙に解決! 「本は最初から最後まで通読しなくてはならない」「内容をしっかり理解しなくてはならない」など読書への固定観念が、読書に苦手意識を生む原因。そこから自由になる方法をやさしく伝えます。 大ベストセラー『独学大全』をはじめ、圧巻の「大全」を著してきた著者が、自身の「核」となる読書術を、かつてなく薄く読みやすく、それでいてどこまでも深くお届けします。「本は好きだけど読書は苦手……」読書への片想いはもう終わりです! 目次 第1部 本となかよくなるために……しなくてもいいこと、してもいいこと 第1回 全部読まなくてもいい 第2回 はじめから読まなくてもいい 第3回 最後まで読まなくてもいい 第4回 途中から読んでもいい 第5回 いくつ質問してもいい 第6回 すべてを理解できなくてもいい 第7回 いろんな速さで読んでいい 第8回 本の速さに合わせてもいい 第9回 経験を超えてもいい 第10回 小説なんて読まなくていい 第11回 物語と距離をおいていい 第12回 小説はなんでもありでいい 第2部 出会いたい本に出会うために……してみるといいこと、知っておくといいこと 第13回 いろんな本を知ろう 第14回 本の海「図書館」へ行こう 第15回 レファレンスカウンターに尋ねよう 第16回 百科事典から始めよう 第17回 百科事典を使いこなそう 第18回 書誌はすごい道具 第19回 書誌を使ってみよう 第20回 件名を使いこなそう 第21回 上位概念を考えよう 第22回 リサーチ・ナビを活用しよう 第23回 青空文庫に浸ろう 第24回 デジコレにもぐろう
-

【新刊】『タフラブ 絆を手放す生き方』信田さよ子
¥1,980
四六・並製/216ページ 侵入しない・させない関係をつくる。寂しさと共存し、穏やかに、やさしく、タフに暮らすために。 タフラブは、ベトナム戦争帰還兵のアルコール依存や暴力に苦しむ家族が「生きる術」として生み出した概念。「手放す愛」「見守る愛」などと訳されている。 東日本大震災以来、「絆」が困難を乗り越えるためのキーワードとして使われてきたが、「絆」は本来、牛馬などをつなぎとめる綱のこと。家族や世間の絆に苦しめられてきた人々のカウンセリングを長年続けてきた著者は「絆」に疑問符を投げかけ「タフラブ」という生き方を紹介する。『タフラブという快刀』(2009年)を改題し、加筆・修正・再編集した作品。 【目次】 序 章 タフラブの誕生 医療では救われない/勇気をもって手放す/戦争の落とし子/帰還兵の暴力/実体なき「人の心」 ほか 第一章 無法地帯 複雑に絡み合う現実/「崩壊」は悪いことか/「私」と「私」/「弱まる絆」論/持たざる者の希望/モテる男の証/社会の底辺で ほか 第二章 巨大なスポンジ 果てしない吸収力/性本能と母性本能/珍獣パンダ/父性と父権/正義の父/「私に任せなさい」/現代の秘境 ほか 第三章 切り分け 油と酢のように/母の愚痴を聞く娘/「切り分け」の法則/沈黙の臓器/必殺代理人/「問題」とは何か/除外される「父の問題」 ほか 第四章 覚悟と断念 寂しさとともに/結婚制度に囲い込まれ/「積みすぎた方舟」/「夫が娘を蹴ったんです」/久しぶりの深呼吸/四八パーセントの協力 ほか 終 章 関係からの解放 それは蜃気楼/控えめなリスク回避 【著者】 信田 さよ子 臨床心理士、日本公認心理師協会会長。1946年、岐阜県に生まれる。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。駒木野病院勤務、嗜癖問題臨床研究所付属原宿相談室室長を経て、1995年原宿カウンセリングセンターを設立。アルコール依存症、摂食障害、ひきこもり、DV、児童虐待に悩む人やその家族のカウンセリングを行ってきた。 著書に、『母が重くてたまらない』(春秋社)、『選ばれる男たち』(講談社現代新書)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)、『家族と国家は共謀する』(角川新書)などがある。
-

【新刊】『新版 読書のおとも』編著・岸波龍
¥1,000
SOLD OUT
サイズ:A4/ページ:58 海乃凧「読書する身体のための調律」 二見さわや歌「読書のおともにオカメサブレ」 奈良原生織「濃度/Nord」 岸波龍「マッチウォーター」 柿内正午「読書の感覚」
-

【新刊】『高円寺グルメガイド』海猫沢めろん(サイン本)
¥880
A6横とじ/32P/サイン本 俺の名前は海猫沢めろん。本名だ。雑文を書いて暮らしてる売れない作家だ。いろいろあって高円寺に住んでる。なんでここにいるのかはまあ俺のエッセイなんかを読めばわかるから説明しない。まさか人生の後半戦でこんなことになるなんてな。人生はうんざりするようなクソみてえなトラブルばっかりだ。それでも俺はこの街で暮らす俺が好きだ。高円寺って街はサブカルの聖地とか言われてるけど、要するに飲んだくれと飯好きが集まるカオスな場所だ。駅前はチェーン店もあるけど、一歩裏道に入れば個性的な店がゴロゴロしてる。狭い店、クセのある店主、謎のメニュー、全部ひっくるめて高円寺の味ってやつだ。 このグルメガイドは、そんな高円寺の飲み食いスポットをゆるーく紹介するもの。別に高級レストランとか洗練されたグルメじゃない。むしろ、安くてうまくて面白い店ばっかり。でもまあ、結局のところ店の良し悪しってのは雰囲気とタイミング次第。隣の席の常連がやたら絡んでくるのも高円寺の日常。酔っ払いが路上でギター弾いてるのも日常。そんな雑多な空気が嫌なら武蔵小杉とか東横線にでも行ったほうがいいかもな。とにかく、このガイドは高円寺の雑多なグルメを楽しみたい人向けだ。腹を空かせてふらっと歩けば、どこかしら面白い店に出くわすのがこの街のいいところだ。深く考えずに飲んで食って、この街のノリを楽しんでくれ。
-

【新刊】『めろんと檸檬を読む』海猫沢めろん(サイン本)
¥750
判型:A6/中綴じ/38P サイン本 双子のライオン度で開催された読書会が冊子になりました! 『梶井基次郎『檸檬』読書会 めろんと檸檬を読む』は、名作『檸檬』を題材にした読書会の内容をまとめた冊子です。 VR的想像力、ひそやかなたのしみ、語り直し、いきぐるしさ、技術と感性のバランス……12人の参加者がゆる〜く『檸檬』をかたります。
-

【新刊】『日記の練習』くどうれいん
¥1,870
SOLD OUT
四六判/256ページ 「おもしろいから書くのではない、書いているからどんどんおもしろいことが増える」 小説、エッセイ、短歌、絵本と幅広い創作で注目される作家、くどうれいん。その創作の原点は日記にあった。そんな彼女の日記の初の書籍化が本書である。日々の短文日記=「日記の練習」とそれをもとにしたエッセイ「日記の本番」をとおして浮かび上がる、作家くどうれいん一年間の生活と思考と情動。書かなかった日も、あまりに長くなってしまう日も、それこそが日常のなかの日記だ。
-

【新刊】『蛇の棲む水たまり』梨木香歩&鹿児島睦
¥2,200
15.3 x 1.1 x 19.5 cm/68ページ 「陶芸家の鹿児島睦さんの展覧会が開かれます。新作の器を見て、そこからお話を作っていただけませんか」 依頼を受けた作家の梨木香歩さんは、色や形のさまざまな器に草花に馬や象、蛇などの生き物が描かれた200点の作品を1枚ずつ、何度も繰り返し見ながら物語を紡ぎました。梨木さんの物語を受け取った鹿児島睦さんは、何度も読んで反芻し、ラストシーンに新しい1枚を制作しました。 このようにして生まれた本です。水たまりを見つけのぞき込む馬のように、水たまりに棲む蛇に、会いにいってください。